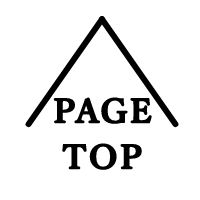――降り子
当会の創父・荻堂巧三(一九一四−一九七六)氏が天寿を全うしたのち、自身の〈生まれ変わり〉として現世に降臨させた少年少女のことをいう。
〈荻堂創流会『教典Ⅰ』 第二章「降り子」〉
◆ 吉沢癒知
儀式が始まる直前、癒知はいつもあの日のことを思いだす。三歳だった。
広大な施設には信徒が定期的に身体を動かすためのグラウンドがある。癒知はいつもその端っこにいた。イチョウの木の根もとに落ちた枝を拾い、覚えたばかりのひらがなを五十音順に書いては、誰かに褒めてもらいたくて近くにいる大人を呼びとめる。だが誰も癒知の相手などしてくれない。まだ教典も読めず、礼拝や創父さまの意味も理解できない。当時、施設にいる未就学児は癒知だけだった。
「ゆっちゃんにはまだ難しいからなあ」
大人たちだけでなく、小中学生の子たちにさえ適当にあしらわれる。
「まずは教典が読めるようにならんと。まだ漢字も読まれへんやろ?」
からかうような響きを拾い取り、癒知は頰をふくらませた。「読めるもん」と言い返し、一緒に遊ぼうと思って持参した木の棒や葉っぱを投げて駆け去った。
物心ついたころに貰った教典は漢字が多すぎる。しかも国語辞典ほど分厚いから重くてしかたない。焦げ茶の革張りの表紙も、そこに刻まれた金色の文字も威圧的だ。
癒知も読めないなりに何度か開いてはみたのだ。が、読みかたのわからない漢字に出会うたび、ふくふくした自分のちいさな手を頼りなく感じるだけだった。ページをめくるたび革のにおいが鼻をつく。大人のにおいだ。
「きょうは大事なお話があります」
ある朝の礼拝のあと、母に呼びとめられた。
「かんじのおべんきょうですか?」
すたすたと廊下をゆく小豆色の背中を追う。窓から射した朝陽が母の白いうなじに集まって、金色の産毛が光って見えた。
「いいえ」
突然立ちどまる。廊下には癒知と母しかいない。
「もっと大事な、あなたの人生にかかわることです」
母は癒知を振り返らなかった。ふたたび歩きだす。
「会議室へ行きます。ついてきてください」
癒知にとって会議室は「えらい大人しか入っちゃいけない場所」だ。そんなところに、なぜ三歳の自分が呼ばれるのだろう。
「おかあさま?」
いつもは静かな声で「はい、なんですか」と、癒知と目線の高さがあうようしゃがんでくれる母が、このときは振り返りもしなかった。左手の庭に面した窓にその横顔が映っている。白い頰が光っていた。耳を澄ませると、足音に混じって引き攣った呼気を吞みこむ音がする。母が泣いているところを見たのはそれが初めてだった。
会議室には支部長のほか、ここ近畿支部に属する幹部八名がそろっていた。
「お待ちしておりました、癒知さま」
ホワイトボードを背にした支部長が恭しく一礼する。幹部たちもそれに倣う。衣擦れの音がさわさわと重なりあった。
奇妙な沈黙のなか、癒知はぷっと吹きだした。
「ゆ、ゆちさまって」
支部長は昨日まで「ゆっちゃん」と呼んでいたのに、今朝はいきなり「癒知さま」だ。幹部たちまで三歳の自分にお辞儀をする。癒知はきょろきょろと大人たちを見まわす。
誰も笑い返してくれない。
大人たちの冷めた顔に熱を奪われるように、癒知の顔から笑みが抜けていく。笑ってはいけないというより、誰も自分の笑顔を求めていない、そんな空気を嗅ぎ取り、とたんに癒知は緊張した。これは、ごっこ遊びなんかじゃない。
降り子だと言われたとき、うれしかったのか、怖かったのか。いまでもわからない。会議室へむかう途中、母はなぜ泣いていたのか。それもわからない。これから歩んでいく降り子としての道が、まっすぐな心と身体をどんなふうに歪めていくのかも。
なにもかもわからないまま七年が経った。
礼拝堂の扉のまえにいた。分厚い観音扉のむこうから、マイクを通した支部長の朗々とした語りがくぐもって聞こえる。
「ただいまより、浄器の儀を執りおこないます。ここ荻堂創流会・近畿支部の降り子であられる癒知さまは、二〇一四年にこちらの世界へ降臨されました。幼くして開眼され、創父さまの魂をお身体に宿されたご神体です」
自分の紹介をされているあいだ、癒知は身じろぎもせず俯いている。真っ赤な口紅をひかれた唇がべたべたする。頭には黒塗りの網代笠をかぶっていた。そのさきから垂れた黒いベールが、視界を暗く翳らせていた。白帷子の内側の繊維がちくちくと肌を刺す。
「それでは、癒知さまに御入堂いただきます」
礼拝堂の内側から、観音扉がみっしりと軋みながら開く。春の冷えた廊下で待っていた癒知の頰に、暖房で乾いた空気がもわりとかかった。
儀式が終わり、礼拝堂から信徒たちがぞろぞろと廊下へでていく。
「癒知さま、ご苦労さまです」
祭壇のまえに残された癒知のもとへ森田が駆けよってきた。青々とした坊主頭の下で、牛乳瓶の底みたいな眼鏡が光っている。
「今日は信徒の人数が多かったですから疲れたでしょう。ええっと、ちょっと待ってくださいね。このあとの予定は……」
骨ばったおおきな手で、小豆色の作務衣のポケットからくしゃくしゃのメモ帳を取りだす。「すみません、まだ慣れないもので」と苦笑しながらページをめくった。
「日曜日やから、今日はこのまま部屋に戻るよ」
癒知は言いながら白帷子の帯を結び直した。冷えた指さきの動きが鈍い。
「あ、そうでした。あと春休みの宿題をチェックするようにお母さまから言われていますので、ちょっとお部屋にお邪魔しますね」
「はーい」
降り子には「世話役」という大人がつく。その名のとおり、降り子の身のまわりの世話と監督を担う人間だ。それまで癒知の世話役は五十代の女だった。宗教団体の幹部というより、修道院のシスターといったほうがしっくり来る柔和な雰囲気をまとっていた。その彼女が先月、関東の支部へ移ることになり、入れ替わりでやってきたのが森田だ。二十四歳の彼は「若者の宗教離れ」をテーマにした大学の卒業論文が本部から高い評価を受けて幹部候補生になり、研修の一環として癒知の世話役につくことになったらしい。
信徒たちの熱気とにおいを残した静かな礼拝堂をでた。本棟一階の廊下をすすむ。窓を開けた際に入りこんだのか、桜の花びらが何枚か落ちていた。
「もうすぐ一学期ですね。小四かあ、懐かしいな」
森田がおおきく伸びをする。
「癒知さまもはやくお友達に会いたいでしょ」
「会いたくない。てか友達おらんし。行かんでいいなら行きたくない」
癒知は早口で呪文のように言う。森田が「ええっ、もったいない」と顔をしかめた。
「小学校なんて遊び放題じゃないですか。癒知さまは降り子ですけど、学校ではひとりの小学生なんですから。ずっといい子でいる必要なんてないんですよ」
そんなことを言ったら世話役としてお母さまに怒られるで、と言いたくなる。けれど癒知は、森田のこういう、ほどよく間の抜けたところが好きだった。年が近いこともあって話しやすい。まえの世話役は堅苦しくて変に畏まっていて、あまり仲良くなれなかった。
「森田ぁ、わたしと代わってや」
「癒知さまの代わりなんていませんよ」
当たりまえじゃないですか、とおどけたように森田が眉をあげる。度のきついレンズで拡大された一重まぶたが憎々しい。癒知は半目で溜息をついた。
本棟から居住棟へ続く渡り廊下にでる。春にむかってほとばしる緑を広げた中庭は光をふんだんに浴びて、目をむけると、まぶしさで眼球の裏側がつきんとした。
視界になにかがちらついた気がして、癒知はふっと足をとめた。
渡り廊下の左側、中庭のむこうは信徒用の駐車場で、そのさきに立派な正門が黒々とした瓦屋根を広げている。その正門から、ちいさな頭がひょっこり覗いていた。小柄な少女だ。正門をささえる木柱にぴったり手を添え、じっと癒知を見つめている。
信徒ではない。近所でも見かけない顔だった。
「お友達ですか?」
癒知と目があうと、少女は口を半月形にする。相手が笑い返してくれることを疑いもしない、咲くような笑顔だった。
「ううん。知らん子」
癒知は陽ざしを直視したときのように目を細めた。実際、彼女の笑みがまぶしかった。あんなふうに笑える子は、きっと神さまなんて必要ないんだろう。
少女は癒知に睨まれたと思ったらしい。肩をすくめ、へいへいすんません、というふうに顎をしゃくると柱の裏側へ顔を引っこめた。
◇ 渡来クミ
クミはいちど引っこめた顔を、もういちど門の内側へ突きだした。
クリーム色の四角い建物が三つならんでいる。さっき、真っ赤な唇をした白い着物姿の女の子が、真んなかの市役所みたいな建物から左側へのびた渡り廊下を歩いていった。
「おいクミ、もうやめとき。帰るで」
父は自転車にまたがったままだ。クミをたしなめつつ、好奇心とうさん臭さが半々の表情で四脚門を見あげている。と、駐車場の片隅から、小豆色の作務衣を着た恰幅のよい中年男が近づいてきた。
「ご見学でしょうか?」
クミの背後にいる父にむかって笑いかける。父は「あ、いやいや」と場を取り繕うように、顔のまえで手を振って笑い返した。
「このへんに引っ越してきたばっかりなもんで、散策しとったんですわ」
「ほお、そうでしたか。このあたりは緑が多いし、坂を下ればすぐに市街地まで行けますからね。丘の上は住みにくいという人もいますが、いい場所ですよ」
「おっちゃん」
下腹のあたりで手を組んだまま微笑みを絶やさない男が、クミの声に視線を下ろす。
「さっきそこに女の子おってんけど、何歳? めっちゃきれかった」
父があわてて自転車から降り、「すんません」と苦笑して娘の腕を引く。男はクミの質問にはこたえず、恭しく一礼すると駐車場の隅へ戻っていった。その気配が消えたのを確認して、父がどっと疲れたように溜息をつく。
「急に話しかけんなって」
「だって気になったんやもん。お父さんかって、ちらちら覗こうとしてたやん」
クミは短いポニーテールにくすぐられたうなじをぽりぽり搔いた。一時間ほど自転車を漕いでいたから、肌寒さの残る四月初旬でも首筋が汗ばんでいる。
新しい町の散策は、引っ越しとセットでついてくる恒例行事だった。母はここ数年具合が悪いから、今回も父とふたりで市街地を見てきたところだ。これから通う小学校、駅、最寄りのスーパー。ひととおり散策を終え、坂をのぼって丘へ戻る道中、この施設が目に飛びこんできたのだ。
クミは目のまえの立派な四脚門をあらためて見あげた。春の陽を浴びて黒光りする瓦屋根が、猛禽類の翼のようにぬんと反りかえっている。右側手まえの太い柱に縦書きの木彫り看板が嵌めこまれていた。
『荻堂創流会 近畿支部』
さっきの少女の姿が、まだクミの眼裏に残っていた。ひっつめた髪の黒さと、しみひとつない着物の白さ、そして鮮血のような口紅の赤さ。そこまで年は離れていないように見えたが、やけに大人っぽい雰囲気の子だった。
「はい、もう行くで。置いて帰りまーす」
すでに自転車を漕ぎはじめた父の背中が、道のさきへちいさくなる。
「ちょ! あたしが誘拐されたらどうすんねん」
高い声が春の空気にわんわんと響く。クミはあわてて自転車にまたがった。
明るく、接しやすく、笑顔で。これは、転勤族として自然と身についた三種の神器。
「愛知県から来ました。渡来クミです」
三度目の転校ともなれば慣れたものだ。三十人ばかりの視線にも臆することなく、クミは教壇からぐるりと教室全体を見まわす。小学四年生にしては小柄だが、やや上がりぎみの眉毛と凜とした二重まぶたが、すこしだけクミをおおきく見せていた。
「愛知から来たのに関西弁なんは、大阪に住んでたときが長かったからです。ちなみにまえの学校では、くうちゃんって呼ばれてました。よろしくお願いします」
「はーい、渡来さんありがとう」
担任の若い女が、背後からダークブラウンのランドセルに手を添える。
小学校は四校目、引っ越しは五度目だった。ひさしぶりの関西だが、今回は大阪とはまるで規模の違う、人口八万人の小都市だ。都会での暮らしが染みついたクミは、窓際の席から見える町なみの低さに驚いた。風は排ガスではなく土のにおいがする。
休み時間に入ると、クミの席は女子たちに取りかこまれた。新しいクラスに馴染むとき、最も大切なのは緊張や不安を隠すことだ。それは相手にも伝わる。裏を返せば、にこにこしていれば誰かが話しかけてくる。そこから糸を編んで一枚の布をつくるように、すこしずつ輪を広げていく。三年生のときに誰が誰と同じクラスだったか、誰と誰が親しいのか、あるいは不仲かを、なにげないお喋りのなかで拾い取っていく。クミが意識するよりさきに、転勤族としての本能がピピッと脳内で光るような感覚だった。
一学期が始まって一週間もすると、クミはすっかり教室に馴染んでいた。
「くうちゃん家って梢ヶ丘やろ?」
「そやで。長い坂道のぼったとこ。けっこうかかる、四十分くらい」
鳴り終えたチャイムの余韻が残るなか、机の横に掛けたランドセルを外す。
背負ったランドセルの側面を擦り合わせるようにして、クミは仲のいいクラスメイト数人と連れだって教室をでた。四年生の教室がならぶA棟二階の廊下。下校ラッシュで、各教室から黒い頭と色とりどりのランドセルがわらわらと溢れでる。
二転三転する友人たちの話題に相槌を打ちながら、ふと窓へ顔をむけたときだ。
中庭をはさんだところにある校舎の足もとに、女の子が座っている。パンジーの揺れる花壇を背もたれにして、図鑑のようなものを太もものうえに広げていた。左側に赤いランドセルが行儀よく置かれている。
「あれ……」
クミは窓枠に手をかけ、つま先立ちになって二階の窓から顔をだした。
ちがうかも。わからん。いや、やっぱそう? その三つをしばらく繰り返し、とりあえずいってまえ、という勢いで「おーい」と叫ぶ。少女が手もとの本から顔をあげた。
「あ、やっぱり!」
クミは今度こそ手を振った。
「憶えてるー?」
白い着物と赤い口紅の女の子だ。いまは濃い灰色のシャツワンピースを着て、唇は自然な桃色だった。長い裾が地面に擦れないよう、ワンピースを膝の裏側にしっかり巻きこんでいる。
「え、なになに。誰?」
クラスメイトが駆け寄り、クミの両脇を埋めた。
「わーお。アーメン」
ひとりがそうつぶやくと、周りの子たちがぷっと吹きだす。
クミはどこに笑いどころがあったのかわからず、困惑ぎみに彼女たちを見やり、少女に顔を戻した。花壇のそばにしゃがんだ彼女の白い眉間に、深いしわの影ができていた。鬱陶しげな表情にも、ただ陽ざしがまぶしいだけのようにも見える。
「くうちゃん、梢ヶ丘やったら近いんちゃう? 近くに変な場所あるやろ。でっかくて古くさい、なんか異世界の市役所みたいなとこ」
「ああ、あっこかな。たぶんわかった」
「そこの子」
クラスメイトたちが妙に含みのある目配せをする。うちひとりが皮肉っぽく笑った。
「あの子、そこの神さまなんやで」
「やめなん。くうちゃん純粋やから信じてまうで」
「待って、なんていう子?」
会話の意味がわからないから、クミはそれだけ尋ねた。
「吉沢癒知。おんなじ四年やけど、あんま関わらんときや。やばいから」
「こないだも、男子何人かが、ちょっと癒知のことイジってんな。そしたら癒知、じーっと黙って聞いたあと、いきなりハサミ持ちだしてさ」
あれ誰がケガしたんやっけ、と彼女が話を振ると、ひとりが男子の名前を挙げた。別の子が、それは違うときやで、と訂正してから言った。
「とりあえず、すぐ手でるから、あいつは」
「四年のフロアにおる? 見たことないけど」
クミが訊くと、となりを歩く子が「わかごま学級やから」と短く答えた。
四年生の教室があるのはA棟。一方、わかごま学級は、中庭をはさんだB棟だ。こうした特別支援学級は、クミが通ってきたいずれの学校にもあったし、学年を問わない少人数教室というのもおなじだった。
神さま、やばい、わかごま学級。そのいずれの言葉も、クミは癒知の姿とうまく結びつけることができなかった。少し大人っぽいことを除けば、ごく普通の女の子に見える。
クラスメイトたちの話し声を聞きながら、クミは窓越しの中庭に目を戻した。レンガ造りの花壇のそばに、癒知はもういなかった。
(続きは本誌でお楽しみください。)