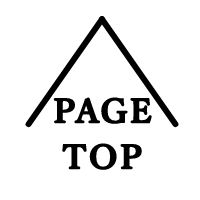序
西暦一九四五年(昭和二〇年)八月、ポツダム宣言を受諾した日本の無条件降伏により、太平洋戦争は終結した。
日本は占領下におかれ、米軍を中心とした連合軍最高司令官総司令部・略称GHQの支配をうけることとなった。
が、それをさかのぼること四カ月、日本本土より先に米軍に占領されていた沖縄は、いくつかの経緯を経て、琉球列島米国軍政府の支配下におかれていた。
米軍による沖縄統治は、日本本土の占領が終了した一九五二年よりさらに二十年長く、一九七二年までつづいた。
敗戦によって日本が支配権を失った外地、満州、朝鮮、台湾などからは多くの日本人が辛酸をなめながら日本各地に引き揚げ、それは何年もの時間を要した。
日本の西端に位置し、台湾とは百十一キロの位置にあった与那國島にも多くの日本人が引き揚げてきた。与那國島と沖縄本島には五百九キロの距離があり、台湾北端の港基隆から与那國島の久部良港までは、ポンポン船と呼ばれた当時の焼き玉エンジンの小型船でも五、六時間の航海だったが、沖縄本島までは二、三日を要したからだ。
多くの人、物品が、台湾から与那國に移動した。それを片道で終わらせるのは合理的ではないし、不経済でもある。結果、台湾、与那國間の交易が自然発生した。
もともと与那國島の住民にとって、台湾は他の琉球列島より近い存在だった。最寄りの石垣島でも百二十七キロあり、台湾より十数キロ遠い。したがって戦前は、与那國島の人が働きにでたり買い物に訪れる土地は台湾であった。
その台湾も終戦直後は混乱していた。日本による統治が終わると同時に、覇権を巡る内乱が各地で勃発したのだ。
一方、中国本土は、蔣介石率いる国民党軍と毛沢東率いる共産党軍の、国共内戦のまっ只中にあった。敗北した国民党政府が台湾に逃れる一九四九年まで、この内戦はつづいた。
当初、与那國島と台湾の交易は、物々交換が基本だった。敗戦の影響で、日本、台湾双方の通貨に信頼がおかれていなかったからだ。
ことに日本では途方もないインフレが発生していた。
台湾からは、まず食料が与那國島に運ばれた。米、ビーフン、砂糖、サッカリン、茶葉などである。これらの食料は、ただちに石垣島、宮古島、沖縄本島などにも運ばれていった。
琉球列島米軍政府が発行する軍票、通称B円が通貨として流通し始めると、交易はさらに活発化した。
沖縄本島からは、米軍の放出物資を中心に、衣類、煙草、毛布、ライター、タイヤ、ガソリン、薬莢などが与那國島に運びこまれた。
それらの物資の一部、たとえば薬莢などは香港に運ばれ、中国本土で工業利用された。
ひきかえに香港からは、米、小麦粉、電球、靴、医薬品のペニシリンなどが送られた。
医薬品は日本本土の神戸にも運ばれ、帰りの船には、瀬戸物や建材や漁具などがのせられた。
当時、与那國島では、二・四キロの薬莢と六十キロの小麦粉が等価で交換され、その価格は六十円だったが、それを沖縄本島にもっていくと、二千円の値がついたという。
与那國島には、台湾、香港、沖縄本島、日本本土からさまざまな物資が流れこみ、取引され、運びだされた。
与那國島で交易が始まるきっかけは、台湾からの引き揚げ受け入れだったが、盛んになったのには、さらに別の理由があった。
当時の琉球列島にあって、船籍を問われることなく船が入港できるのは、与那國島のみだったのだ。
米軍政府の管理が強く及んだ石垣島などには、外国船は容易に入れなかった。
とはいえ、与那國島での入港先となった久部良港は水深が浅く、大型船は座礁を避けるため沖合いに停泊せざるをえなかった。
したがって荷揚げには、サバニ、サンパンと呼ばれた小舟と荷役労働者が不可欠だった。
サンパンの多くは、米軍機の涙滴型の燃料タンクの廃品を半分に割ったものが用いられた。
荷役労働者は担ぎ屋と呼ばれ、最盛期には百五十人を数え、中には小学生くらいの子供もいた。
小学校の教諭の月給が四千円の時代に、千円以上をポケットに入れている、担ぎ屋の小学生がいたという。
こうして与那國島には、一攫千金を目論む貿易商が集まり、彼らがもちこむ品を売買する仲買人が現れ、貿易商や仲買人、担ぎ屋に住居や倉庫を貸す商売が生まれた。
当時、戸籍人口五千七百人だった与那國島に、最盛期には二万人以上の人間が滞在した。
台湾、中国本土、ベトナムといった外国や沖縄本島、日本本土に至るまで、さまざまな土地のさまざまな人間が集まっていたのだ。
与那國島久部良地区には、発電所がみっつあり、港周辺には、劇場、映画館、料亭、食堂、酒場などがたった。そこで稼ごうと、日本各地から女性もやってくる。それをあてこんで、美容院やクリーニング屋まで開業した。
久部良港の護岸通りは、サンパン屋、荷役労働者である担ぎ屋のたまり場となり、二百メートルの通りの両側には、食物や雑貨を売る露店がずらりと並んだ。
戦前、そして現在の与那國島からは想像もできないような人口密集地区と歓楽街が、わずか二十八・八二平方キロメートルの島に出現したのだ。
この頃の与那國島のことを「ケーキ時代」と沖縄の人は呼んだ。ケーキとは景気を意味する。
与那國島の繁栄は、一九四八年から五〇年まで三年間つづいた。が、一九五〇年の五月、二十日間にわたる米軍の取締をうけ、この「ケーキ時代」は終息に向かった。
与那國島をハブとした貿易は、すべてが税関を通さない密貿易だったからだ。
この物語は、与那國島が繁栄の頂点にあった時代を舞台にしている。ただし、登場する人物、組織、できごとは、すべて創作である。
1
船が近づくと、港はにわかに騒がしくなる。遠目で船の大きさをはかり、大型船なら数多くのサンパンがこぎだしていくし、小型船だとその数は少ない。
島は切りたった崖に囲まれていて、三カ所しかない浜のひとつに港はある。
この浜に港が作られたのは、島を囲むサンゴ礁が三十メートルの幅で途切れているからだ。潮がひくと、小舟でも通れる水路はそこだけに限られる。
港は島の西端にあり、北西方向にひらいた地形をしている。したがって、島の北西方向にある台湾の港基隆からくる船はかなり沖合いにあっても、まっすぐ近づいてくるのが見える。
沖縄本島や日本本土からくる船は、島の北東側からやってくる。どの方角からくるかで、船がどこからきたのかの見当がつく。
その船は大型船で、港から見て右方向からやってきた。
「本土(だまとう)だ。本土の船(だまとうぬんに)だ」
目のいい担ぎ屋の誰かが最初に叫んだ。
次々とサンパンがこぎだした。大型船ほど沖合いに投錨するため、港から時間がかかる。
サンパンには一、二名が乗り、担ぎ屋の大半は港で待機する。人が多ければ荷降ろしは楽だが、荷物を積むスペースが減る。
まるで蠅がたかるように、停泊した船をサンパンがとり囲む。接舷し、いっぱいに荷を積んだ一艘が離れると、別の一艘がそこにすべりこむ。
サンパンが港に入るのを待って、浅瀬に立ちこんだ担ぎ屋が近づき、荷を背負って陸揚げする。今度は蟻が行進しているようだ。
荷は一度護岸で降ろされ、待ちうけていた差配たちによって、品種とその数が確認される。
差配は、かたわらで待つ担ぎ屋にどこに運ぶかを指示する。
担ぎ屋は再び荷を背負い、取引の場となる倉庫や空き地へと運ぶ。六十キロの米俵なら、ひとりでふたつを担ぐ者もざらだ。
サンパンが沖合いと港を往復し、担ぎ屋が港と島の奥を往復する。蠅と蟻の作業が終わってようやく、船の乗組員と乗客が上陸した。
その頃には護岸に積み上げられた荷の大半は、港の東側、村の中へと運びこまれている。
鳴き声をたて、羽根を散らす鶏の入った籠を抱えた半ズボンの少年が、上陸したばかりの男の前で足を止めた。
少年は十二、三歳でまっ黒に日焼けし、細い体にだぶだぶのアロハシャツを着ている。
アロハシャツは本土で大流行しているが、少年の体には大きすぎた。
坊主頭に利発そうな目をしている。その目が男の身なりを観察した。
男も日によく焼けていて、黄ばんだ開襟シャツに膝の抜けたズボンをはいている。足もとは軍靴のような編上げブーツだ。左のこめかみから頰にかけ、傷跡らしき白い筋が何本も走っていた。そこだけ見ると剣吞だが、目尻のたれた人の好さそうな顔つきをしている。
「いやてい、んまからくん?」
少年は男にいった。
「え?」
男は訊き返した。背が高い。百五十センチ足らずの少年より、三十センチ以上はある。
「おじさんどこからきた? 本土(だまとう)か」
少年は訛の残る標準語で訊き直した。
男は頷いた。男の肩には軍用と思しい雑囊があった。ふくれあがり、いかにも重そうだ。
「それ、運んでやる。重いだろう」
雑囊を目で示し、少年はいった。
「よせやい。子供に荷物をもたせたら、笑われる」
男は首をふり、目尻に皺をよせた。笑うとさらに目尻がたれ、困っているような顔になる。
「島(ちま)にそんなことを気にする奴はいないよ。子供だろうが何だろうが、担ぎ屋は担ぎ屋だ。金(かに)を払ってくれるなら、何だって運ぶさ」
鶏の入った籠をおろし、少年は男の雑囊へと手をのばした。
「いいって」
男はそれをよけた。
二人が立っているのは、護岸通りの入口だった。島の先へとのびる通りの両側にはずらりと露店が並び、うまそうな匂いを漂わせている屋台もある。
「おじさん、島は初めてか」
少年はしつこくせず、籠を抱えあげ訊ねた。
男は頷いた。
「この頃は、本土からやたら人がくる。皆んな金の成る木があると思ってるんだ」
吐きだすように少年がいった。
「そうなのか?」
まるで初耳だというように男は訊ねた。フンと少年は鼻を鳴らした。
「最近は、食い詰めてやってくる奴ばっかりだ。あんたもその口か」
「いや、そこまで困っちゃいないんだがな。初めてきたのはまちがいない。いろいろ教えてくれるとありがたい。荷物をもたせはしないが、案内してくれたら礼は払う」
男はいった。
「礼? いくら?」
少年の目が鋭くなった。男は訊いた。
「いくらほしい?」
「千円」
「はあ?」
男は頓狂な声をあげた。
「じゃあ五百円」
男は無言で首をふり、護岸通りを歩きだした。少年は追いすがった。
「三百円にしとく」
「どこかのお大尽でも案内するんだな」
男はいった。
「百円でいい。きたばかりで何もわからないのだろ。俺がついてないと、どこいってもふんだくられるぞ」
男は足を止めた。
「あのな、金の価値がわかっているのか」
少年をふりむいた。
「もちろんさ。俺はこれで食ってるんだ」
少年は肩をそびやかした。
男はあきれたように少年を見つめた。
「この島じゃ子供にそんな大金を払う奴がいるのか」
少年は籠をおろし、半ズボンのポケットに手をつっこんだ。
「これがきのうの稼ぎさ」
とりだした紙幣を男に見せた。百円紙幣が五、六枚束ねられている。紙幣は日本本土のものではなく、B円と呼ばれる米軍が発行した軍票だ。
男は目を丸くした。
「金持だな」
少年はあたりを見回し、すぐに紙幣をポケットに戻した。
「俺はそんな金持じゃない」
男は首をふった。
「いくらだせるんだ?」
少年は訊ねた。男が答えようとしたとき、
「――!」
不意に大声が浴びせられた。裸の男が護岸通りを走ってきて、少年の襟首をつかんだ。担ぎ屋のひとりだった。ふりむいた少年の目が大きくみひらかれた。
担ぎ屋は軽々と少年をもちあげると、地面に投げつけた。少年の体が籠を押し潰し、羽毛が飛び散った。
少年は道に転がった。頰にべったりと白い砂がついた。鶏がけたたましい鳴き声をたてた。
担ぎ屋の男は褌一丁で、背は高くないが、横幅のある、カニのような体つきをしている。
担ぎ屋は少年を見おろし、男には意味のわからない言葉を浴びせ、拳をふりあげた。
担ぎ屋の目に男の姿は入っていない。
男が、ふりあげた担ぎ屋の拳をうしろからつかんだ。担ぎ屋は驚いたようにふりかえった。
「よしな。子供相手に」
担ぎ屋は目をみひらき、男を上から下まで見た。が、たいした相手ではないと思ったのか、男を意味不明の言葉で罵った。
「悪いな。あんたのいっていることが俺にはまるでわからん」
男は担ぎ屋の拳をつかんだまま首をふった。
「殺すっていってるんだ」
地面に手をついた少年がいった。
「そいつは困ったな。きたばかりで殺されたくない」
男は目尻を下げた。担ぎ屋は男の手をふりほどいた。男めがけ、拳をつきだす。それが空を切った。男がひょいとよけたからだ。
担ぎ屋の顔がまっ赤になった。
大声をあげ、男につかみかかろうとした。
その弾みで、男が地面においた雑囊につまずき、つんのめった。それほど雑囊は重かったのだ。
立ち上がった少年が担ぎ屋をつきとばした。
担ぎ屋は勢いよく護岸から転げ落ちると、下の浅瀬で水しぶきをあげた。
「逃げろ!」
男の腕をつかみ、少年が走りだした。男は雑囊を手にひきずられるように走った。
浅瀬に立った担ぎ屋が叫び声をあげたとき、二人は護岸通りの奥まで達していた。
「もう、大、丈夫、だろ」
膝に手をあて、少年がいったのは、護岸通りからさらに奥に入った一画だった。あたりにはバラックに毛が生えたような建物がたちならんでいる。食堂と思しい店には人が溢れ、「バー」や「料亭」と看板を掲げた間口一間ほどの店先では白粉の匂いをぷんぷんさせた女が客を呼びこんでいた。
男は驚いたようにあたりを見回した。時刻は午後四時を回ったばかりで、日は高い。
「入船」「菊松」「みなと屋」「水月」「群青」「つるや」といった看板がずらりとならんでいて、その数はざっと二、三十ある。さらに先には、「みなと劇場」とアーチ看板を掲げた、ひと回り大きな建物があった。
音楽も流れている。軽快な「青い山脈」や悲しげな「リンゴの唄」といった流行歌ばかりだ。それぞれの店がレコードを鳴らしているのだった。
「ここ、ここ」
少年は「黒猫」という名のバーを示した。
(続きは本誌でお楽しみください。)