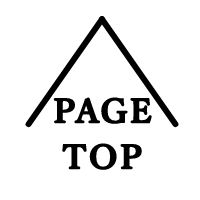プロローグ
一九九三年三月五日。
ロシア・モスクワ市。
錆びた鉄製の蓋をずらして、ユーリは地上に顔を出した。
新鮮だが凍った朝の空気がたちまちマンホールの中へと流れ込む。小さな雪片が幾つか舞い、黒い前髪に触れて水滴となった。
灰色に垂れ込める空を見上げた。降雪はどうやら止んでいる。
(でも、しばらく晴れそうにはないな……)
ほのかな暖気の中から氷点下の外気へと出ていくのは辛かったが、ユーリは唇を引き結び、ほつれた毛糸帽を目深に引き下ろした。梯子を上り切る。
このマンホールの底で暮らし始めて、そろそろ半年だ。モスクワには街中の建物の暖房を担う給湯管が張り巡らされており、これはその本管の地下部分へと下りる無数の穴の一つなのである。もちろん中は暗いし、狭いし、汚くて臭い。寝ている頭の横を虫やネズミもよく通る。でもとりあえず管の側にいれば長い長い冬のあいだ一応は暖が取れるのだから、ユーリのように住む家を持たない者にとってこれほどありがたい場所はない。今朝だって、外気温はまだマイナス十五度を下回っているだろう。
古鉄板の蓋をきちんと閉めた。市内の丸いマンホール蓋はたいてい何十キロもの重さがあるが、廃材だらけの空き地の隅に見つけたこの出入口の蓋は、十歳のユーリの力でも開け閉めが出来る、小さめの角板である。
崩れたブロックの山をさっと踏み越え、雪道へと飛び出した。角を曲がり、人の多いノーヴィ・アルバート通りのほうへと向かっていく。
今日は郊外の大きなゴミ捨て場まで行く日だ。もちろん徒歩で行ける距離ではないので、知り合いのおじさんの古い車に一緒に乗せていってもらうのだ。「おまえを連れてくと、不思議と良いものが見つかったりするからな」。実際、自分でもこれまでに掘り出し物を何度か手に入れている。それに昨日の木曜には、タバコ工場のトラックが来たはずだ。そのゴミの中にタバコの破片がけっこう混じっているかもしれない。量を集められたら、たぶん誰かに売れる。売れなくても、食べるものと交換が出来る……。
そしておじさんとの待ち合わせの時間までにも、出来れば使い走りや車の窓拭きくらいはこなして小銭を稼ぎたい。
ユーリは朝の人ごみの中を慣れた動きですいすい進んでいった。吹きつける風に鼻がかじかみ、足元で泥混じりの雪がびしゃびしゃと撥ねる。
今は、モスクワの市街が最も陰鬱で汚らしくなる時期だ。冬の終わりにはまだ遠い。そして地表に残り続ける雪がすっかり汚れてぬかるみ、撥ね散り、道も車も人の足も泥だらけにする。車道はいつも通り、でたらめに渋滞中。行き交う大人たちも、いつも通りの無表情。
バターを手に入れるための行列が朝の六時からできるような光景は、去年ほどは見かけなくなった。レストランやカフェはたいてい賑わっているし、大通りのショーウィンドウには高価な外国の製品もきらびやかに並ぶ。だが、これまでより何かが上向いてきた気配など、少なくともユーリ個人はさっぱり感じていなかった。
(どんどん分かれてってるだけだ)
強いものと、弱いものとに。
歩道の脇に座り込んで虚ろに通りを眺める男たち。コップに集めた吸い殻を売ろうとしている老女。人だまりで外貨両替の駆け引きをする男。地下鉄の階段口に並び、仔犬や仔猫を抱えて買い手を待つ中年女たち。空っぽの帽子を前に座り込む、老いた物乞い……。いつもの光景――この自分にとっては、すっかり身に馴染んだ、灰色にざわつくいつもの光景。
近道をしようと、人気のほとんどない裏通りへと曲がった、その途端である。
「――ママ!」
幼い叫び声が響いた。
前方の横路地から、何か光を含んだものが飛び出してくる。
「ママ? ……ママー!」
小さい子どもだ。女の子……、いや、男?
水色の毛糸帽から、黄金色の髪がはみ出している。光――、と思ったのはそれだったのかもしれない。
大きな青い目が、怯えたように見開かれているのがわかる。
(迷子かな?)
母親が近くにいるのかと、ユーリも周囲を見回した。そしてすぐに、通りかかった別の男も自分と同じように足を止めていることに気付いた。
黒い髥、小腹の出た中年男である。オーバーのポケットに両手を入れ、子どものほうをじっと見ている。そして、そちらへ歩き出した。
(ヤバい)
どうすべきかユーリが迷った瞬間、民警が二人、ぶらぶらと角を曲がってくるのが目の端に入った。
髥の男も、すぐに立ち止まった。よからぬ魂胆があったのが見え見えである。そのまま頭を反らし、建物の看板を確認する素振りを始めた。
民警が通り過ぎると、ユーリはすぐに声をあげた。
「ドミトリー!」
子どものほうへ小走りに近付いていく。
「こんなとこにいたのか。ママが捜してるぞ、さあ、行こう」
一緒にその場を離れながら、ちらっと振り向いてみた。髥の男は背を向けて歩き去るところだった。
「あのね」
大通り近くまで戻ると、子どもがこちらを見上げながら言った。
「ぼくの名前、ドミトリーじゃないよ。ミハイル……ミーシャっていうの」
間近で見ると、遠目に思った以上に綺麗な顔をした子である。ユーリは、アパートで母親が壁に貼っていた天使像の絵葉書のことを思い出した。
「そうか。おれはユーリだ」
応えながら、ついまじまじと相手に見入ってしまう。考えたこともなかったが、あの絵葉書と別れて以来、何かを見て「綺麗だな」と思ったのはこれが初めてかもしれない。
「とにかく、ミーシャ、あんな怪しい大人に近付いたり、ついていったりしちゃだめだぞ。どっかへ連れていかれて、ひどい目にあわされるからな」
たとえばどんな目に遭わされるのかということを、ユーリは既に知っていた。
「うん」ミハイルが素直に頷く。「ママは?」
「ママが捜しているっていうのは、うそだ。あいつから引き離すために言ったのさ」
「……そう。そうかなって、思ってた」
小さな顔が俯き、表情が見えなくなる。
「でも……、たすけてくれてありがとう、ユーリ」
「ユーシャでいいよ。おまえ、いくつ?」
「もうじき、五歳」
まだ五歳にもならないにしちゃあ、結構しっかりしている、とユーリは思った。
「ママとは、どこではぐれたんだ」
「あっちの、パイプのところ。建物とのすきまのとこに、風の当たらない、ちょうどいいくぼみがあるの」
ユーリがマンホールで頼りにしている給湯管は、地上に露出して走る部分も多い。その陰に親子は身を寄せ、何かシートを被って夜を過ごしたということらしい。よく凍え死ななかったものだ。だがミハイルがママの腕の中で目を覚まし、トイレを済ませて戻ってみたら、眠り続けていたはずのママの姿が消えていたのだという。
「おれ、少しならまだ時間あるから、一緒に捜してやるよ。行こう」
ユーリはミハイルを連れ、それから小一時間ほど周辺を歩き回った。
「このへんで、若い女の人を見ませんでしたか。長い金髪で、青い目の人です。灰色のオーバーを着てます……」
「いや、見てないね」
相手を選びつつ二十人ほどにも尋ねてみたが、答えは皆同じだった。
誰かが、寝ている彼女を病人と間違えて通報でもしたんだろうか、とユーリは考えた。
(でも今どき、賄賂もなしに診てくれる医者なんか……)
突然、小さなものが、左の掌の中にそっともぐりこんできた。
ユーリは、どきん、とした。
ミハイルの手袋をした手が、彼の手袋にきゅっと摑まっている。
「……疲れたか?」
ミハイルが黙ったまま首を横に振った。俯きながら、ユーリの歩調に遅れないよう、懸命に歩いている。
「ずいぶん歩いたもんな。少し、座って休もうぜ」
道路脇に連れて行き、雪のないブロックの上に並んで腰を下ろした。
「腹が減ったろ。今朝は、ママと何か食ったのか?」
ユーリ自身も空腹だったが、昨日の昼間は天気が悪くなかったので、洗車の仕事などをこなしてわりあい稼ぎ、ジャガイモを手に入れられた。ゆうべは空き缶でそれを熱く茹でて食べてから眠ることが出来たのだ。
ミハイルが、また首を振った。
「でも、きのうは……、パンを食べたよ。ママが、自分のショールと交換したの」
ママはそれを自分では少ししか食べず、偶然見つけた瓶に半分残っていたウォッカをちびちび飲んでいたという。
ミハイルがママと二人で路上暮らしになって三週間ほどだというが、たいてい地べたに寝て風呂にも入らずにいた生活のわりには、それほど不潔そうにも見えない。シラミもまだついていないようだ。ママが毎日髪に櫛を通し、時たま暖かくて安全な場所を見つけると、そこを追い出される前に急いで体を拭いてくれていたという。姿を消したミハイルのママは、少なくとも、なるべく息子の世話をしようとはしていたらしかった。
「ユーシャには、ママはいる……? パパは?」
「いない」つい、ぶっきらぼうに答えてしまった。
「いや、いるけど……、おれは追い出されたんだ。あいつは本当の親父じゃないし、ママももう、あいつと一緒にアル中になっちゃってるしな」
「おとなはみんな、ウォッカをのむんだね」
「意気地がねえんだよ。仕事がないとか言うけど、ただいろんなこと嫌がって逃げてるだけだ。大人のくせに」
ミハイルは、黙っている。ユーリにくっつくようにしてちんまりと座っている。
「おまえ、もしも……もしも、だけどさ」
ユーリは、言ってみた。気がひどく進まないが、どうしても訊いておかなければならない。それにそろそろゴミ捨て場行きの約束の時間になる。
「捜しても、やっぱりママがいなかったら、どうすんだ」
「ママはいるよ。きっと、どこかに用事に行ってただけだよ」
「…………」
「ぼくはママの宝ものなんだよ。いつもそう言ってるもの。ミーシャ、あなただけよって。本当にあなたしかいない、って。だから、ぼくをおいていくわけがない」
「でも、おまえのママも、酔っ払ってたんだろ」風に目を細めながら、ユーリは慎重な調子で言った。
「ママが悪いんじゃないよ。ママはウォッカをのんで、あたたかくなって、それでぼくを抱いて、夜じゅうあたためてくれたんだ」
ユーリは黙った。
(……そりゃあ……)
そういう良い親も、もしかしたら、世間にはいるのかもしれない。
だけど、どんなに良さそうな大人でも、やっぱり限界ってものはあるんじゃなかろうか。体にも。心にだって。
しばらくそのまま、混雑する通りを並んで眺めていた。
向かいの建物の陰に、少年が何人か座り込んでいるのが見える。接着剤を入れた皺くちゃのビニール袋を顔に当て、無心に吸い続けている。
二人組の少女が、信号で車の列が止まるたびに車道に出てゆく。『お金か、食べ物を頂けませんか』と書いた紙を窓越しに見せて歩いている。
いつもの光景。いつもの……
「ユーシャ」ミハイルが、ふいに言った。涙声だった。「ぼく、こわい」
はっとして見下ろすと、毛糸帽の下で白い頰がふるえている。
黄金色の――綺麗な――前髪が、風に揺れてひかっている。
「泣くな。おまえは、だいじょうぶだから」
何がどう大丈夫なのかまるでわからないまま、気付くとユーリは口にしていた。
(ばか。だいじょうぶなわけ、ないじゃないか……)
こんなチビ、ほんとに明日にでも死んじまうぞ。
ユーリは、だが、顔を前に向けて繰り返した。
「だいじょうぶだ」
「ユーシャ……、ママは、どこ?」
「わからない。だけど……、だけど、これからは、おれがいるよ」
第一章
二〇二三年七月十一日。
東京都・中央区。
デジタル・タイマーが残り時間を刻み続けている。交代の目安まで、あと二分。
早瀬真音は、今回のパートナーである後輩の様子を隣から静かに窺っていた。
ヘッドホンを着け、その倉田杏里は集中した横顔でマイクに向かっている。
「……ロシア水域での流し網漁業の操業は、ご存じの通り、二〇一六年一月より、禁止されていますが……」
通訳用ブースの中は、いくらか冷房が効きすぎている。カウンターデスクに椅子が二つ並ぶだけの小さなスペース。ガラスの向こうには漁業シンポジウムの参加者で七割がた埋まった会議場が広がり、壇上ではロシアから来日した水産会社の社長がスクリーンを背に喋っている。声質は明瞭だが、ジョージア訛りが強い。そして早口だ。訳を続ける杏里が、キーワードを取りこぼさぬようずっと必死であるのが伝わる。
(あと少しよ、杏里)
こうした「同時通訳」の場合、発言者の台詞というのは、実は半分から七割程度しか聴衆に通訳されない。歴戦のベテラン通訳者によってもそうなのだ。それだけに、文脈を考慮しつつ、どの情報を瞬時にすくい取り、どの情報を切り捨てていくかという点にも、通訳者の力量は如実に表れる。
同じエージェント会社に登録している杏里は、真音にとって親しい後輩と言っていい相手だった。まだ二十六歳、この規模のイベントでの「同通」は今日が初めてなのだ。しかも昨今の国際情勢下ではロシア語通訳の仕事は激減している。杏里とすれば、これは貴重な現場経験のチャンスとも言えるのである。
もういつ交代してもいいとわからせるため、真音は二人の間にあるマイクの切り替えボタンにそっと手を被せた。極度の集中力と頭脳労働を要する同通の仕事は消耗が激しい。長時間の仕事の場合は複数の通訳者でチームを組み、十分から二十分程度で交代しながら回していくのもそのためだ。
真音自身は、今年三十歳になった。だが年齢だけで言うなら、三十代前半でもまだ新人と見られておかしくないのが通訳者業界である。背丈こそ一六八センチあるが、黒髪ショート・ボブの童顔、すっぴんでいるといまだに学生に間違えられたりする真音が、エージェント会社から既にロシア語と英語で最高ランクの「S」認定を受けていると知り、驚くクライアントも珍しくない。
壇上の男の言葉が、ふと途切れた。眼鏡をずらし、手元のノートをめくっている。そして、「ああ、これだ」というふうに、開いたページを手でさすった。
「ここで、私のルーツであるジョージアの著名な詩人、イアシュヴィリによる詩の一節をご紹介しましょう」
杏里が小さく息を吞むのがわかった。
「……時に限りはない。私たちを壊すものは何もないのだ……」
(読むな! 話して!)
真音は胸中で、壇上に向かい呪詛を投げつけた。
「同時」に「通訳」するというのは、「話し言葉」であるからこそ可能なことなのだ。労力と時間をかけ無駄なく練り上げられている文芸作品を、その場ですらすらと朗読され、それを瞬時に完璧な他国語に変換してゆくことなど、どんな通訳者にも無理な話だ。
杏里が既に何秒かためらってしまっている。
通訳が困難な場合、それを発言者にランプの点滅で知らせる装置を備えた会場もあるが、ここにはそれはない。発言者側に原因があって通訳不能の場合、通訳者がその旨をアナウンスすることもなくはないのだが――
(いっちゃえ)
真音は「替わる」と杏里に合図し、素早く切り替えボタンを押した。
「……仕事、戦争、嵐……、その中で、私たちは、人生の恵みを説く……」
(続きは本誌でお楽しみください。)