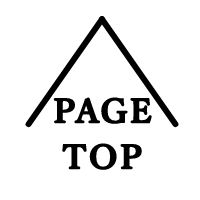燕が二羽、高瀬川の川面を互いに前になり、後になりながら、飛んで行く。まだ巣立ちをして日が浅い若鳥なのか、その飛び方は敏捷なわりにどこかぎこちない。川岸から垂れ下がる柳の枝にぶつかりかけ、あわてたようにこちらの目の前に方向を変えた二羽に、「うわっ、危ないやないか」と俊太は悲鳴を上げて立ちすくんだ。
もっともその時にはすでに燕たちは、空の高みはるかへと舞い上がっている。地上のことなぞまったく顧みぬ自在な飛び方に、俊太は胸元の笊を抱え直して、ふうと息をついた。
麻袋に入った米や油紙に包まれた味噌、それに先ほど錦小路で買い求めてきたばかりの塩鮭が詰め込まれた笊を抱えた俊太の姿は、まだ十四歳という年齢とあいまって、木屋町筋に立ち並ぶ料理屋の奉公人としか見えない。荷車を曳いて通りを南からやってきた屈強な男が、柳の根方に立ちすくんだ俊太に、邪魔だとばかり舌打ちを浴びせかけた。
俊太はその背中をきっと睨みつけたものの、すぐに笊を抱く手に力を込め、足取り重く歩き出した。
石組が施された高瀬川の向こう岸に目をやれば、白い土塀が初夏の陽射しを眩く照り返している。あれは加賀藩邸、あれは対馬藩屋敷。京の市中に諸藩の藩邸は数え切れぬほど点在しているが、奉公先に向かう足取りが重ければ重いほど、長く連なる土塀の明るさが忌々しい。笊の中身をすべて高瀬川にぶちまけてやりたい衝動に俊太が駆られた時、
「どうした。そんなどごでぼんやりして」
と、背後から軽く肩を叩かれた。
振り仰げば、柱がそのまま人になったかと思われるほど背の高い三十男が、小腰を屈めて俊太の顔をのぞき込んでいる。別に、と顔を背けた俊太の手から笊を取り上げ、「おお、嬉しいなあ。塩吹きの鮭でねえが」と強い北の抑揚とともに、総髪の顔をほころばせた。背中に負われた薬籠が、身動きするたびかたかたと鳴った。
「これは牛渚どのも、さぞ喜ぶべな。京の食い物は水っぽいだの、塩気が足りんだのと、いづも文句ばかり仰ってるからな。やっぱ鮭は、塩が粉のごとくまとわりついでるものでなければいかん。わざわざ買い求めてくっちゃのか」
「その分の銭はちゃんともらってますから。わし、自分の仕事をしただけどす」
そんなことより、と俊太はいらいらと男を見上げた。
「南部さま、またお国訛りが顔を出してはりまっせ。外やわしの前では、慎まはるんと違いましたんかいな」
「おっと、いかん。そうだった」
あわてて自分の口を片手で押さえた南部に、俊太は大きな溜息をついた。このところの苛立ちの元凶の一つであるこの男ののんびり具合が、どうにも腹立たしくてならなかった。
五年前に流行病で相次いで亡くなった俊太の父母はともに、三条御幸町の八幡屋という旅籠で働いていた。北は遠い松前から、南は薩摩。各地からの旅人を見てきた両親は、「北のお人は頑固、南のお人は人懐っこくて気が優しい」と事あるごとに俊太や妹のお君に話してくれたものだ。
この南部精一という男は、現在、俊太が下男奉公している絵師・塩田牛渚と同じ、東北・会津の出。ただどうもこの間の抜け具合を見る限り、両親の見聞もすべての人に通じるわけではなさそうだ。
「……まったく、これやから田舎のお人は迂闊で困ったもんや」
「すべて聞こえているぞ、俊太。悪かったな、田舎者で」
言葉面とは裏腹にからりと笑う南部は、大坂や長崎で長く医術を学んでいたそうで、現在は釜座竹屋町の小石という医師のもとで修業をしている。三十二歳という年齢は、俊太の目には十分な大人と映る上、小石家では時に師の代診を命じられもしているという。ならばさっさと国許である会津に戻ればよかろうに、「なんの、なんの。これっぱかの学びでは一人前と言えん」と、居候先の牛渚の家から、毎日、生真面目に小石家に通う腰の低い男だった。
「今日の飯はその塩鮭か。骨もちゃんと一緒に買ってきたか。もしそうなら、それで汁を拵えても旨かろうな」
「うるそおっせ、南部さま。わしは牛渚さまに下男として雇われていますけど、南部さまのお世話までは請け負ってしまへん。塩鮭が食いたいんやったら、自分で買うてきておくれやす」
「つれないごどを言うな。おぬしら京の人間は、どごの店で何が売られているかよくわかっておろうが、こっちは都に出てきてまだ半年足らずなのだ。買い物はとかく苦手でならん」
しかたないだろうとあっさり言い放つ口調に、俊太はむっと頰をふくらませた。
「買い物に苦労しているんは、わしかて同様どす。なにせ去年、南部さまたちのお殿さまが長州相手にしかけはった戦のせいで、洛中はどこも綺麗にまる焼け。わしかて、知ってる店がよそに移ってしもうたり、店じまいをして田舎に引っ込んだりとえらい難儀をしてるんどす。ご自分とこのお殿さまが何をしはったか、ちょっとは考えてくんなはれ」
胸の中のものをひと息に吐き出した途端、南部の太い眉の両端がしゅんと下がった。その表情に言い過ぎたと思いはしたが、なにせ昨年の大火への憤懣は俊太の中でまだ収まることなく荒れ狂っている。
南部はまだ修業中の医者だ。去年の火事と、その原因となった蛤御門の変に直接かかわっていないことぐらい、よく分かっている。だからこそそのしお垂れた顔が腹立たしく、俊太は彼の手から強引に笊を奪い取った。
そのまま振り返りもせず川辺の道を進み、四条大橋が見えてくると同時に、料理屋と料理屋の間の路地を折れる。人同士がすれ違うことも難しいほどの細道の突き当りの二階家に駆け込むと、「塩田さまァ。戻りましたで」と苛立ちに任せて、声を張り上げた。
「お申し付けの塩鮭、ちゃんと買うてきましたさかいな。南部さまがわしにも食わせろと言うてはりますけど、差し上げてもよろしおすか」
この家の主である塩田牛渚は、南部より五歳年上。藩士の身分のまま勉学中の南部とは違い、とうの昔に会津藩の家禄を離れて久しいこともあり、同居人のように普段から東北訛りを露わにすることはない。
ただそれでも、会津人は会津人。これまた、京の都を焦土に変え、妹のお君に大やけどを負わせた憎たらしい侍たちの一味であることに変わりはなかった。
(だいたい、八幡屋の旦那さまも旦那さまや。わしに奉公先を紹介する前に、なんでこのお絵師が会津人やと気づいてくださらへんかったんや)
俊太たちの父母の奉公先だった八幡屋の主夫妻は、二人の両親の死後、まだ幼い兄妹を住み込みの下働きとして雇ってくれた。だが昨年の七月、ご禁裏の蛤御門で起こった戦は、戦闘そのものは半日で終わったものの、三日にわたって洛中を焼き尽くす大火を呼んだ。
北は御所周辺から南は塩小路村、東は寺町から西は東堀川まで、三万軒に近い家々が灰燼と帰した大火の中で、八幡屋もまた周辺の宿屋ともどもまる焼けとなり、六歳だったお君は左足にひどい怪我と火傷を負った。幸い命だけは助かったものの、いまだ日がな一日、横になったまま過ごしている。
齢六十を越えていた八幡屋の主夫妻は店の再建を諦め、郷里である篠山に引き揚げると決めた。その際、俊太にせめて新しい働き口をと奔走した結果見つかったのが、絵師・塩田牛渚宅での下男奉公だった。
――西国じゅうを数年がかりで旅して、色んな絵を学ばはったお人やそうでな。やまと絵に唐絵、花鳥画に水墨となんでもございの腕の持ち主でいらっしゃるんやと。ちょっと酒が好きすぎるのが難と言えば難やとうかがったけど、ご禁裏に召され、帝の前で絵を描かはったこともあるらしいで。
しっかり勤めるんやで、と目を赤くした八幡屋の主に、そんなお人のもとでの奉公など勤まるのだろうかと俊太は不安になった。だがいざ働きはじめれば、牛渚は酒さえあれば満足な男らしく、俊太が慣れぬ手つきで拵える夕餉を前にしても、ほとんどは「ご苦労だな」とひと言ねぎらうだけだった。もともと口数が少ないわけではないのか、絵の仕事がひと段落すれば、俊太を引き留めて、世間話の相手をさせることもある。だが牛渚は絵師としてはなかなかの売れっ子らしく、そんな折は、半月に一度あれば多い方だった。
それだけに通いの下男奉公が始まって三月後、いきなり長崎から転がり込んできた南部精一と牛渚が強い北国訛りで話し合っているのを目にした時、俊太は腰が抜けるほど仰天した。それがこの数年、京都のそこここで聞くようになった会津藩士たちの言葉と同じと気づき、つまりこの二人の生まれはと思い至った時には、会津人のもとでなぞ働けるかと、牛渚のもとを飛び出そうとも考えた。
(だけど――)
お君を案じた八幡屋の主がよくよく頼んでくれたと見え、俊太が牛渚の家で働くのは、正午から日暮れまでのほんの半日。奉公は必ず通いで、何があろうとも泊まりを命じることはないと、最初から言われていた。
なにせ、俊太はまだ十四歳。手に職もなく、親もおらず、怪我の妹まで抱えた身の上で、これほどありがたい奉公口は滅多にない。
俊太が物心ついた頃から、京の都ではなにかと物騒な事件が相次いでいた。やれ、江戸の幕府を倒すべきだの、帝を国の主となし奉るべきだのと騒ぐ不逞の輩が都を行き交い、商家への押し込みや名のある侍や学者が往来で殺される騒ぎも珍しくなかった。会津の侍たちはそんな京都の治安を守るべく、遠い遠い東北からはるばるやってきた護国の武士であることぐらい、俊太とて理解している。そして昨年七月の火事は、そんな彼らを西国の長州藩が排除しようとしたところから始まっているということも。
ややこしい大人たちの争いはよく理解できなくとも、帝が厚い信頼を寄せているという会津藩および藩主・松平中将(容保)と、朝廷はおろか幕府の言うことにも従わぬ長州のどちらが天下の悪人か、分からぬ俊太ではない。ただ長州の侍たちは、昨年七月以来、潮が引くように都から去り、木屋町に面していた藩邸も大火の中で焼け落ちた。一方で京都守護職・会津藩の侍たちは、京都所司代麾下の者たちともども、いまだ洛中を忙しく行き交い、その姿を目にしない日はない。また京都守護職配下という京都見廻組や新撰組といった侍たちの一党も、同様だ。なまじ洛中の大半が焦土と化した直後だけに、肩をそびやかし、四方を睥睨しながらのし歩く武士の姿は、否応なしに目立つ。
いつの間に京都は、あんな田舎侍たちが闊歩する町になってしまったのだろうと思えば思うほど、父と母が息災だったかつてがひどく遠い昔に感じられる。どこにもぶつけようのない腹立ちが、奉公先の会津人二人への苛立ちにすり替わり、またそんな彼らのもとで働くしかない自分自身への怒りとも化して、年の割に小さな身体の中で荒れ狂っていた。
「お返事があらしまへんけど、ほな、晩飯は二人分拵えてよろしおすな。後からとやかく言わはっても、困りまっせ」
土間の流し台に笊を置きながら更に声を張り上げても、牛渚が画室として使っている階段下の奥の間の襖は、固く締め切られたままだった。
牛渚は仕事に対しては癇性で、絵を描いている時の雑音を何より嫌う。このため俊太は勤めの間はなるべく物音を立てぬように立ち働いていたが、今日ばかりはそんな遠慮が馬鹿馬鹿しく感じられた。
怒りたければ怒ればいい。こっちにだって言い分はあるのだと思いながら、空の手桶を引っ摑む。裏庭の井戸で水を汲もうと身を翻した時、からりと襖が開く音がした。やれやれ、やっぱり雷が落ちるらしいと内心舌打ちしながら頭を転じ、俊太はおやと目を見開いた。
牛渚は頭の鉢が大きく、反対に手足はちまちまと短い小男である。だがいま襖を引き開けたのは、身の丈は六尺(約一メートル八十センチ)はあろうかという大柄な男だった。
まるで旅先から戻ったばかりのようにぶっ裂き羽織をまとい、両手に手甲までつけている。形のいい頭は毛一本残さず剃り上げられ、油を塗ったかのようにてらてらと光っていた。
「せ、先生。松本先生ではございませんか」
南部がぎょっと目を見開いて、上がり框に駆け寄った。おお、と金壺まなこを見開いた禿頭の男の背後から、牛渚が「やっと戻ったか」と畳に片手をついて顔をのぞかせた。
「おい、南部。ここはわたしの家なのだぞ。客人が来るなら来ると、なぜ早めに言ってくれんのだ。こちらにもこちらの都合というものがあるのだぞ」
「しばらく世話になりたい旨、江戸から文を出しておいたのだがな。どうやら手違いがあったようだ。いきなり押しかける形になってしまい、すまん」
松本と呼ばれた男は、南部より二つ三つ年上だろうか。その身動きは鷹揚で、人にかしずかれることに慣れた気配がある。
下駄をあわてて脱ぎ捨てた南部が、上がり框の端に膝を折る。背の薬籠を下ろし、「大変ご無沙汰申し上げております」と、松本に向かって両手をついた。
「江戸にお帰りになられた後、奥医師にお進みになられたと聞きました。ご栄達は陰ながら存じ上げておりましたが、お祝いの文一つお送りしなかった非礼、何卒お許しください」
「いやいや。わたしの方こそ、おぬしが大坂や長崎で勉学を続けているとは小耳にはさんでいたのだ。だが多忙にまぎれて、すっかり無沙汰をしてしまった。しかもこのたびおぬしが京にいる旨、会津藩より仄聞し、かつての師弟の縁に甘え、しばらく厄介になろうと独り決めをして来たのだが――」
松本はもの言いたげに、瞼の厚い目で家内を見回した。
一階に牛渚の自室と画室、二階に物置と現在南部が暮らす六畳間が一間ずつというこの家は、牛渚を贔屓とする六波羅の米屋・成田屋の隠居の持ち物である。どうもかつては妾を住まわせていたらしく、欄間の細工や通り庭の敷石など何もかもがこじゃれているのはいいが、三十男の二人暮らしにはいささか窮屈な、瀟洒すぎる一軒家だった。
どうやら松本という男は、この家に逗留すべく江戸からやってきたらしい。これでただの友人であれば、南部と同室での寝起きも悪くはない。しかし先ほど来のやりとりから推すに、松本は彼とは師弟の関係にあるようだ。
(続きは本誌でお楽しみください。)