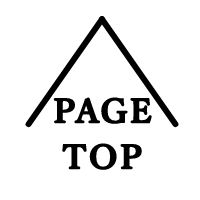ホールの時計は、前に見た時から二分しか進んでいなかった。あまりのやることのなさに、関は目をぎゅっとつむって開いたり、首を回したり、眼鏡を外して埃や皮脂汚れをチェックしたり、自分と同じように学生課の窓口の行列に並んでいる98年度入学の新入生たちを見回してみたりした後、また時計を確認したのだが、やはり一分しか進んでいなかった。大学に入ったらいかにもいそうだと思っていた、髪や服装に手間暇をかけていて何にでも自信がありそうな見た目の学生がどうしても目に留まるけれども、それほどでもないタイプもたくさんいて、絶対に自分に居場所がないというわけでもないかもしれない、と関は思った。
緊張が少しおさまると、音楽を聴こうという気分になり、リュックサックのストラップの左側から腕を抜いて前側に持っていき、ファスナーを開けてポータブルCDプレイヤーのイヤホンを探した。大学に来る時に急いでバスを降りたので、何にも巻き付けない状態でリュックの中にしまい込んでしまい、イヤホンのコードはものすごく絡まった状態で出てきた。けれどそれを解きほぐす作業ですらも、行列が一向に進まない今ではちょっとした気晴らしのように思える。
先ほど初めて乗った八時台の京都市内のバスは、地元のバスより混んでいて、ちゃんと料金を払えるのだろうかとはらはらした。バスに乗っていた三分の一ほどの若者が、いっせいに自分と同じ停留所で降りたことにもどうも緊張した。
イヤホンを耳に入れ、つながったリモコンを操作する。リモコンには電池の残りが少ないという表示が出ていたけれども、とりあえず一曲聴いてから電池を入れ替えることにして、関はCDの一曲目を再生する。シューベルトの軽快なピアノ三重奏第一番が流れる。D898だ。第一楽章がとても好きだった。中学生の頃からオアシスやグリーン・デイのような英語圏のバンドばかり聴いてきたので、自分が十八歳になってシューベルトを聴いているというのは意外だったけれども、深夜にテレビを観ていて番組の間の繫ぎのような環境映像で流れていたピアノ曲が気になったので聴き始めることにした。シューベルトのいくつかの曲は、エリオット・スミスを聴いている時と同じ気分になると、誰にも言わないが思っていた。彼ほど関が好きな曲を書く人が二人とおらず、自分がこれまでの曲を聴き過ぎて使い果たしてしまうのではないかということを、関はときどき心細く思っていたのだが、シューベルトが千曲も書いていると知って、自分の倉庫に新しい備蓄食料が何トンも補充されたような気がした。ちなみに、関がテレビを観ていて初めて認識したシューベルトの曲は、ピアノ即興曲D899の3番だった。
音楽を聴き始めても一向に行列は進まなかったが、関もそれをかまわなくなっていた。現代の音楽ばかり聴いていると、シューベルトの曲が十五分もあるということに最初は驚くのだが、聴いているうちに飛ぶように時間が過ぎていく。シューベルトに限らず、関は自分の死ぬまでの時間が、音楽の再生と次の曲に移るまでの小さな停止だけで過ぎていかないものかと考えることがあった。関は小説を書いていたし、厳密に考えると、うまいものを食べたいとかたくさん寝たいとかいくつかの欲求はあったかもしれないが、もし音楽だけを聴いて生きていけるのならそれでよかったし、そうやって生きられるのなら他には何もいらないと思うことがよくあった。
曲を再生してからしばらくすると、関の後ろに誰かがやってきたようだった。軽く振り返って確認すると、かなり背の高い女子の学生がそこにいた。一七三センチの関が少し顔を上げて見上げるぐらいの身長なので、おそらく一八〇センチを超える長身だと思われる上に、姿勢の良いその女子には、人が行列に並んでいる時の油断がほとんどなかった。額にまでかかる黒くて太いヘアバンドで髪を後ろに流していて、前髪で印象を左右されない表情は硬かったけれども、目つきにだけは何かをおもしろがっているような明るい親しみやすさがあった。
彼女の佇まいの珍しさに、関は山や塔を眺めていたいのと同じような気分になったのだが、興味深いというだけの理由で人を見つめすぎるのは良くないということぐらいは知っていたので、四秒ほど見つめるだけですませてまた前を向いた。
曲が終わると、関は次の曲に入る前に急いでプレイヤーを停止して、電池を入れ替えることにする。替えの電池を入れているプレイヤーに付属していた巾着が、たまに紐の締まりが緩くて電池がリュックの中の他の荷物に紛れていて探すのに手間取ることがあり、交換の時はいつも緊張するのだが、今日はちゃんとあるべきところに入っていた。
何も聴いていない時にイヤホンが耳に入っているのがいやなので両方外して電池を入れ替えていると、それと同じの持ってるよ、家に置いてきたけど、という声が頭の上から聞こえた。穏やかな女性の声だった。
振り向くと、後ろに並んでいる背の高い女子が関の手元のCDプレイヤーを見ていた。
「しかも同じ色の。やっぱり黄色だよねあの中では」
「青はなんか工事現場っぽい青やったし、ピンクは柄やないしね」
同じ売場に置いてあった同機種の他の色の製品を思い出しながら、関は言う。自分の生活圏では今まで見たことがない彼女の佇まいを考えると、標準語を話すことはまったく意外ではなかった。
「列がまったく進まないから、聴くもの持ってるのがうらやましくて。話しかけてごめんね」
「ええよ」
そう言っているうちに、関の前のスペースがおよそ二人分突然空いたので、急いで詰める。窓口から男女が離れていくのが見えたので、たぶん付き合ってる者同士なんだろうと関は思う。後ろの背の高い学生の後ろにも数人増えていて、さらに列が長くなっている。
「何聴いてるの?」
「普段あんまり聴かんけれども、さっきのはクラシック」
「そっか」
関のちょっとした警戒を感じたのか、彼女は深追いはせずいったん納得したようにうなずく。音楽に関しては、固有名詞を出して説明してもわからない相手の方が多かったりするので、詳しくは言わないようにしている。普段あんまり聴かないというのも、クラシック音楽を聴いているというマイナーなイメージをごまかすためのうそだった。
「電池入れ替える前に聴いてた曲は十五分あったんやけど」関は話をごまかしてしまったことを取り繕うように、べつの情報を出しながら続ける。「それでも列進んでなくて逆にすごいと思うわ」
「みんな慣れないのかもね。高校の時は勝手に学校が時間割組んでくれたし」
めちゃくちゃ面倒だった、受講希望者が多い場合もあるからその時間はだめかもしれないんで予備の希望を考えておけとかね、と彼女は自分で作成した時間割の登録用紙を見せてくる。関とは違って心理学科の学生のようで(関は社会学科だった)、平日はほとんどの日に一限目から三限目か四限目まで授業を入れていて、すぐに単位が取れてしまいそうな様子だった。関は、分厚くてページごとに断片的な内容が羅列されているシラバスを読むのが苦痛で、一般教養はほとんど授業の名称だけで時間割を組んでしまったのだが、彼女は関が考えもしなかったような講義を時間割に加えていて、ちゃんとした人なんだな、すごいな、という平たい感想を持った。
「自分はなんか、あんまり内容読まんと決めたから、しょうもない感じやわ」
関がリュックから用紙を出していると、また一人進んだので詰める。彼女は関の用紙を覗き込んで、半ば笑っているような声で指摘する。
「変なこと言ってたら申し訳ないけど、三国志の武将の名前みたいだね」
関猛、という自分の名前をまじまじと見る。せきたけし。せきもう。かんもう。祖父がつけたらしい。何を思ってかは知らないが、関は猛々しさとはほど遠い大学一年になり、けれども祖父は気にしていないようだった。
「関羽の息子っぽいか。でも関平がおるよな」
「じゃあ関平の息子とか」
「関羽の孫か」
「いいじゃないおじいさんが関羽。うらやましい」
背の高い彼女の、おもしろがっているような目がますます明るく輝くように思えてくる。内心の生き生きした心持ちが、身体に満遍なく反映されているように思える彼女の様子を見ていると、関はもっと彼女をおもしろがらせたいと思っている自分に気が付く。
また一人分列が進む。窓口の人が有能な人に代わったのか、それともこれまで列の前の方にいた学生が特段難しいことをやっていたのか、音楽を聴いていた時とその前からは考えられないほど列がちゃんと進み始める。
用紙もう一回見せてくれる? と関が言うと、彼女は関に希望する時間割を記入した用紙を渡してくれる。共通している授業は何もなかった。彼女も少し変わった名前だった。
「こっちの名前も変わってるでしょ。名字に〈地〉って入ってるからかもしれないけど、なんか地名みたい」
疋地泉。それが彼女の名前だった。確かに、姓と名の間に空白を入れないと、人名だとはわかりにくいなと関は思った。名字がひきち、名前がいずみ、と彼女は言って、関が戻した用紙をつまんで受け取り、クリアファイルにしまった。
今度は二人分ほど列が突然進み、関はつんのめりそうになりながら詰めた。いきなり進み始めたね、と疋地さんも前の様子を覗き込む。気が付いたら、窓口に関がたどり着くまであと二人というところまで来ていた。関はにわかに緊張してきて、もう疋地さんとしゃべるどころではないという感じだったのだが、疋地さんにもそれが伝わったのか、それからは何も話しかけてこなかった。
関の前の男子学生が、用紙と一緒に学生証を窓口に提出しているのを肩越しに見かけて、関はえっと声をあげた。え、学生証持ってきたっけ? ていうか入学式の時に受け取ってから学生証自体一度も手に取ってないし見かけてない。このリュックは入学式にも持って行って、シラバスと時間割の登録用紙を取り出した以外は中身を出し入れしてないから、学生証はあるとしたらこの中にあるはずなのだが、配付されて以来手にしたことのないものの所在に確証などなかった。
おろおろしているうちに自分の番が回ってきて、「登録用紙と学生証を呈示してください」と窓口の女性に言われた関は、時間割の登録用紙だけをその場に置き、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、と言いながらリュックの中を探し始める。学生証ってどんな封筒に入ってたっけ、ていうか封筒自体見当たらない、どうしたんだ、底の方で折れ曲がってるのか、いやない、どうしたっけ、記憶にないけど、シラバスを出した時にもしかして一緒に出したのか?
すみません、すみません、と言いながら関は息が苦しくなってくるのを感じる。手足が冷たくなって、頭の中の平衡感覚が切れるようにぼうっとする。視界の上と下が斜めにずれていく。
「リュックの中に顔を突っ込んでみたら」
後ろから声が聞こえた。疋地さんだった。言われた通り、リュックサックを開いて中に顔を入れて周りがいったん暗くなると、さっきまでよりは落ち着いてものが考えられるのを感じた。
学生証はよく使いそうだから、もらった日に財布に移したことを思い出した。自分がそんな気が利く人間だなんて意外だ。関はリュックから顔を出し、呆気にとられている窓口の女性に、思い出しました、と告げて、財布から学生証を出した。財布は高校二年の時から使っているやつで、ちょっとすり切れてきている。そろそろ買い換えないと、でも金がない、ていうかこれ使いやすいからまったく同じのがほしいんだけどどこにも売ってない、と考えたことまで思い出した。
窓口の女性が、正式な時間割は明日と明後日のオリエンテーションが終わった次の日に出ますので、またこの窓口に取りに来てください、と言う。なんて非効率的なんだ、という文句は、自分も学生証が見つからなくてリュックサックに顔を突っ込んだ人間なので深く考えずにおいた。
関は窓口の女性に、すみません、お願いします、と頭を下げ、その場を離れながら、申し訳ない、とこれまで何度も学校で言ってきたように、疋地さんに自分の不自由を詫びた。疋地さんは、関の名前を三国志に出てくる武将みたいだと言った時とまったく同じ表情と眼差しで、え、あやまることなんて何もないよ、と言った。
下宿への帰りのバスに揺られながら、自分が彼女にできそうなことはおもしろいことを言うだけだけれども、学科も違っているし授業も何一つ重なっていないので、それがもうできそうにないことを関は残念だと思った。
(続きは本誌でお楽しみください。)