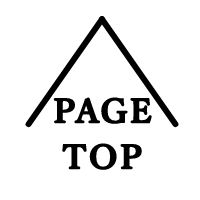のらぼう菜の花
母親について唯一の記憶らしい記憶といえば、十歳のときにサイドカーに乗せてもらったことくらいだ。
そのころの僕は祖父母の家で暮らしていた。
東京と言うよりはもう山梨と言ったほうがいっそ潔い奥多摩のさらに奥深くに、祖父母の田舎家はあった。それは祖父の生家で、大学を退官した祖父が青山のマンションを処分して祖母と戻ってくるまで長らく空き家だったのだが、高い屋根を支える太い梁は少しも傷んでおらず、色褪せた大黒柱には祖父の子供のころの成長の記録が刻まれていた。
祖父母は自分たちだけでその家をまた人が住めるようにした。軒下に巨大な巣をつくっていたスズメバチを退治し、燻煙タイプの殺虫剤を焚いてムカデやヤスデを追い出した。壁を何枚かぶち抜き、床を張り替え、書架をしつらえ、北欧製の薪ストーブを運びこみ、庭先に大きな栗の樹を二本植えた。それだけのことを、ふたりだけでやってのけた。そして生活のためというより、趣味でのらぼう菜やトウモロコシをつくりはじめた。胡麻と和えたらおいしいのらぼう菜は菜の花の仲間で、春になると菜の花みたいな黄色い花をたくさんつける。でも、そうなったらおしまいで、葉っぱが硬くなって売り物にならなくなった。
小学校の校門の向かいにその古臭いサイドカーを見つけたのは、六月も終わりかけの木曜日の朝だった。
都心のほうは連日の猛暑に襲われていたけど、朝靄たなびく雲取山から吹き下ろす風のおかげで、僕たちの町はいつものようにひんやりとした朝を迎えていた。空は朝顔みたいに青く澄み渡り、生まれたての蟬がぎごちなく鳴いていた。
小舟のような側車がくっついた妙ちくりんなオートバイに、その女の人はもたれかかっていた。
髪の長さが肩くらいまであって、ブルージーンズにゴム長みたいな黒いブーツを履いていた。黒いTシャツを着たその体つきはほっそりしていて、マンガみたいなごっついゴーグルを首にかけていた。別段、綺麗だともブサイクだとも思わなかった。ただ、僕を見つめるその吊り上がった細い目が少し怖かった。
サイドカーというものを見たのは、そのときがはじめてだった。オートバイから車に進化しようとしている途上のような、なんともネアンデルタール人的な名付けようのない乗り物だった。
出し抜けに名前を呼ばれたとき、一瞬それが自分のことだとわからなかった。顔をふり向けると、その女の人がにっこり笑って馴れ馴れしく手招きをしていた。僕は猫みたいに警戒し、もしかして僕のほかにも「ペイジ」なんてへんな名前の子がいやしないかと、あたりをきょろきょろと見回してしまった。
すると彼女が笑顔のまま道路を渡ってきたので、僕は学校のなかへ逃げこむべきか真剣に迷った。僕はその場に踏みとどまった。登校中の児童たちと、まぶしい空にもくもく湧き上がった入道雲が僕を大胆にしていた。まったく人生というやつは、いつだって取り返しがつかなくなってからそのことに気づくようにできている。
彼女はしばらくじっと僕を見下ろしていた。驚くべき大自然の驚異を目の当たりにしているかのように、たとえば海面に躍り上がったクジラとか火山の噴火でも見ているかのように、その目はきらきらと輝いていた。なにか言いかけては、またあきらめて口を閉じた。
彼女はあきらかにひどく興奮していた。目が潤み、鼻の穴がひくひくと膨らみ、唇が震え、くしゃみが出そうで出ないときみたいな顔をしていた。同時に、なにかにおびえてもいるみたいだった。
いったい人はこんな微妙な表情をどこにしまっているのだろう? 生き別れの息子とでも再会しなければとてもこんな顔にはならないはずだが、結論から言えば、実際にそのとおりだった。こちらの不信の眼差しをものともせず、彼女は声を上ずらせながらこう切り出した。
「ペイジ、憶えてないだろうけど、あんたのママだよ」
僕は後退りした。
彼女は笑っているような、それでいて泣いているような顔で両手を広げた。さあ、この胸に飛びこんでおいで、と言わんばかりに。
母親を知らずに育った十歳の男の子のまえに、ある日いきなり母親を名乗る女が現われたとしたら、誰だって動揺するだろう。なんなら攻撃的になるかもしれない。僕に関して言えば、びっくり仰天して開いた口がふさがらなかった。
こんな見え透いた罠にひっかかるやつなんているのだろうか? いくらなんでも十歳を見くびりすぎている。新手の詐欺かもしれない。この女はどこかで僕のコジンジョウホウを手に入れ、フィリピンとかにいる悪党の命令を受けてこんな手の込んだ芝居を打っているのだ。
彼女を睨みつけたまま、じりじりと校門のほうへ後退りした。鳴き真似上手なカケスが、まったく可愛げのない声でギャーギャー騒いでいた。それが警報みたいに頭のなかでわんわん鳴った。少しずつ距離が空き、くるりと回れ右をして駆け出そうとしたまさにそのとき、彼女がまたもや口を開いた。
「そうだよね、信じられないよね。怪しすぎるもんね」
いくら猫撫で声を出されても、僕はけっして油断しなかった。そこには花期を迎えたのらぼう菜を売りつけようとするあざとい響きがあった(祖父母がそんなやくざな商売をしていたという意味ではない)。そんな不誠実なものにたぶらかされるつもりはなかった。
「ペイジはジミー・ペイジのペイジ」彼女がすがるように言った。「あんたのパパはジミ・ヘンドリックスと迷ってたけど、いくらなんでも久保田ヘンドリックスはないからね」
足に根が生えた。
気を取り直した蟬たちの声が山間に谺していた。
登校してきた子供たちが、僕たちに無遠慮な視線を投げかけては、学校へ吸いこまれていった。
ジミーかペイジか
じゃあ、なんでジミーにしなかったのさと問えば、久保田ジミーなんてお笑い芸人みたいじゃないかと父はいつもしれっと答えた。
久保田炳児。
それが僕の名前だ。「炳」には「光り輝く」という意味があって、ふつうなら「へいじ」でなんの問題もないのだけれど、僕の両親はたぶんほんの少しばかりふつうじゃなかったのだろう。さもなければ、わざわざ正しい日本語読みをねじ曲げたりはしない。こんな初手から間違ってしまったような名前の由来を尋ねると、父は悪びれもせずに教えてくれた。
「レッド・ツェッペリンのギタリストの名前さ」
「それってなんなの?」
「大むかしのロックバンドだ」
名前のことを考えるたびに、僕は鉄道線路の転轍機をイメージしてしまう。ぜったいに触ってはいけない転轍機を父親が面白半分に動かして、僕という列車を間違った線路に引きこんでしまった。「へいじ」なら武士みたいでかっこいいのに、「ぺいじ」になったとたん、お花畑であはあは笑いながら蝶々を追いかけているような洟垂れしかイメージできない。政府は半濁音を名前に使うことを禁止すべきだ。
そこで祖父に、僕にこんなへんてこな名前をつけなければ収まらなかった父の事情を尋ねてみたりもした。
「そりゃ、おまえのお父さんがずっと音楽をやっていたからだろう」というのが祖父の見解だった。
「レッド・ツェッペリンのような?」
「音のでかさだけでいったら、まあ、そうだな」
「あと、髪の長さとか? ピアスとか?」
「いまだにそういうものが世界のすべてだと思ってるんだろうな、あいつは」
「なんで誰も反対しなかったのさ?」
「ペイジは自分の名前が嫌いか?」
「大嫌いだね!」
「しかし、ものは考えようだぞ。名は体を表すと言うからな。おまえは誰も持ってない名前をもらった。だから、これから誰も歩んだことのない人生を歩めるかもしれないよ」
僕は少し考えてから反論した。「お父さんの名前は久保田静市だけど、音のでかいロックバンドをやってるじゃないか」
「そういうこともあるんだ」祖父が言った。「人ってのはあたえられたものを大切にして生きていくか、さもなきゃ憎んで生きていくかのどっちかだからな」
つまり、と僕は思った。お父さんは親にあたえられたものを憎みながら生きてきたのだ。静市なんて名前をつけられた反動で、でかい音のロックに走った。彼はそこから摑み取った大切なものを自分の息子にあたえ、そのせいで僕もまたこれからレッド・ツェッペリンを憎みながら生きていかなければならないというわけだ。
素直叔父さんが遊びに来たときも、僕は性懲りもなくこの問題を持ち出して詰め寄った。
「叔父さんってさ、むかし悪いことやって刑務所に入りかけたんだよね?」
「誰に聞いた?」素直叔父さんが舌打ちをした。「どうせ兄貴だろ」
「このへんじゃ有名な話だよ」
「俺がなにをやったかなんて訊くなよ。おまえみたいなガキにしゃべるつもりはねえからな」
「車泥棒だったんでしょ?」
素直叔父さんが唸った。
「そんなことはどうでもいいんだ。お祖父ちゃんたちはいつも叔父さんのことをボロクソに言ってるけど、僕は気にしてない。それより僕が聞きたいのは、叔父さんも自分の名前が嫌いなのかってこと。だってせっかく素直ってつけてもらったのに、ぜんぜん素直に生きてこなかったから」
「さっきからいったいなんの話をしてんだ、おまえは?」
だからね、と僕は叔父さんの物わかりの悪さに辟易しながら言葉を継いだ。「お父さんは静市なのに、バカでかい音のロックに取り憑かれてる。叔父さんは素直なのに犯罪者じゃん? じゃあ、僕はどうなるの? ペイジの反対語っていったいなんなのさ?」
「犯罪者が素直じゃないなんて誰が言った? むしろ素直すぎるがゆえに道を踏み外すことだってあるんだぞ。いいか、ペイジ、へんな名前だからって自分を卑下することはない。おまえのせいじゃないんだからな」
「叔父さんもやっぱりへんだと思ってるんだね」
「なにをへんと思うかは人それぞれさ。日本でへんでも、外国だとちっともへんじゃない名前だってたくさんある。むかしイタリアのオートバイレーサーにウンチーニってやつがいたぞ。な? 久保田ウンチーニじゃなくてよかったじゃないか」
「否定しないんだね」
「下には下がいるってことさ。考えてもしかたないことをくよくよ考えるな。よし、ペイジの反対語か……簡単さ。いいか、ペイジの反対語はな、ジイペだ!」
それを聞いて、僕は危うく笑い死にしてしまうところだった。ペイジの反対語はジイペだって? そんな、まさか!
素直叔父さんは、本当はやっぱりとても素直な人なのかもしれない。そうじゃなければ、こんなにも子供のことがわかるはずがない。
「俺は自分の名前が気に入ってるよ」僕の頭を乱暴に撫でながら、素直叔父さんが言った。「どうするか迷ったときは、いつも自分の胸に訊けばいいんだからな」
どうするか迷ったときは自分の胸に訊く――素直叔父さんの言うことを真に受けて、僕は祖母にしつこくつきまとって母親のことを尋ねた。ねえねえ、なんで僕にはお母さんがいないの? 死んじゃったの? どんな人だったの?
畑から採ってきたばかりののらぼう菜を流しで洗いながら、祖母がうるさそうにこう言った。
「さあ、手を洗っておやつを食べちゃいな」
(続きは本誌でお楽しみください。)