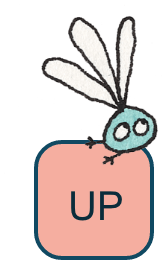建て付けの悪い窓を、桐乃が力をこめて開けると、視界の隅に団地の給水塔が見えた。
先端は球形を上下から軽くつぶしたような形で、白玉だんごのようにも見える。円盤の上半分は白に、下半分は茶色に塗られていて、その下に続く細く白い円柱が地上と繫がっていた。
二階にある桐乃の部屋から見上げる角度にある給水塔は、まるで花の蕾を裏から覗いているように見えた。小さな頃、父は「あれは宇宙人の基地なんだよ」と桐乃に言い聞かせた。あの先端から宇宙人がこちらを見ているかも、レーザービームで攻撃されるかも、と思うと幼い桐乃は気が気ではなかった。だから、給水塔が目に入るたび、走って自分の部屋に帰った。なんて、馬鹿で純粋な子どもだったのだろうと桐乃は思う。
中学二年になった今、改めて給水塔を見てもなんの感慨も湧かない。
春のほこりっぽい風が部屋のなかに入ってくる。窓の外から見える景色のほとんどは、隣の棟の外廊下で、それも子どもの頃から見慣れた景色だったから、心はぴくりとも動かない。もう少し視線を上げれば、隣の棟の上に切り取られた春の青空が見えたが、晴天だからといって、十四歳の桐乃の心を浮き上がらせるものではなかった。
「桐乃、遅刻するよ! 早くしなさい!」
台所から母の声が飛ぶ。
「わかってるって!」
力をこめて、開けたばかりの窓を閉めながら、叫ぶように返事をする。今、支度をしようとしていたのに、遅刻する、とか、早く、とか言われると心の底からむかむかする。なかなか閉まらない窓の古さにも、いらっとした気持ちがわき上がる。
桐乃が住むのは、ふたつの市にまたがる巨大な団地群で、上空から見ればその敷地は体に収まる肝臓の形に似ていた。肝臓を横に突き刺す針のように、団地の間には川が流れ、その南側には比較的新しい時期にできた高層団地群、その北側には団地群のなかでいちばん古く作られた低層の団地がドミノのように並んで立っている。新しい団地群には家賃の安さを求めてやってきた若い日本人家族が多く、さらに家賃の安い低層団地群には、日本人だけでなく、さまざまな国の人間も多かった。
団地のなかでも高層団地群の「新しい団地」の人間が、低層団地群の「古い団地」の人間を見下す、ということがしばしばあったが、団地の外に出てみれば、もれなく「団地の人」と呼ばれたし、子どもたちは一緒くたに「団地の子」と呼ばれた。
桐乃が住むのは、古いほうの低層団地群だ。八畳の居間と六畳の両親の部屋、桐乃が暮らす三畳の部屋、そして台所、浴室、トイレ、洗面所。それが桐乃の家のすべてだった。
二千戸以上の部屋がある団地群は、なぜだか紅葉団地と呼ばれているが、ここには紅葉するような木々や植物は植えられていない。低層団地群はゆうに築五十年を超えている。団地そのものにガタが来ているから、いつもどこかの部屋で修繕工事が行われている。桐乃の隣の部屋も二カ月前に水道管が破裂して、その修繕工事がこの前、やっと終わったばかりだった。分厚いコンクリートに穴を開けるようなノイズが夕方まで続き、桐乃は耳栓をして宿題をした。うんざりした気持ちが幾度もわき上がってきた。
桐乃はここで生まれ、育った。でも、この古くてぼろい団地が嫌いだ。
「団地の子はさあ……」
小学校でも中学校でも、そんな言葉を数えきれないほど聞いた。そのあとに良い言葉が続くことはほとんどない。小学校でも中学校でも、団地の子は、クラスにだいたい七、八人はいた。「団地の子」という言葉の響きそのものにも、どこか侮蔑の気配がにじむ。上から物を言われているような気持ちになる。とはいえ、「団地の子」と口にしてしまう人たちの気持ちが桐乃にはわかる。ここの団地に、特に低層団地群に住んでいる人たちは、お世辞にもお金持ちとは言えないし、その子どもたちも上品とは言えない。学校で問題を起こすのは、大抵「団地の子」なのだった。
問題を起こす団地の子には二種類いる。悪い日本人と悪い外国の子どもだ。この団地には日本人じゃない人たちがたくさん住んでいる。「外国人が」と口にすると、すかさず母に注意されるのも、桐乃には納得のいかないことだった。もっとくだけて「外人が」と言うと、母は目を三角にして怒った。
「外国人なんていう人はこの世にはいない」と言うのが母の持論だ。
「いやいるでしょ、そこらじゅうにたくさん」と言い返したくなるくらい、桐乃の住む団地には外国の人が多かった。いちばん多いのはベトナムの人で、中国、カンボジア、フィリピン、ブラジル……、だから、ゴミ捨て場には、日本語を含めて六カ国語の注意書きがあった。
外国の子どもだって、いい人間と悪い人間がいる。それもわかっているけれど、学校や団地で起こるトラブルのほとんどは、外国の子どもたちが引き起こす。授業はそのたびにストップするし、大きなトラブルがあれば、団地の見回りに父や母が駆り出される。学校では桐乃にわざと聞こえるように言う生徒もいた。
「また、団地の子がさあ……」
そう言われてしまえば反論の余地はない。
「なんで、この団地に住んでんの? いつまで住むの? 引っ越さないの?」
何回、そう母に尋ねたことか。
「最高じゃない。この団地」
目を輝かせながら、そんな斜めの言葉が返ってくるばかりで、母には何を言っても無駄だ、と思わせられるのに十分だった。父に同じことを言えば、
「ごめんなあ、父さんの稼ぎが悪いからなあ」と眉毛を下げて頭を搔きながらそんなことを言う。その言葉を聞くと、桐乃は自分がひどいことを言った気持ちになって後味が悪かった。
そうは言っても団地が嫌いだ、と桐乃は思う。敷地のなかを歩いていると、外国の大人の人から下卑た言葉(それが外国の言葉でも、発している人の表情や態度で意味はなんとなくわかってしまう)をかけられることがある。「うるさい!」と反論するものの、内心は怖くて仕方がなくて、走って部屋まで戻った。「どこが最高なんだよ」と母の言葉にいらつきながら、誰もいない部屋のドアチェーンがしっかりかかっているのを何度も確かめた。我が家が裕福じゃないことはもう仕方がない。でも大人になったら(例えば、大学に入ったら)もう一目散にこの団地を出て行くつもりでいた。
(続きは本誌でお楽しみください。)