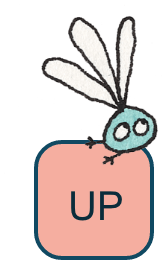一章
一
江戸城は大手門に集結する大名行列が名物なら、俺は華を添える看板役者だぜ。
陸尺の桐生は、ごった返す門前を眺めながら、周りの男たちより頭一つも二つも抜き出た長身をそびやかした。
寛保二年皐月十五日(新暦一七四二年六月十七日)。今日は江戸在府の、二百を超える諸国大名が一斉に登城する月次と呼ばれる日だ。
「ねえ桐生。まだ殿さまの下城まで間があらあ。どうだい」
二人で担いできた駕籠を下ろし、額の汗を拭いながら龍太が顎をしゃくる。その先には、酒樽に板を載せただけの俄か屋台がひしめき合っている。
この日のために、商売っ気のある連中が出す、さまざまな屋台も名物の一つだ。
「皐月の半ばだってのに、やけに蒸すねえ。冷えたのを一杯、奢るよ。好きだろ」
門前は、諸国家臣団や供を勤める者たちの人いきれで、息苦しいほどだ。供が八十人を超す国もあるため、ここには一万人を超える男どもが詰め込まれている。
「いっつも言ってんだろ。勤めが済むまで、俺ぁ、やらねえよ」
「つれないなあ。下城まで半刻もあるってのに、酒でも入れないと間が持たねえや」
供のなかには、酒を堂々と干す者、派手に蕎麦を手繰る者、だらしなく寝そべる者までいる。
遠巻きにしている人垣は、諸国から江戸へ下って来た旅人たちだ。もの珍しげに、江戸城に集う御家来衆を眺めている。ふと赤い小袖の娘と目が合った。
娘はずっと桐生を見つめていたらしい。桐生は娘に片頰だけで笑って見せた。娘は見る見る紅潮し、慌てて人垣から離れた。
「田舎娘を誑かしてんじゃねえよ。女と見りゃあ、片っ端から手を出しやがって」
同じ陸尺の利助と、その腰巾着の末吉がすかさず絡んできた。
「調子ぶっこかしてると、田舎大名の国抱の陸尺から、因縁を付けられるだろうが。あいつらは江戸抱の俺らに張り合いたくて始終、こっちの動きを窺っているんだからよ。お前のせいで恥なんざ搔かされたら、どうすんだ」
「そんな野暮は、しねえよ」
桐生は鼻で嗤った。それだけで前のめりに群れる女たちが嬌声を上げる。桐生を見に来た常連のお内儀連中だ。
「ご覧よ、あれが噂の〝風の桐生〟だよ」
お内儀の一人が、新参らしい右隣のお内儀を肘で突く。
「風みたような脚さばきと身ごなしで、そりゃあ見事に駕籠を担ぐのさ」
「風って、どんな塩梅で駕籠を担ぐのさ」
新参のお内儀が首を傾げる。
「まあ、今日も披露してくれるんじゃないかねえ。あたしゃ、これだけが楽しみでさ」
ぞろりと長い隊列を組み、通りを埋める大名行列は、町人にとっては邪魔でしかない。六万石、七万石の小身の大名でも先頭から殿まで連なれば、行列の長さは四十間(約七十三メートル)におよぶ。
さらに行列が連なる大大名家は複数の隊に分け、四半刻ほどずらしながら、小出しに行列を進める。町人に対する配慮だが、それでも疎ましがられている。
だが嫌われ者の大名行列の中でも、箔と威勢を添えながら軽やかに主君を担ぐ桐生は、町人の人気を集めていた。
左隣のお内儀も調子を合わせ、聞こえよがしに声を上げる。
「そそ、やっぱり〝風の桐生〟がいなくっちゃあ、どんな大大名さまの行列でも、締まりがなくっていけないわ。こうね、ぱあっと華があるんだよ」
桐生はお内儀たちに、片目をつぶって見せた。確かにそんな芸当ができるのは、上大座配の俺ぐれえのもんだよ。
陸尺の給金は背丈によって格差がある。背丈が五尺八寸から六尺(約百八十二センチ)を超せば最も格上の上大座配になる。その下に中座配、並小座配と続き、五尺五寸五分以下の者は平人陸尺。上大座配の給金は、平人陸尺の四倍だ。
背丈に加え、面立ちのよさも斟酌されると、まことしやかに囁かれている。
だから桐生は門前で主君を待つ間も、決して座り込んだり、吞み食いはしない。隙も無粋も人に見せぬが、桐生の意気だ。
大振りな湯吞の酒を片手に、龍太が戻って来た。桐生に付き合い、立ったまま湯吞を傾ける。他家と諍いを始めた供たちがいるらしい。どこかで罵声が上がっている。これも毎度の些事だ。
酒と食い物を腹に収めれば、次にやることは知れている。先ほどの諍いもすぐに治まり、そこかしこで車座の賭場が開き始めた。
「お武家なんてもんは、とんだ屁っぴり腰だよな。流れもんの奉公人連中が相手だと、あからさまに賭場を開かれたって、𠮟責の一つも出せないんだぜ」
酒を舐めるように含みながら、龍太は呆れたように呟く。
御公儀は慶長十五年(一六一〇年)から延々と、流れ者の奉公人を雇い入れることを禁じてきたが、武家は密かに召し抱え続けた。江戸に溢れる浪人にとっても、またとない稼ぎ場だ。
国から用人を抱えて参府するだけで、かなりの費用が掛かる。財に乏しい大名家は、江戸で流れ者の奉公人をひとまとめにして買う。用向きが済めば、ひとまとめの奉公人は別の御家に向かう。安価な使い捨ては、いつでも重宝されている。
当然のように、そこに国抱の奉公人のような主従はない。故に流れ者の奉公人は勝手のし放題、殿さまと家臣は見て見ぬ振りを決め込む。
「しっかし頼朝の奴は、人使いが荒いよなあ。一斉に登城のどさくさに紛れて、俺と桐生に高家肝煎の駕籠担ぎを差配したのは今朝だよ。どうせ担ぐはずだった奴らも流れもんで、深酒でもしたんだろうね」
「そう言やあいつ、妙な名乗りをしてたっけな。そんな高貴な面ぁ、してねえくせに」
「渾名に決まってらあ。鎌倉の国を一人で築き上げちゃった遣り手って意味さ。噂じゃ、自分で付けた渾名らしいよ。引く手数多の桐生を差配して稼がせてもらってるくせにさ」
もともと口数の多い龍太だが、今日は特によく喋る。
「龍太、酒を過ぎるなよ。お前はてえして酒に強くねえんだから。たかが千四百石の貧乏大名だろうが、今日はお偉い高家肝煎さまの駕籠だからな」
「わかってるって。俺らは江戸抱として、いろんな旗本や殿さまを担いで活計を立てているけどさ、高家肝煎となりゃ格が違うや。はしゃいでもみたくなるってもんさ」
湯吞を傾け、にかっと笑う。
「そんな高家の殿さまを、桐生と運べるのが一番、嬉しいんだよ。やっぱり桐生が加わると、ぐっと行列に箔が付く。それに仕事が終わると、いつもさっさか一人で帰っちゃうし。桐生と話せるのは、こんな時だけだからさ」
桐生は陸尺連中を見回した。
仕事仲間と連れ立って遊ぶなぞ、真平御免だ。十七になった龍太はいい奴だし、このところ背丈がぐんぐんと伸びたおかげで桐生の相方を勤められるようになったが、それとこれとは別。つるまない仔細は簡単だ。陸尺は揃いも揃って格好いいからだ。
どいつもこいつも上背があり、おまけに美丈夫で粋な男が多い。
自らの様子の好さを心得ているせいか、陸尺はつるんで派手に町を闊歩したがる。一人目立ちが好きな桐生は、決して奴らとつるまない。
「お、戻って来なさったぜ」
大手門付近がざわつき始めると、家臣団は、押取刀で主君が乗る駕籠に走る。続いて流れ者の供たちがだらだらと駕籠に集まり、下城の支度が始まる。
「桐生、勤めが終局たら《市村座》の芝居はどうだい。いい芝居が掛かってるよ。って桐生は、どうせ行かないよな」
「桐生なんざ放っておけよ、龍太」
通り過ぎざま、利助が吐き捨てた。
「龍太、お前はほんっとに桐生に岡惚れしてんだな」
末吉が、きいきいと笑う。
「違えよ。おいらは桐生から陸尺のいろはを教わったからさ」
もぐもぐと龍太が呟く。中座配の利助は、桐生とさほど背丈が変わらない。駕籠舁の修練も積み、江戸の道筋にも明るくなった。おまけに大名や旗本に顔が売れ始めたとなれば、そろそろ駕籠宿の寄合で上大座配に推挙されるやも知れない。
「桐生、粧香っつう上玉の芸者をモノにしたんだってな」
利助が低い口調で問うた。何だ、こいつもやっぱりただの助平か。桐生は鼻で嗤って応えなかった。ここのところ、妙に絡んでくる利助が鬱陶しい。上大座配も間近ともてはやされ、桐生とがぜん張り合うつもりらしい。
「そこな駕籠舁どもっ。早うせい」
今日の桐生と龍太の雇い主である家臣が、苛立った様子で急く。
「さ、高家肝煎の殿さまのおなりだ、行くぜ」
桐生は龍太の背を押した。
「桐生、あんまり利助に絡まないほうがいいよ」
「絡んでねえよ。あっちがいちいち盾突いてくるんだよ」
「けど、利助は今、若年寄の専らの─」
しつこい龍太の背をどやした。
「利助なんざ、どうでもいい。行くぞ」
(続きは本誌でお楽しみください。)