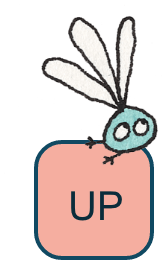第一部 台北、初夏
1
重慶南路を吹き抜けていく風の色はたとえるなら、なんの色だろう。ふわりとした羽毛のような雲に、薄桃色の夕方の光が静かに広がっていく空を見ながら、わたしは一瞬そんなことを考える。もうすぐスコールが降るのか、湿気で飽和状態の空気に乗って、排気ガスと深い森のようなにおいが漂ってくる。帰宅を急ぐバイクのクラクションとエンジンの騒音がリズミカルに響く夕方の街を、北門に向かって歩く。巨大な城郭のような台北車站を背に、大通りを車に気をつけてわたると、派手な電飾の看板が目に飛びこんできた。
そこからまっすぐ進んで、湯気が立ちのぼる餃子屋の蒸籠を目印に、名もなき小路に入って、ちょうど十歩いったところの右手に、幸福古物商というガラクタが山積みになった古道具店がある。最近のわたしのお気に入りの場所だ。
ガラガラとガラスの引き戸を開けると、古い家具と堆積した埃の、どこか懐かしいにおいがする。店の奥に座るトッポ・ジージョのような小さなおじいさんは、少しだけ顔を上げてこっちを見たけれど、なにもいわずまた視線をよれよれの新聞紙に落とす。おじいさん自体がひとつの骨董品みたい。
すぐ後ろからわたしを押しのけるように、赤い花柄シャツのおばあさんが店に入ってきた。竹の皮に包まれたちまきをひとつおじいさんにわたすと、閩南語でなにかいって慌ただしく店をでていった。前に見たときも、胡椒餅をもってきていたから、もしかしたらおじいさんの家族なのかもしれない。引き戸を勢いよく閉めるガシャッという大きな音が響いて、店にはまた静けさが戻ってくる。
わたしは、きょうもガラクタの山のなかに切りこんでいって、なにをさがすというわけでもなく、たださまよう。
─安月給なのにまた無駄遣いか─さっちゃんってもの好きだな。小言をいうジュリの顔が頭に浮かぶ。シェアメイトのジュリは、わたしのことをさっちゃんと呼ぶ。それが小学校のときみたいでわたしは少しむずがゆく感じる。
ゲストハウスのスタンプが押された日本語のガイドブックの山の向こうに、埃をかぶった焦茶色の革のトランクが見えた。四角に真鍮の鋲が打ってあって、キャスターもなにもついていない。古い映画のなかでヘップバーンがもっているようなトランク。薄暗い店のなかで不思議とそのトランクだけが鈍い光を放っているように感じた。
視線を上げると店主のおじいさんと目があった。わたしの使える数少ない北京語で、多少銭、と値段をきいた。
おじいさんは目を擦り、トランクを見ると、何回か瞬きをして、ふいに懐かしそうな表情を浮かべた。少しの沈黙の後、イーチェン、とぽつりといった。すぐにまた視線を新聞に戻す。
一千元、二〇一三年現在の相場ではだいたい三千円くらいだ。わたしは、謝々、とだけ返事をする。日常的には使うことがなさそうな革のトランクの値段として安いのか高いのか、いまいちぴんとこない。
三十分くらい逡巡して、買わずに店をでた。ジュリのどこか突き放すような、ふーん、気に入ったならいいんじゃないの、という冷ややかな視線が脳裏に浮かんだのもたしかだ。
あれだけ熱かった昼間の太陽は、西に沈みこんでいて、淡水河のほうから気持ちいい五月の風が吹いてくる。いまは真夏の入口にあって、わたしは昼間の熱気が少しだけ静まるこの時間帯が一番好きだ。わたしの生まれ育ったつくりものめいた多摩ニュータウンとはまるで違っていて、生きている街の気配がある。
物心ついたときから、遠くへ、遠くへいきたかった。ずっとかかえていた得体の知れない息苦しさから逃れるために飛びだしたのが、地球の裏側とかではなくて、羽田から三時間程度のフライトでたどりつく台北だというのは、わたしの度胸と幸運の限界なのかもしれない。それでも、大学の卒業旅行で大好きになったこの街の求人をインターネットでみつけたとき、ふっと心が軽くなったような気がした。それから二年が過ぎるけれど、あいかわらず亜熱帯の街のにおいも、食べ物も、うらさみしい小路にいたるまでわたしを惹きつけてやまない。
新光三越のショーウィンドウの鮮やかな紫のペイズリー柄のシャツが目に飛びこんできて、わたしは立ち止まる。
─ああ、わたしもあんなシャツをもってたな。ライブハウスのステージで赤いジャガーをかき鳴らしていたのもはるか遠い昔だ。ガラスに映りこんだわたしの姿には、西荻窪の高架下を歩いていたパンクガールの面影はほとんどない。猫みたいとよくいわれたくりくりの目とショートボブ、靴底に穴が開く寸前の黒いコンバースと色あせたスキニーパンツは変わらないけれど、二十五歳のわたしが纏っている空気は、あのころからは五キロくらい増えた体重と同じで、ちょっとだけ重たい。
なかなか沈まない南国の夕日に別れを告げて、台北車站のエスカレーターを駆け下りた。ホームに入ってきたばかりの地下鉄に飛び乗る。
ベビーカーのなかのおまんじゅうのような顔をした赤ちゃんに、おばあさんが笑いかけているのを横目で見ていたらあやうく乗り過ごすところだった。こっちのひとは、ほんとうに子どもに優しい。中央線で押しつぶされそうになりながら出勤して、帰りはすべてシャットアウトして座席で眠りこんでいたころから考えると、まるで異世界のようだ。でも、チートスキルもなにももたないわたし自身は、実はあまり変わっていないのかもしれない。
地下鉄の長い階段を上り、淡水河に向かって歩く。橋の手前で左に曲がってしばらくいくと、ようやくわたしとジュリが暮らす迪化街という古い街路にたどりつく。鍋やたわしの並ぶ古めかしい金物屋と、モダンなカフェが混在する通りを歩き抜けるころには、懐かしい家に帰ってきたような気持ちになった。
すっかり馴染みになった蒸し餃子屋さんで、打包、とテイクアウトをたのみ、ついでに雑貨屋で台湾ビールと八角香るゆで卵も買った。見た目とにおいはインパクトがあるゆで卵。だけど、殻を剝くと案外香ばしくておいしいのだ。
風に乗って、薬膳粥のような、子どものころ、風邪をひくたびに母さんにのまされた苦い薬のにおいが漂ってきた。この周辺は、台湾で一番といわれるくらい漢方薬屋や乾物屋が集まっている地域で、通りには漢方薬のにおいが充満している。
ジュリとわたしが暮らす部屋は十八世紀末に建てられたバロック建築の古びたビルディングの三階にある。このあたりの1LDKで月一万元は破格だよ! とわたしの働く日本語学校の受付のシーティンが目を丸くしていっていた。どんな事情があるのかはわからないけれど、天井はリノベーションを途中であきらめたのか配管が剝きだしで、シャワーは憎たらしくなるくらいトイレの真横にあって、浴びるたびに床がびしょびしょになる。それでも、まったく気にならないのは、わたしが育ったのもここと似たり寄ったりの古ぼけたマンションだったからだろう。
扉を開けると真っ暗なリビングのソファーで、ジュリは頭に大きなヘッドフォンをつけて、二十八インチのモニターをぼんやりとながめていた。画面の点滅にあわせて、フローリングの床に赤や緑の光が反射する。
リビングの蛍光灯のスイッチを入れる。ジュリはやっとふりむいて、眠たそうに目を擦った。わたしが洗濯したばかりの丈の長い生成りのコットンシャツを勝手に部屋着にしていた。すらっとしていて、手足の長いジュリのほうが、わたしより似合っている気がする。
「もう、夜?」
ジュリにはおよそ時間の感覚というものがない。為替証拠金取引とか、通貨スワップとか、説明をきいてもわたしにはいまいちわからない仕事をネットの海をさまよいながらこなしている。いま、画面の端っこには血圧計のように上がったり下がったりを繰り返すユーロと円が映っている。
「蒸し餃子とゆで卵買ってきたよ」
そういってキッチンのテーブルに置く。ジュリは背伸びをして、ちょっと照れたような顔をして、ありがと、と小さな声でいった。ジュリは、お礼をいうときに、いつも恥ずかしそうな顔をする。
キッチンの白いサイドシェルチェアに座ると、ジュリは左手で壁のリモコンをとって、テレビをつけた。画面のなかで赤いドレスを着た女のひとが歌っている。日本でもきいたことのある古い歌謡曲だ。ジュリは画面をまったく見ないで、早くして、とわたしが食卓の準備をするのを子どものように待っている。
ジュリは無音の空間に耐えられないらしい。なんで、って前にきいたら、長い沈黙のあとに、ひとの声がきこえるとこはセーフゾーン、とほとんどきこえないような小さな声でいった。ジュリはたまにお酒をのんだときだけ心の声を漏らすように話しだす。わたしが知っているのは、ジュリが十三歳で在日一世のハルモニの家に引きこもるようになって、その十年後に一念発起してワーキングホリデーで海をわたってきたということだけだ。この部屋にきてからは、やっぱり引きこもりに逆戻りしている。
冷蔵庫から黒酢を取りだして小皿に注ぐ。刻み生姜と黒酢という小籠包スタイルが蒸し餃子にもぴったりだと少し前に気がついて、それからはいつもひと手間でも生姜を刻んでいる。
「いただきまーす」
生姜を散らした小皿をテーブルに置くよりもはやくジュリが蒸し餃子に箸をのばす。わたしも負けじと餃子をつまむ。まだ温かかった。厚い皮にたっぷりのスープが閉じ込められていて、口のなかいっぱいに肉汁が染みだしてくる。ジュリもおいしそうな顔をして頰張っている。三十個もあったのに五分できえた。
緑色のラベルの台湾ビールをのみながら、帰りに立ちよった幸福古物商の話をすると、またガラクタを買ってきたの、とジュリが冗談めかして笑った。きょうは機嫌がいいのかもしれない。
「ううん、ジュリがばかにするし買わなかった。でも、すごい古い革のトランクがあって、なんか気になるんだよね」
「ばかになんかしてないよ! さっちゃんっておもしろいなあって思ってるだけ。トランクって旅行いきたいの?」
─どうなんだろう。あのトランクをもって旅にでるなんて考えもしなかった。それよりも、あのトランクが旅をしてきた時間そのものに惹かれているのかもしれない。
うまく答えられないまま、ゆで卵の殻を剝いていると、ジュリは、ごちそうさま、といって早々にモニターの前に戻った。ゆで卵の黄身がきらいなのか、白身だけ食べてあとはテーブルに放置してあった。ジュリはほんとうに小さな子どもみたいで食べたら食べっぱなしで、散らかしたものをおよそ片付けたことがない。でも、もうすっかり慣れた。ジュリにはひとに世話を焼かせる天性の才能のようなものがあるのかもしれない。
テレビでは、どこかの国の吹き替えドラマをやっている。口の動きとセリフがまったくあっていない。目がぱっちりした女優さんが屋台の行列に並んでいるシーンを見ていたら、ジュリとはじめて出会ったときのことを思いだした。
まだ街がうっすらと冬の空気を纏っていたころ、わたしは夜の授業がはじまる前の休憩時間に近くの胡椒餅屋の行列に並ぶ。でもわたしのすぐ前で売り切れてしまった。からっぽになったタンドリーチキン窯のような鉄の壺を指差して、冷たく手をふる店員の女の子の顔を見ながら、わたしは香ばしい肉の餡とサクサクの生地を想像して、しばらくその場から動けずにいた。
目の前で背の高い女の子がうれしそうに湯気ののぼる胡椒餅の袋を握りしめている。艶のある黒髪は内側に軽くカールしたおかっぱで、意志の強そうな二重の大きな目をしている。古めかしいダッフルコートにグレーのチェック柄のプリーツスカート、汚れたナイキのバスケットシューズという中学生のような格好がどこかアンバランスな印象。─何歳くらいなんだろ。高校のころ、たまたま夜のスナックが休みだった母さんと一緒に見たドラマの女優さんに似てるかも─そんなことを取りとめもなく考えていたら、その子と目があった。
その子は大きな目でわたしの顔をのぞきこんできた。
「─サチコねえちゃん? 覚えてへん? あたし中学で京都引っ越しちゃったけど」
夕方の強い西日のなかで、その子の薄茶色の目はほとんどベージュに近くて、透き通っていた。小学校の記憶をたどってみても、いま関西の言葉で話しているその子がいたかどうかやっぱり思いだせなかった。
「ごめん、だれ?」
「パク・ジュリよ。サチコねえちゃん、六年三組やったよね? マンションの前まで送ってくれたことあったやん」
そういわれてみれば、当時はまだ優等生のふりをしていたわたしは、歳下の女の子たちを家まで送ったりしながら、ぶらぶらして帰っていた。どうせ部屋に帰っても母さんはパートでいなかったし。
「そうかも。ごめん、忘れてて」
「ずっと前のことやしね……それより、思いっきり普段着やけど、こっちに住んどるん?」
「うん、日本語教師してるの。旅行?」
その子はうなずいてしばらくなにかを考えていた。口を開いて、言葉をさがしているけれど言葉がでてこない、そんな感じだった。そのとき、薄暗いお店の奥にかけられた柱時計の針が休憩時間の終わる五時半を指しているのが見えた。
「ごめん、わたし、もういかなくちゃ。そこの角曲がったとこの日本語学校で働いてるの。台北しばらくいるなら寄ってみてね」
その子は、無言でうなずいて、それでもやっぱりなにかいいたげな顔をしていた。
日本語学校の下のコンビニでシーチキンおにぎりを取ってレジに向かう途中で、なにかにつまずいた。足元をよく見るとぼろぼろのコンバースのつま先のソールが剝がれかかっていた。その瞬間、さっき見た女の子の白いバスケットシューズを思いだした。まるでずっと歩いて旅をしているんじゃないかというくらい、泥で真っ黒になっていた。
─どうして、あんなに靴が汚れていたんだろう。
わたしが胡椒餅屋の前まで駆け足で戻ると、その子はやっぱり袋をもってどこへいくでもなくぽつんと佇んでいた。
「ねえ、ホテルどこ泊まってるの」
わたしがそういうと、少し恥ずかしそうにうつむいてから、きこえないくらいの声で、お金なくて三日前に追いだされちゃった、とつぶやいた。
それからわたしの目の前に、胡椒餅の袋を差しだした。ぎこちない笑みを浮かべているけれど、その手は祈るように震えていた。
「あんな、これ半分あげるし、泊めてくれへん? 今夜はもう野宿とかしとうないし……」
半分かよ、と内心つっこみながらも、野宿なんてだめに決まってるでしょ、おねえさんにまかせときなさい、とつい口にしていた。
その子は、ほんとうに安心したように笑った。胸を鷲摑みにされるような、そんな笑顔だった。どこにもいく場所がないのか、そのままわたしについてくると、日本語学校の受付の前のベンチで仕事が終わるまでずっと待っていた。その子がまったく動かないのを心配したシーティンが事務室のお菓子をあげて、毛布まで貸してくれたとあとできいた。
数日だけのはずが、それから三ヶ月間、ジュリはずっとわたしの狭い部屋に住みついている。わたしの喋る標準語に影響されたのか、いつのまにか関西の言葉をあまり使わなくなった。小学校まで関東にいたのに、ジュリの話す標準語はどこかぎこちなくて、いつも言葉をさがしながら話している。
一番最初の取り決めでジュリのスペースはロフトだけということにしていたのに、あっというまにリビングのソファーで眠るようになって、いまではわたしがロフトに追いやられている。それでもそんなに腹が立たないのは、やっぱりわたしもいい加減ひとり暮らしがさみしくなってきていたのかもしれない。家賃はもらわず、たまに儲けがあったときだけ、教えたつもりもないわたしの口座に、わたしの給料一ヶ月分以上の振り込みがある。
(続きは本誌でお楽しみください。)