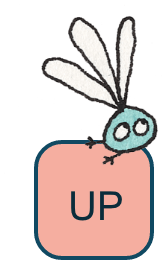1
スーツ姿の男がレジカウンターにガムを置き、無言でスマートフォンを提示してきた。
「バーコードを表示していただけますか」
椎名和彦は丁寧な口調で言った。男が怪訝そうに首を傾げ、画面をスクロールする。
「バーコードって? ないねんけど」
「あ、PayPayとかですかね。でしたら、こちらを読み取ってください」
レジ前に備え付けられた、キャッシュレス決済用のQRコードを指し示す。
「どういうこと? 現金で払うけど」
男がおもむろに財布を取り出した。
「あれ。えっと、そのスマホは?」
「はあ? これやんけ」
眉を顰め、責め立てるようにスマートフォンを突き出してきた。
しばらく画面を見つめ、ようやく理解した。
「すみません、子供の日のデコレーションケーキをご予約のお客様ですね」
「そうそう。書いてるやんけ、最初から」
苛立たし気に言われ、舌打ちされた。俄かに、胃の底が重たく感じられる。
「失礼しました。こちらのご予約のケーキと、ガムが一点。お支払いは現金ですね」
「だから、そうやって」
「すみません。少々お待ちください」
精一杯の愛想笑いを浮かべた。男の目を見ないようにして、会計を済ませる。
「トロいなあ」
吐き捨てるように言い、男が背を向けた。
「死ね。殺すぞ。クソが」
椎名は呟いた。世界的な感染症拡大のせいでマスクの着用が日常化して早一年、数少ない利点のうちの一つが、営業中に独り言を言っても、誰にも気付かれないことだ。
「カリカリしてましたね、さっきのお客さん」
隣のレジの対応を終えたグエンが、労わるような声で言ってきた。
「老害ってよう言うけど、中年のおっさんが一番有害っすよ。十六のガキ相手に、ええ歳こいた大人が偉そうに。最初から、予約してたケーキください、って言えよ、ホンマ」
「日本のお客さん、僕には優しいです。でも、日本人の店員さんには厳しい」
事実だった。一目で外国人と分かるグエンに対して、露骨に人種差別的な態度をとる客も稀にいるが、大半の客は淡々と接するか、妙に馴れ馴れしく優しく接する。
日本はいい国、日本人はいい奴。外国人にそう思われたいのだろう。別に構わないが、一方で日本人の店員にばかりハイクオリティな接客を要求されると、苛立ちも募る。
「グエンさんが羨ましいっすよ」
「でも、時々悲しい。子供に優しくするみたいな、対等に扱われてない感じがします」
グエンが嘆息し、目を伏せた。
「ベトナムって、子供の日、あるんですか」
「ありますよ。六月一日。日本のハロウィンみたいに、派手にお祝いします」
「へえ。まあ、日本のハロウィンで盛り上がってんのは、一部の奴だけですけどね」
「そうなんですか。楽しみにしてますよ」
「彼女さんと一緒に、コスプレしたり?」
グエンがはにかんだ。
「いいかもしれない。シーナさんは?」
「いやあ、彼女いないんで」
前腕を目許に当てて、泣く真似をした。おどけたつもりだったが、ため息がこぼれた。
「ごめんなさい」
お悔やみの言葉を述べるときのトーンで言い、そそくさと品出しに向かってしまった。
椎名は肩を竦め、カウンターフーズの扉の前に立った。客側からは見えないが、扉の部分が鏡になっている。指で髪を軽く整えた。
結構、イケメンだ。重ための奥二重だが目は大きいし、眉の頭から真っ直ぐ鼻筋が通っている。唇が薄いのがコンプレックスだったが、クラスの女子がクールだと言っているのを耳にして以来、むしろ気に入っている。流行のセンター分けも、我ながら似合っている。
身長は一六七センチしかないが、ブルーノ・マーズだって一六五センチしかないのに、オーラたっぷりで格好良い。同年代はアイドルやJ−POP、J−ROCKを聴いている連中ばかりで、ブルーノ・マーズの良さを語れる相手がいないのはつまらないが、優越感もある。小学生のときにCMで流れているのを聴いて以来、大ファンだ。
彼女くらい、いたっていいはずだ。というか、いたのだ。それもこれも全部、このクソなパンデミックのせいだ。
抑圧し続けている鬱屈が頭をもたげ、鏡の前を離れた。折しも、制服姿の高校生らしきカップルが入店してきた。
「いらっしゃいませー!」
やけっぱちのような大声を張り上げると、カップルが躰をびくつかせて驚いた。それから顔を見合わせ、くすくすと笑い始めた。
マスクの下で、下唇を嚙み締める。強く、鈍い痛みが走った。
2
「俺のミスは逐一指導してくるくせに、自分が同じようなミスしたらなあなあで済ませんの、ホンマクソやわ」
バイト先の先輩に毒づきながら、家路を辿る。すっかり唾臭くなったマスクは、退勤と同時に外している。
いつの間にか、独り言が癖になってしまっていた。バッグを担ぎ直し、ワイヤレスイヤフォンをつけてブルーノ・マーズの「Runaway Baby」を流す。五回目のリピート再生に差し掛かった頃、公園に到着した。
再生を「Talking To The Moon」に切り替える。しっとりとした失恋ソングだ。この曲を延々と聴きながら、人のいない夜の公園でバスケをするのが好きだ。感傷に浸れる。悲劇の主人公になれる。
バッグをベンチに置き、バスケットボールとシューズを取り出した。
エア ジョーダン 5。
絶大な人気を誇るシューズだ。新品で、三万円以上する。高校の入学祝いに父親から贈られたが、汚したくなかったため一度も部活動中に履くことはなく、部屋に飾っていた。
退部後、夜に一人でバスケをする時間にだけ、履くようになった。そうすれば、父親のことも、自分の置かれた境遇も、許せるような気がした。
ドリブルしながら、フリースローラインまで向かう。足を肩幅に開き、膝を軽く曲げて下半身を落とす。右脚を前に出し、ボールを胸の前で持った。全身をリラックスさせ、地面に二度ボールをついてから、優しく抛る。
ボールが弧を描いている間、右手はリングに向かって、真っ直ぐ伸ばしたままだ。
スパッ。
イヤフォン越しでも、ボールが網を揺らす音が聞こえた。リングやボードに当たることなく網に吸い込まれたときにだけ、この心地好い響きを耳にすることができる。
何本連続で成功できるか。いつも最初はそんなことを考えながら打ち始めるが、いつの間にか時間を忘れ、繰り返し無心でシュートを放っている自分に気付く。
Tシャツが汗で躰に張り付いてきた。自動販売機で買ったコーラを一気飲みし、大きくゲップしてから、ゴールリングを見据えた。
ボールを地面に置き、駆け出す。ゴール手前で踏み込み、跳んだ。目一杯、手を伸ばす。
虚しく空を切り、着地して数歩よろけた。
バスケをするには不利な身長だが、そんな自分でも活躍できるポイントガードとして、小学生の頃から精一杯頑張ってきた。強豪校ではないが、一年生の時点でレギュラーもあり得るところまで評価された。
しかし、世界的な感染症拡大を受けて、部活動を始めとした学校生活は様々な制限を受け、インターハイの開催は中止された。リベンジを誓ったウィンターカップでは、複数の部員の感染が発覚し、出場辞退を迫られた。
不戦敗。
こんなにも悔しく、虚しいことはない。
─お前らには、来年があるやん。次のインターハイでかましたれ。
泣きじゃくりながらも強がって笑う三年生の言葉に、涙を堪えてリベンジを誓った。
だが、椎名が二ヶ月後のインターハイ予選に出場することは、もうない。
ため息を吐き、大の字になって横たわる。気持ちが鎮まるまで、瞼を閉じた。落ち着いてから目を開け、ゴールリングをぼんやりと見上げる。
中学生のとき、YouTubeで一六五センチのアメリカ人選手が華麗なダンクシュートを決める映像を観た。それ以来、自分も成功させたいという野望を秘かに抱いている。
イヤフォンからは、失恋ソングが流れ続けている。
マンションの階段を上り、三〇三号室の鍵を開けた。右手にある和室の電気は、既に消えている。達樹はもう、寝たみたいだ。
リビングからは、映画の音が漏れ聞こえてきていた。そのまま浴室に直行し、汗を流してからリビングに向かう。顔を合わせるのは億劫だが、喉が渇いてしまった。
父親は、ソファで鼾をかいて寝ていた。テーブルの上に、空になった焼酎のペットボトルが倒れている。テレビ画面の中では、砦のような場所で血みどろの銃撃戦が繰り広げられていた。リモコンを手に取り、再生を停止する。地上波のデジタル放送に切り替えた。
深夜の人気バラエティ番組にチャンネルを合わせ、冷蔵庫からお茶を取り出した。ソファから離れた椅子に、腰を下ろす。
マスクも着けずに密集した出演者達が、最高月収の話で盛り上がっている。売り出し中の若手芸人が、先月の収入は六十万円だったと言わされていた。売れっ子の司会者が、稼いでるねえと余裕綽々の態度で笑っていた。
「帰ってたんか」
いきなり声を掛けられて驚きながらも、反射的にリモコンでテレビの電源を消していた。
「今、帰ったとこ」
「そうか。父ちゃんも、今起きたとこや」
まだ、酔いは醒めていないらしい。眼窩の奥で、光が鈍く沈んでいる。
「えらい、遅かったな」
「出勤予定の人が、体調不良でいきなり休んで。二時間だけ残ってくれへんかって」
「緊急事態宣言出てんのに、コンビニは大変やな」
「あれ、今って宣言出てたっけ? もう、緊急事態感なさ過ぎて、分からへんわ」
父親が痰の絡んだ声で笑った。不快感が背筋を這い上ってくる。
「遅なるなら、連絡せえよ。心配するやろ」
「してへんやん。寝てばっかりで」
硬い声で言うと、気まずそうに顔を伏せた。
「公園で、バスケしてきたんか」
鼓動が跳ね上がった。冷静を装い、曖昧に頷く。知られていたとは、思いもしなかった。
居心地の悪い沈黙が流れた。寝るわ。そう口にして腰を浮かせようとしたが、その前に、父親が口を開いた。
「お前にばっかり、辛い思いさせてるよな」
語尾が掠れていた。目を合わそうとはせず、虚空を見つめている。
「ホンマに、悪いと思ってる。父ちゃんが、不甲斐ないばっかりに。申し訳ない」
胸が詰まった。熱い塊が、喉の奥から込み上げてくる。
「ロスジェネ世代いうて、和彦は分かるか」
答えあぐねていると、構わず話し始めた。端から、返答は期待していないらしい。
「父ちゃんの世代は、就職氷河期やった。せっかく大学出たのに、就職できひん。そんな奴らがゴロゴロおった。でも俺は、どうにか運良く、何年かしてあの会社に入れた訳や。コツコツ真面目に働いて、お前らも生まれて。大した稼ぎやないから、母ちゃんもパートに出てくれてな。家事に育児に仕事。ナンボ俺も手伝ってたいうたかて、やっぱり母ちゃんの負担の方が大きかったやろからな。俺のせいで、早死にさせてもうたんかもしれん」
母親は五年前に、くも膜下出血で他界している。
「別に関係ないやろ、それは」
語気荒く言った。これ以上、聞きたくない。だが父親は、堰を切ったように続ける。
「ちょっとタチの悪い風邪が流行ったからって、ここまで大騒ぎするようなこと違うやろ。なあ? 俺達ロスジェネは、ずっと見捨てられてきた。俺はまだ運よく何とかなってた方やけど、どうにもならんかった奴なんかナンボでもおる。経済的な弱者を切り捨てて、平和で豊かな国やって言い続けてきたんやから、病人かて切り捨てたらええやないか」
顔を上げ、真っ直ぐ視線を合わせてきた。酒で、目が濁っている。
父親が勤めていた建設関係の会社は、感染症流行による不況の煽りを受けて、一月に倒産した。五月下旬になっても再就職先は見つからず、知り合いのツテを頼りに、派遣スタッフのような形で日々働いている。
弟の達樹は、まだ小学五年生だ。長男として、家計を少しでも支えるために、バスケ部を辞めてアルバイト漬けの日々を送る道を選んだ。
「オトン。もう、ええから」
感情を押し殺して言った。
「よくない。何にもよくない。お前からバスケっちゅう楽しみを、青春を奪った。ホンマに悪いと思ってる。情けないわ」
声に、苦渋の色が滲んでいた。頭の中で、何かがはち切れた。
「グチグチグチグチ、鬱陶しいんじゃ」
立ち上がり、大声を張り上げる。
「別にええ、言うてるやろ! ああ、そりゃバスケしたいよ。気ィ遣ってんのか知らんけど、バスケ部の仲間やったみんなにも距離置かれるし、今更新しい友達もできひん。彼女にもフラれたよ、今サッカー部の奴と付き合ってるらしいわ。毎日毎日、クソ鬱陶しい客の相手して、たかが知れた金稼いで、それを達樹は何の苦労もせんとお菓子ばっか買うてさ。けど、別にええよ。俺が全部我慢すれば済む話、犠牲になれば済む話やろ!」
怒鳴り散らすうち、怒りが増幅してきた。絶句する父親を見下ろし、こめかみが痛んだ。
「今更、惨めったらしくごちゃごちゃ言うなよ。あのとき、止めてくれたらよかったやんけ。金ならなんとかする、それが父親の役目やから、バスケは続けたらええって。そうせえへんかった以上、今更謝ってくんなよ。どうにもならん。惨めで、鬱陶しいだけや」
溜め込んでいた鬱憤を吐き出し、父親を惨めだと罵倒するのは、破滅的な快感があった。
もう、これまでの親子関係には戻れない。頭の片隅で、感覚的に悟った。
知るか。先に酔うて絡んできたのは、そっちや。こっちはずっと、我慢し続けてきた。
リビングを飛び出すと、達樹が目を擦りながら廊下に立ち、トイレに入ろうとしていた。
「あ、おかえり。なんか騒がしかったけど」
暢気な顔で笑っている。パジャマの胸倉を摑んで引き寄せ、顔の前で怒鳴った。
「邪魔じゃ!」
瞬く間に、泣き顔に変わった。
達樹を突き飛ばし、玄関を出た。頰を刺す夜気の感触が心地好い。胸がすく思いがする。嫌悪感で、押し潰されそうだ。
手ぶらで出てきたが、自然と足は公園のバスケットコートに向いていた。
颯然と風が吹いた。コートの周りを取り囲む木々が、音を立てて揺れた。枝葉の隙間は、濃い闇に塗り潰されている。
センターサークルの中に立ち、鼻から大きく息を吸い込んだ。真夜中の匂いがした。
胡坐を搔き、スマートフォンを取り出す。少しでも時間があれば、つい触ってしまう。
退部してから作った、ツイッターのアカウントを開いた。ジョーダンというハンドルネームで、日々の愚痴を連ねている。本名で使っていたインスタグラムのアカウントは、退部後しばらくして削除した。
ツイッター上のトレンドの話題を見て、苦笑交じりのため息が洩れた。
国民に外出や活動の自粛を呼び掛けてきた日本医師会の会長が、自身が後援会会長を務める与党議員の政治資金パーティーに、参加していたという。参加者は、百人規模だそうだ。
死にたい。
軽い気持ちで、ツイートしてみた。途端に、重たい実感を伴って、胸に迫ってきた。
スマートフォンから、顔を上げた。バスケットゴールの真っ赤なリングが、仄明るい外燈の光を照り返している。
遥か高みで、満月が煌々と輝いていた。
(続きは本誌でお楽しみください。)