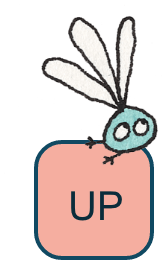1
桜島が噴火したせいで、僕のペニスは勃たなくなった。もとより、あの子と出会うまでは使う見込みのない機能だったから、別にいいのだけど。
連日、降灰の片づけに大忙しだった。
種子島宇宙ステーションからは、週に二回、月行きのクルーズ・ロケットが出ている。次の出発まで幸い三日あるが、総面積三百万平方メートルに及ぶ出発ターミナルの清掃が間に合うか。かなりギリギリだと思う。
夜明け前から小型のカートに乗り込んで、灰を吸引してまわる。遠くに見える海岸線がうすく瑠璃色に輝き、空は茜色に染まっていく。細切れの雲が薄墨のように黒ずんで見えた。清潔な冬の朝だ。数時間もすれば寒さは少し、やわらぐだろう。
誰もいないステーションでの静かな掃除の時間が好きだった。口にするとみんな笑うのだけど、この仕事だけが僕の生きがいだし、存在意義だ。
太陽が顔を出す頃には、リー駅長が出勤してきた。僕はちょうど事務所にバッテリーを替えにきたところだった。
リー駅長は僕の顔を見て、早口の中国語で何か言った。その声とかぶさるように、胸元につけた自動翻訳機から、滑らかな日本語が聞こえてきた。
「鮫島君、ちょっと、鮫島君」
大げさに手招きして、「あれ、見てよ。受信アンテナのまわり。あっちも灰でやられてるでしょ」と壁にかかったモニターの一つを指さす。
天文観測衛星と対になっている大型アンテナだ。確かにうっすらと灰をかぶっているのが見える。
「あれもきちんと掃除しといてね。前にも言ったと思うけど、今年の夏には、ハレー彗星が接近するんだよ。一九八六年以来、七十五・三二年ぶり! 分かる? 分かるよね。君、清掃員のわりに勉強熱心だもんね」
「ええ、父が一時期、僕の教育に凝っていたものですから」
「うんうん、それはいいんだけどさ。問題は彗星だよ。宇宙望遠鏡が写真を撮ることになってるの。それをなるはやで全世界に公開したいの。世界各地、色んなところで万全の準備が進んでるはず。それなのにうちときたら! 灰をかぶってる場合じゃないのよ。シンデレラじゃないんだから」
リー駅長は早口でまくし立てると、両手で自分の腰をパンパンと叩いて「よし!」と言いながら、事務所を出ていった。
火山灰の清掃はかなり大変だった。宇宙事業は好況のはずなのに、人件費の高騰のせいで他のみんなはクビになった。僕だけで宇宙ステーションの面倒を見るのは正直荷が重い。だけど父さんは、どんどん仕事を受けてくる。最近は市街地の清掃業務にまで手を出しているほどだ。
月経由の大型クルーズ・ロケットが発着するようになって、種子島も一気に観光地化が進んだ。街中にはゴミがあふれ、ヘゴの原生林は枯れるわ、ニホンイシガメは姿を消すわの大惨事に至る。焦った西之表市は国から補助金を獲得し、「街中クリーン事業」なるものを立ち上げた。その選定事業者として父さんはいの一番に手を上げたのだった。いつも酔っぱらっているくせに、こういうときだけ勘が冴えて動きが早い。
「お前の教育に一体いくらかけたと思ってるんだ」
父さんは毎晩、ねちねちと言い募る。僕が生まれたのは、技術特異点が発生した二〇四四年で、世間は好景気に沸いていた。父さんも当時は羽振りがよかった。三十人超の研究員を抱える研究所で、数百億円単位の予算をもらった研究をしていたという。
そこから十七年、世間の景気はどんどん良くなっているのだが、父さんの事業だけは傾いている。ヤマッケを出して設備投資しすぎたのだ。
「できうる限り最高の技術を搭載する」というのが父さんの信条だった。けれども世の中にはオーバースペックという言葉がある。例えば清掃員の僕がいかに高い知性を誇っていようとも、誰も得をしない。
結局、それなりのものをそれなりの予算で開発している他社に、売上では大幅な差をつけられている。経費ばかりがかさみ、黒字に転じる目もなく、メインバンクからも大株主からも要注意監査対象としてにらまれている。
そのせいで僕は昼も夜もなく働き続けることになった。日に五時間も休めればいいほうだ。関節の動きが悪いせいか、身体が悲鳴をあげるようにボキボキと音を立てる。動こうと思っても、すぐに動き出せず、よっこらしょっというタメがいる。おじいちゃんになったみたいだ。そんななかで桜島が噴火し、周囲百キロ圏内に灰が舞い散った。追加で掃除をしなくちゃいけない。身体の不調もここに極まれり、僕の大事な下半身にすら不調が現れるようになったわけだ。
けれども僕は黙々と掃除をした。ステーションの清掃に一区切りつけると、市街地に出た。
目抜き通りには自然石灰岩を使った南国風の低層建物がずらりと並んでいる。出店の暖簾は地元で織ったリネンに手刺繡が施されている。昔ながらの浴衣を着た外国人たちが、歩き慣れない草履をはいて、ぺったんぺったんと音を立てながら騒がしく行き来する。
富裕層向けの一大リゾート地として、一世紀以上前に存在したかも分からないノスタルジーを作り出そうと、行政は必死なのだ。
けれども和紙製のコーヒーカップは道の脇にごろごろ転がっているし、最近急にブームになった葉巻の吸い殻すら落ちている。旧式の健康悪化嗜好品に高い金を払うなんて、金持ちの考えることは分からない。
ノズルで吸い込むには大きいゴミが多いから、右手のゴミバサミでつまんで左手のゴミ袋に入れていく。あまりにも原始的で嫌になるのだが、現状残念ながら、これ以上の清掃方法は発明されていない。
「父さんにもう少し商才があれば」
ため息をつきながら、脇にそびえ立つ近代的なビルを見上げた。
ディープ・スペースという会社の種子島分室オフィスである。
景観規制を一切無視したつくりで、むき出しの鉄筋コンクリートの柱に、まぶしいほどピカピカに磨かれたガラスが張られている。行政からは指導が入ったり、勧告が出たり、果てには罰金まで科されているが、彼らは社屋の外装を変えようとしなかった。
「手ごろな材料で機能的なプロダクトを作る。これはわれわれディープ・スペース社のミッションです。そのミッション・コンセプトに沿って社屋は作られています。罰金を科せられたとしても譲るわけにはいきません」
というのが社長のローガン・ブラウンの主張だった。
父さんに言わせると、「そこそこの材料でそこそこのものを作って、大量に売りたいだけ。それを綺麗な言葉で言い換えやがって」となる。
消費者に求められていない最高技術の搭載にこだわる父と、手ごろなモノ作りをモットーとするディープ・スペース社とでは分かりあえるはずがない。
周囲が薄暗くなってくると、街中の提灯に火がともり始める。何度見ても美しい光景だ。鬼灯の果実が一斉に実るように、街道の両脇にオレンジ色の瞬きが揺れる。その間をすりぬけるように、小型の自動配達機が軽快なプロペラ音を響かせながら飛んでいく。
空を見上げれば、ぞっとするほど荘厳な星が見える。すぐに分かるのは大きなオリオン座。おおいぬ座、こいぬ座。ベテルギウスとシリウス、プロキオンをつなぐと冬の大三角だ。さらにアルデバラン、カペラ、ポルックス、リゲルが連なって、冬のダイヤモンドが輝く。空を見上げているあいだだけは、現実を忘れられる。
僕はしばし固まって空を見ていた。
そのとき、何光年も先の宙空で横に一筋、鮮烈な光が走った。
「あっ! 流れ星!」思わず声が漏れた。
願い事なんていう情緒的な習慣はない。遠くから、塾帰りと思われる学生たちの「おおっ」とどよめく声が聞こえてきた。本当は彼らみたいに学校に行って勉強したかった。けれど願っても仕方ないことだ。
「おい、どうなってるんだ」
「ちょっと、臭いよ」
「何これ? 人?」
通りの向こうを右に折れたあたりから、騒ぎ声がした。甚兵衛姿の大柄な男が角を曲がり、こちらに走ってくる。
「ちょっとあんた! あんた、あっ、ちょうど良かった」
奥の通りで《星影》というバーを営んでいる男だ。
「あっちに変なものが落ちてるんだ。掃除してくれ」
男に連れられるまま、角を曲がって進むと、細い路地の中央に一人の少女が倒れていた。棺に入った聖女のように腹の上で両手を組んで、眠るようにまぶたを閉じている。
「何なの、変な格好」
通行人の女が鼻をつまみながら言う。「しかも臭いし」
確かに、倒れている少女は古めかしい洋装をしていた。ロココ調のドレスとでもいうべきか。艶のある桃色の絹織物にレースとビーズで細かい刺繡が施されている。コルセットとパニエを身に着けているせいか、腰から下は滑稽なほど左右に大きく広がっている。前開きガウンの間、胸元には薔薇の造花がついた胸当てがのぞいている。肘の部分にも同様に薔薇の造花がついていて、さらに薔薇の葉に見立てたらしい緑色のリボンまでバランスよく配置されていた。
リボンの先からは透けるように白く細い腕が伸びている。
顔も死人のように青白い。カールのかかった金髪が形よく盛られた胸の上に落ちている。よく見ると、胸はわずかに上下していた。
「生きてますね」
僕が言うと、《星影》の店主が大きな手を少女の口の上にかざして応えた。「確かに……息がある。けど、すっげえ臭い。なあ、あんた、清掃員なんだし、臭いは大丈夫だろ。この子、どうにかしてよ。コスプレ大会のすえ酔っぱらったのか、何なのか知らないけど、ここで寝られると営業妨害なんだよね」
店主は目の前にある自分のバーの看板を指さした。騒ぎに気づいた通行人たちが足をとめ、輪になるように少女を取り囲んでいる。見ているわりに近づいて抱き起こそうとしないのは、店主が言うように彼女の臭いが原因なのだろう。
「どうにかしてと言われましても……僕はただのゴミ拾いですよ。一応、ゴミってのは『一般人をして不快感を催させる有形物』と倫理委員会が定義してるんです。この子は人間だし、有形物ってことはないでしょう」
融通が利かないと怒られるのは分かっている。だが職権以上の仕事をしたら、後で面倒なことになりかねない。
「形があるんだから、この子も『有形物』ってことでいいだろ。なあ?」
店主は周囲の見物人に同意を求める。
「えー」「そうだ」「どうかな」「いいんじゃない」とそれぞれが勝手なことを口にする。
次第に野次馬すら減ってきた。新しく通りがかる人も「何かのパフォーマンスかな」と言うだけで気にとめない。
「なんだよもう」店主が頭を抱えた。「このあたりは服装規制で和服を着なくちゃいけないってのに、この女、変な格好しやがって」
「これはローブ・ア・ラ・フランセーズ。十八世紀に流行したフランス貴族の女性服ですね」
僕が言うと、店主は頭をかいた。
「さすがに物知りだな。でもお前はゴミ拾いだろ。さっさとこの子を拾っていけ」
あごで指示をすると、店主は店の中に戻ってしまった。
路地には僕と、見ず知らずの少女だけが残された。訳もなく天をあおぐ。そこには先ほどと寸分も変わらないような眩い星空が広がっていた。僕はそのまま数秒固まっていたが、意を決して視線を戻し、少女の肩に触れた。
ゆすってみる。反応はない。「あのう」と声をかける。やはり反応がない。
「あのっ! ちょっと!」声を張り上げながら、強くゆすった。
すると少女は驚いたように、びくっと身体を震わせた。ゆっくりと目が開く。エメラルドグリーンの美しい瞳が、僕をじっと見つめた。
「アン?」聞きなれない発音だった。「ブゥエキ? ウソモヌ?」
フランス語のような気がするのだが、正確なことは分からない。僕はとっさにフランス語で「ちょっと待ってください」と言ってから、自動翻訳機を取り出し、彼女の胸元につけた。
彼女は一瞬びくりとして、身体を硬くした。目を見開いて警戒心をあらわにしている。まもなく自動翻訳機が起動して「位置情報取得。日本。言語互換条約第十六条に基づき、日本語訳モードで作動します」と音声ガイダンスが流れた。
少女は固まったまま、自動翻訳機をしげしげと見た。
「クェセクセ? エセマジク?」
つぶやく声を自動翻訳機が拾い、「これは何? 魔術なの?」と日本語音声が流れた。
少女は頰を紅潮させて、自動翻訳機を見つめている。
「何ということでしょう。これは何の魔術なの? あなたは……いや、そんなはずはない。いくらわたくしの脳が女性らしく柔らかく湿っていたとしても、自然哲学に反する事柄は受けつけませんの」
僕は混乱した。
自動翻訳機の原語表示には「フランス語・古語」と出ている。
少女は周囲を見渡して、「ここは一体……ああ、そうだ、わたくしは。わたくしは……」と涙ぐみ始める。
「アカデミーの会長に直談判しようとパリに出かけたのでした。それで誰かに背中を押されたと思ったら、乗合馬車に轢かれて……」
ガウンのひだに隠していたらしい巾着袋からレースの扇子を取り出して顔を隠した。
「なんたること。なんたる無念。しかしながら、ここは彼の神との約束の地なのでしょうか。わたくしは決して褒められた信仰者ではなかったのですが、永遠の命を得られたのでしょうか。いや、いけない。わたくし、どうしても霊魂なんてもの、受けつけませんの」
少女は一人でとうとうと話し続ける。周囲の者は当然自分の話を聞くべきだと信じてやまないような、堂々とした態度である。だが通行人たちはポカンとした表情を浮かべて一瞬足をとめるものの、すぐに通り過ぎていく。
「しかしながら、ああ、肉体がある。ということは、霊魂の復活ではないのでしょうか」
少女は両手で地面のアスファルトをさする。「この土はどうしてこんなに硬いのでしょうか。テッラの元素がこれほどまでに純粋に凝縮することがあるのかしら。強い火にあてて熱素を徹底的にあぶりだせばよいのかしら。ああ、あそこに水がある!」
少女はバー《星屑》前の側溝を指さして、四つん這いになり、側溝の隙間から下をのぞき込んだ。
「テッラでアクアを挟み込んでいる。ああ神様、自然の原理に逆らう私たち人間をお許しください。そう人間はいやしくも……あれ、つまり、人間がいる。身体がある。そして─」
少女は四つん這いの姿勢のまま、首をぐっと曲げて空を見上げた。
「北斗七星がある……おうし座、ふたご座……」
口をぽかんとあけてしばし固まっていたが、すっと真剣な顔になって言った。
「つまり、古代ギリシャの神話が存在する土地。空気は……涼しい、いや寒いくらい。冬だわ。冬にこの星座が見える。方角も……矛盾はない」
少女はカッと目を見開いて、僕に向きあった。
「ここは地球なのね。ねえ、そうでしょう」
僕はうなずいた。「そうだけど」
「そしてわたくしは、生きている……のね」
「そのようですね」
「あなたは? 見慣れない風貌をしているけど。この地域では普通なのかしら。ああ、あそこの路地にもあなたみたいなのがいる。そういうものなのでしょうか。それにしても、どうして私はここにいるのでしょうか。どうも言葉が通じるのに時間がかかるようですし」
少女は胸元につけた自動翻訳機をつまんで引っ張った。
「そんなに乱暴に触らないで」僕は慌てて声をかけた。「繊細な機械なんだ」
「機械?」少女が目を丸くする。エメラルドグリーンの瞳が星の光をうけて輝いた。「懐中時計のようなものかしら? かなり小さいようだし、仕組みは分かりませんけど。この地には腕の良い職人がいるようね」
少女はすっくと立ちあがってドレスの裾の曲がりを直し、まっすぐ僕を見て言った。
「わたくしの名はマリー・ドゥ・ランクル。ラブール地方のピエール・ドゥ・ランクル六世の三女です。こちらの地方のしかるべき方にご挨拶を差し上げたいのですが、案内してくださいますね?」
(続きは本誌でお楽しみください。)