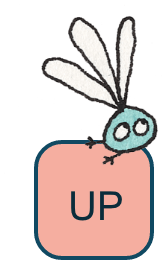ぬばたま
一
はじめて取った男の手は、思ったよりやわらかく、あたたかいものだった。織江がその感触をたしかめるように力を籠めると、相手も応える体で握りかえしてくる。自分でもはっきり聞こえるくらいに鼓動が高まり、下腹のあたりがきゅっと窄まるのが分かった。
だれかに見られていないか不安になったが、あたりは身動きするのもままならぬほどの人出である。そのうえ、新月に近いかぼそい月夜だから、気に留める者がいようとは思われなかった。
城下のはずれに祀られている荒神さまの祭礼は梅雨入りまえと決まっているが、今年は思いのほか雨のはじまりが早く、きのうおとといと続けて降った。祭礼当日の今日は朝からつよい陽光にめぐまれ、日向ではすっかり土も乾いて雨の名残りも見られない。が、大気のなかには、いまだ零れるような湿り気がふくまれ、すこし動くだけでも首すじに汗が滲みだしてきた。
馬廻りをつとめる高梨家は百石をたまわる家柄で、織江はその末娘だった。母ははやくに亡くしたが、父の作兵衛は先年隠居し、兄の敬太郎が跡を継いでいる。姉ふたりはすでに嫁ぎ、残るは織江だけだった。はっきりと聞かされてはいないが、もう十七だから、そろそろ話があるはずと察している。
荒神さまの祭礼に行きたい、といったのは、そうした心もちとも関わりがあるだろう。城下で催される祭りはいくつかあるものの、荒神社はいくぶん遠い場所だから見物にいったことはなかった。嫁入りに否などいうつもりはないが、それまでにひとつくらいは気ままを通してみたい、という思いが頭をもたげたのかもしれない。
とはいえ、すんなり許されたわけではなかった。
「なにかとよくない噂も聞くからな」
兄が渋い顔をしているところに作兵衛が通りかかり、
「新蔵をつけてやれば、大事なかろう」
口添えしてくれたおかげで、ようやく行けることになったのである。もっとも、じぶんにあまい父が加勢してくれるのは織りこみずみで、わざと作兵衛に聞こえるようなところで兄を呼びとめたのだった。
新蔵というのは若党のひとりで、自分とそう齢も変わらない。もともと百姓の出だと聞いているが、引き締まった体軀をした若者で、勤めぶりもまめまめしかったから、父や兄に気に入られ、若党に取り立てられた。織江は新蔵の堅苦しさが苦手だったが、ここが落としどころだと分かっていたから、嫌な顔を見せたりはしない。べつの者にしてくれといっても通らないに決まっていた。
薄暮の気配が漂いはじめるころになって、織江と新蔵は屋敷を出た。中級家臣の屋敷が建ち並ぶ一郭を通ってゆくと、何人か同じ方へ足を向ける武家の男女が目に留まる。それほど数は多くないが、やはり荒神社へおもむくものと思われた。自分だけではなかったのだと、安堵したような気もちが胸を浸す。虞れを抱いていないわけではなかった。
荒神さまの祭礼は、若い男女が気に入った相手を見初める場だという噂があって、百姓や町人たちはそのまま軀をかさねたりもするのだと、娘たちのあいだでまことしやかに囁かれていた。まさかそんなことをするつもりはないが、どこか興をおぼえたのも確かである。
「おまえは、どこか危なかしい」
時おり兄に窘められるのも、こうしたところを指しているのだろう。むろん、そんな話をした覚えはないが、そこは十歳離れていても、兄ならでは伝わるものがあるのかもしれなかった。
一刻以上も歩んでいるあいだ、新蔵はろくに話もしない。ことばの多い男も嫌だが、寡黙すぎるというのも扱いに困った。畦道を通る際に、
「暗くなって参りましたから、お気をつけて」
といったのがいちばん長い話しかけで、あとはこちらが、
「このあたりは蛙の声がうるさいのね」
とか、
「雨があがったのはよかったけど、蒸し暑くて仕方ないわ」
などと半ばひとりごとめかして告げるのへ、さようですな、くらいの応えをかえすだけである。気疲れと腹立たしさの入りまじった心もちを持て余していた。
荒神社へ辿りついたときにはすでに日も落ち、燃えるような夕映えの名残りがあたりに漂っている。朱と黒の混じり合った暮色はなにかが焦げてでもいるようで、わけもなく軀の奥を騒がせた。
社のまわりは丈の高い杉木立ちに囲まれているが、そこへ分け入るまえから、太鼓や囃子が耳朶を震わせている。その音に煽られるごとく、胸がとめどなく高鳴るのを覚えた。新蔵も来るのは初めてらしいが、招くような調べが絶え間なく鳴り渡っているのだから、迷いようもない。町人と武家とを問わず、やはり同じように社へ向かう人影が前後に見受けられた。
「こんなところで珍しいな」
追い抜きざま声をかけられ、とっさに背すじが竦んだ。数人の若侍が連れ立って歩いており、なかの一人が織江に目を留めたのである。ほの暗い闇を透かしてうかがうと、細面のととのった顔立ちに見覚えがあった。
三軒さきに屋敷をかまえる堀田十太夫の嫡男・孫四郎である。堀田家はおなじ馬廻りの家柄で、齢もひとつ上に過ぎないから、幼いころはよくいっしょに遊んだが、さすがに最近はそうしたこともない。顔を見るのもずいぶん久しぶりのような気がした。
少しくらいは話してみたい気もしたが、仲間に急かされた孫四郎は、
「では、また後で」
と言い残して足早に奥へ向かっていった。名残り惜しげに見えなくもなかったが、ほんとうのところは分かるわけもない。軀の奥がかすかに疼いたが、その痛みはどこか甘やかな気配を孕んでもいた。
杉木立ちを抜けると、ひといきに空が広くなる。細い月のかかった溟い夜空ではあったが、それでも吸いこむ息がにわかに深くなると分かった。
社そのものは四、五人も入ればいっぱいになるほどの大きさでしかないが、百人近いと思われるひとが、そのまわりを取り巻いている。階の下に据えられたふたつの篝火が、夜の底でうごめく影を照らし出していた。囃子に合わせて踊ってみせる者もいれば、あたりを所在なげに歩き回っている者もいる。火影を映しているのか、どの顔もこころもち赤らんで見えた。
新蔵も息を吞んで、あちこち目をさ迷わせている。いつも謹直なさまを崩さぬ男がほころびを見せたようで、物珍しさに駆られて瞳が吸い寄せられた。しっかりと顎の張った面ざしが火明かりを浴び、燃え立つように浮き上がっている。
「すこし、あたりを回ってみたいの」
織江がいって歩き出すと、かしこまりましたとつぶやいて、後に付いてくる。放っておいてくれるとは思っていないが、やはり煩わしくはあった。
まずは社へ向かって足をすすめたが、近づくほどにひとの垣根が厚さを増してくる。何度か肩や肱をぶつけているうち億劫になり、爪先の向きをかえた。
「お嬢さま」
寄り添うようにしたがっていた新蔵とのあいだが人波でさえぎられ、若党が声を張って呼びかける。案じげなその響きを耳にした途端、すこし困らせてやろうという思いが湧いた。
男の手が差し出されたのは、そのときである。長い指を見つめて立ちすくんでいると、
「あいつを巻きたいんだろう」
堀田孫四郎がいたずらっぽく笑いながら、背後に目を飛ばした。新蔵とのあいだはすでに一、二間も離れている。見知らぬ顔がつらなった人垣のむこうで、焦りに満ちた男の面が篝火に照らされていた。
つかのまおのれを咎めるような心もちが湧いたが、孫四郎は織江の手を取り、つよく引き寄せる。いくぶん体勢を崩したものの転ぶほどではなく、かえってのめるような足つきで男に近づいていった。
意外にやわらかい孫四郎の手を握ったまま、ひとの流れに任せて歩をすすめる。かさねた掌から男の温もりが流れこんでくるようだった。仲間とははぐれたのか、近くにそれらしき姿は見当たらない。
社を中心にした渦が、巨大な生きもののごとくうねっている。その波へ吞まれるようにして織江と孫四郎はあゆみつづけた。幾度か新蔵が気になり振り返ったが、か細い月明かりと揺らめく篝火に浮かび上がった群れはみな同じ顔のように思え、どこにいるのか見当もつかない。織江がよそへ目をやるたび、孫四郎の手にここちよい力が籠められ、若党の面ざしはしだいに薄れていった。
荒神社の裏手にまわると、篝火のつくる明るみはほぼ絶え、季節が変わったかと思えるほどの冷ややかさがあたりに満ちている。ひとの波もまばらとなり、織江はようやく息をついた。
目のまえに、くろぐろと巨大な塊がうずくまっている。そこだけ光が通らぬかのように、ひときわ濃い闇が立ちはだかっていた。しばらくはそれがなにか分からずにいたが、来たときに抜けてきたのと同じような杉木立ちだと気づく。つかのま、もとのところへ戻ったのかと思ったものの、むろんそのようなわけもない。恐ろしいような、どこか懐かしくもあるようなふしぎな心もちだった。
その闇へ吸い込まれるひとびとが目に留まる。男と女が組になり、手を取り合って木立ちの奥に入ってゆくのだった。垣間見ただけだから確とは分からぬが、そのなかには孫四郎の仲間もいくたりか混じっているように思える。来たときにはともなっていなかった女たちの手を取り、なにかに憑かれたふうな足どりで進んでいた。
軀がすくんで立ち止まりそうになる。それを察したらしく、孫四郎がつよく手を握りしめてきた。掌が汗ばんでいるのを知られたくなかったが、指先はひとりでに動き、絡むように男の手を摑んでいる。
どこか遠いところから、じぶんの名を呼ぶ声が聞こえる。織江はそれを振り払うようにして、杉木立ちのほうへ歩んでいった。
二
まわりから向けられる目が今までと異なるように感じはじめたのは、梅雨に入って数日経ったころである。雨のなか、茶の稽古に出かけるため屋敷を出ると、ちょうど通りかかった数人の若侍がこちらを見て、何ごとかささやき合った。供の女中も察するものがあったらしく、わけが分からぬままあるじの盾となる位置に立ち、若者たちの視線をさえぎろうとする。かえって無遠慮な笑声があがったが、雨でもあるし時刻も近づいていたから、足早に歩をすすめた。
師匠の宅にあがってからも違和感は消えなかった。おなじような家格の娘たちが三人いっしょに習っているから顔なじみといってよかったが、明らかにようすがおかしい。最初からなにか憚るごとき眼差しをあらわにし、織江がお点前のときも残りふたりで意味ありげに視線を交わしている。とうとう師匠から注意されてしまうほどだった。
稽古を終えたあとも、いつもなら途中までともに帰るのだが、こちらから声をかけるまえに、
「きょうは行くところがあって─」
ふたりして早々に立ち去ってゆく。脇の下からひやりとした汗が滲みだしてくるのをおぼえた。帰る道すがらも動悸が増し、足から下がじぶんのものでないように感じる。お付きの女中もことば少なとなり、不安げに面を伏せていた。
重い心もちを煽るように雨が募り、藍地の帷子は濡れて黒く染まった。ようやく屋敷へもどったときには、すっかり足先が冷えている。厨にまわって湯を沸かしてもらい、盥に張って足を浸した。
しばらくそうしていると、強張っていた軀がわずかながらゆるみ、息づかいが深くなる。顔をあげると、ちょうど厨に入ってきた新蔵と目が合った。
若党は黙礼だけして気まずげに瞳をそらし、いそいで白湯を吞むと身をひるがえす。そのまま傘もささずに戸外へ出ていった。
あの日、荒神社の裏手にある杉林へ踏み込んだ織江は、十歩も進まぬうち堀田孫四郎に抱きすくめられた。そのまま、幹に背中を押しつけられる。まったく予期していないわけではなかったが、男の匂いが鼻腔にせまった途端、急におそろしくなって身を縮めた。視界の隅ではおなじように抱き合ったり、横たわって蠢く男女が何組もうかがえる。
あらがっていると、孫四郎の腕にいっそう力がくわわる。苛立たしげに洩らした舌打ちが、耳もとでやけに大きく響いた。
「分かってて来たんじゃないのか」
むしろ途方に暮れたような声で孫四郎がつぶやく。織江はなんと応えてよいか分からず、いやいやをする童のごとく頭を振りつづけた。
かたわらから伸びた手が男の肩にかかったのは、そのときである。うわっと呻いてのけぞった孫四郎の体が引き剝がされると、全身から力が抜け、織江はそのまましゃがみこんだ。夜の風が、ことさらひえびえと吹きつけてくる。男と触れ合っていたあたりが汗みずくになっていた。
おそるおそる面をあげると、肩を大きく上下させた新蔵が闇のなかに立ちはだかっている。その眼差しは怒っているようでもあり、深い悲しみに浸されているようでもあった。
「帰りましょう」
新蔵が誰にともなく告げる。こちらに向けて手を差し伸べかけたものの、思い直した体でそのまま下ろした。そのことばへ導かれるようにして、のろのろと立ち上がる。腰から下の感覚がようやく戻ってきた。
「若党に意見される筋合いはないな」
いつの間にか孫四郎の仲間が幾人かあつまり、剣吞な眼差しをたたえてふたりを囲んでいる。新蔵は恐れる気配もなくこうべをめぐらし、男たちの面を見まわした。
「意見など」そのまま、平坦な口調でつぶやく。「お嬢さまをお連れするだけです」
甲高い音がとつぜん闇のなかに響き渡った。とっさに何が起きたのか分からなかったが、気がつくと、若侍のひとりが身を強張らせて呻き声を発している。新蔵の大きな手が男の腰に伸び、相手の拳ごと大刀の柄を握りしめていた。抜こうとするよりはやく抑え込んだということらしい。残った男たちが怒声を放ちながら腰のものに手を伸ばした。
「……心づよいお供というわけか」
孫四郎が仲間たちを留めるように右手をあげ、忌々しげにつぶやいた。
「まあ、帰るといい」織江に目を向け、木立ちの外へ顎をしゃくる。「次から、まぎらわしい真似はやめてほしいものだ」
そのことばをさえぎる体で新蔵が織江のまえに立ち、
「参りましょう」
低い声でささやいた。織江は声もなく顎を引くと、ゆっくりと踵をかえす。若党の背を追うようにして溟い木々のつらなりを抜けた。
ながい帰り道のあいだ、新蔵はひとことも声を洩らさなかった。いたわられている気は微塵もせぬが、といって責められているわけでもない。ひたすら、いたたまれぬような思いが胸を刺す。あるいは新蔵もおなじ心もちでいるのかもしれないと感じた。
屋敷の門前まで帰りついたとき、ひといきに、
「─手数をかけてしまいました」
といって頭を下げた。鬢のあたりを生ぬるい夜気が嬲ってゆく。
「いえ」
新蔵は当惑を滲ませた面もちで、ことば短かに応える。潜り戸へ手をかけるまえに、うかがうような口調で問うてきた。
「きょうのことは黙っていたほうがよろしいでしょうか」
「……もし、そうしてくれるなら」
消え入りそうな声で応えながらうつむいた。我ながら身勝手なことをいっていると羞じ入る気もちが身のうちをめぐる。承知しました、という男の声がはっきり聞き取れないほど耳の奥が鳴っていた。
あれから十日ほどが経っている。その間、新蔵とことばを交わしたことはなかった。たまさか今のように出くわすことはあったが、話しかけるでもなく、そのまま別れてゆくだけである。若党のほうから主家の娘に声をかけられるわけもないとはいえ、新蔵はあきらかに織江と向き合うことを避けているようだった。
─ひどい娘だと思われているのだ。
仕方ないと思いながらも、胃の腑が重くなる。身を任せるまでの気はなかったが、孫四郎に惹かれるものはあった。つかのま甘美なものを味わったのも事実である。そうした世界を垣間見たい心もちがあって荒神さまの社へ足をはこんだのだった。それは新蔵にも伝わっているだろう。
湯に浸しているうち、すこしずつ指のさきに血がめぐってきたようだった。盥から足を出すと、お付きの女中が拭おうとして布を差し出す。
「いいわ、じぶんで」
織江はこころ安げにいって手を伸ばした。女中は戸惑った面もちを浮かべたが、言われるまま布を渡してくる。受けとって、すっかり赤くなった足をくるんだ。
─それにしても……。
指のあいだに残った滴を丹念に拭き取りながら、今日のことを思いかえす。若侍や娘たちの眼差しは物見高いような恐れはばかるようなもので、いずれにせよ、いままでそうした目を向けられた覚えはなかった。
眼前に深い翳のごときものが立ち籠め、まといついてくる。織江は震える背すじを伸ばし、おもむろに立ち上がった。
(続きは本誌でお楽しみください。)