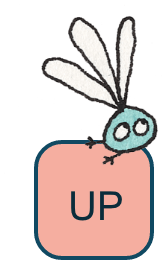*
「コラボしませんか?」
ビデオチャット越しに、私は提案した。
自分の声が緊張で震えているのがわかる。こんな状況じゃ無理もない。
会話の相手はアニメ絵のアバターだった。表情や身体の動きに合わせてリアルタイムにイラストが動いている。彼はいわゆるバーチャルユーチューバーだ。名前は猫崎ケンスケ。唯一無二の推しである。猫耳金髪の可愛い顔と、気怠そうな色気のある声のギャップがたまらない。チャンネルのフォロワー数は五万人ほど、事務所に所属していない個人の配信者としては、相当な人気だった。
その彼が今、私とビデオ通話をしている。
「つ、つまりその、一緒に配信してみませんか、ってことです。お互いにフォロワーを増やせるといいなって」
沈黙を埋めるように話し続ける。自分の推しと話せる嬉しさなんて感じる余裕はなかった。
無理もないと思う。
いま、私は彼を騙そうとしているのだ。
「……でも、ぷちぺむさんの方がフォロワー数は圧倒的に多いじゃないですか、僕なんかでいいんですか?」
彼は口を開く。聞き慣れた色気のある気怠げな声が耳を刺激する。いつもの配信より、どこか落ち着いた口調だった。
《腑抜けた顔してんじゃねえぞお、愛美》
イヤホンから聞こえてくる真の甲高い声に、ふと我にかえった。
「フォロワー数は私の方が多いのは確かです。けど、フォロワーの層は全然かぶっていないと思います。私も新しいファン層を獲得したいって思ってて」
「ぷちぺむさんは、どんなフォロワーさんが多いんですか?」
慣れない名で呼ばれて私の身体はこわばった。今の自分は三方愛美ではなく、『ぷちぺむ』なのだと改めて認識する。
《きょろきょろすんなよ。カメラの正面を見続けろ。あともっとボソボソ話せ》
耳障りな指示が飛んでくる。わかってるっつうの、と心の中で悪態をつく。
「ちょいギャルでちょいオタな女子がよく見てくれてますね」
彼のアバターが上下にゆれた。きっとカメラの向こうで頷いているのだろう。
「どんな動画を出してるんですか」
「あるあるネタとか、今期のアニメ語りとかですね。あ、最近はVTuberさんとのコラボもやってます」
事前に練習させられた通りに話をする。普段の自分の喋り方とは全然違って、妙に居心地が悪かった。
「今までで一番バズったのがこの短尺動画です」
リンクをZoomのチャット欄に貼る。十秒程度の短い動画だった。流行りの音楽に乗せて『ぷちぺむ』が喋っていた。オチがあってクスリと笑えて『ぷちぺむ』のキャラが立ってる動画─ということになっているが、私は内心、ちっとも面白いと思っていなかった。
「はは」
彼は小さい声で笑った。本当に動画が面白かったのか、礼儀として笑って見せたのかはわからない。できれば、礼儀として笑って見せただけであってほしかった。
「ぷちぺむさんの動画、おしゃれ感ありますよね。この動画も、今の服装もそうですし」
「いやいや、そんなことは」
より『ぷちぺむ』っぽくなるよう、いつもは着ない、オフショルダーのワンピースを私は着ていた。顔やメイクではなく、服を褒められたことは嬉しかった。『ぷちぺむ』ではなく、三方愛美の選択を褒めてくれたのだ。
口元がニヤけそうになって、つい手で顔を覆い隠してしまう。
《馬鹿! 顔に手を当てるな!》
インカムから真の叫ぶ声が聞こえた。
そうだった。
やばい、と思ったときには一瞬遅かった。
モニタを見ると、《No face detected》と赤字のエラーが表示されている。顔認識が正常にできていない。ディスプレイには、全く別人の顔が表示されていた。
容姿端麗でメイクもばっちりのインフルエンサー『ぷちぺむ』の顔ではない。
ただただ地味な、すっぴん姿の『三方愛美』の顔がそこにはあった。
血の気が引く。
ディープフェイクだとわかってしまう。
私の正体がインフルエンサーの『ぷちぺむ』ではないと彼にバレてしまう。
*
ことの発端は十日前、校門前で巨大なタラと対面した時に遡る。
下校時のことだった。校舎を出ると、七月の暑さが私を包んだ。マスクの内側が汗ばんで不快だった。居残りの補習を終えた私はくたくただったし、お腹が空きすぎて気持ちが悪かった。昼食はいつものように抜いていた。親から貰った昼食代は、既に猫崎ケンスケへの投げ銭代に消えている。今日はリモート授業にしておけばよかった、と私は後悔した。
数年前、パンデミックが突然はじまった。PTAと学校はどう対応するか揉めに揉め、結果としてリモート授業が解禁された。Zoomでも通学でも授業が受けられるよう、すべての教室に機器が揃えられた。登校するかの判断は各家庭に一任され、共働きで放任主義の我が家では、私が適当にその日の気分で決めていた。
ポケットの中でスマホが震える。画面を見ずとも猫崎ケンスケのツイートだとわかった。夕方は彼が毎日欠かさず呟く時間帯だった。
《顔がまんまる! ますますおもちに似てきたね》
ツイートに添付されていたのは彼の家猫、おもちたんの写真だった。おもちたんは、つぶらな瞳をカメラに向けている。真っ白で柔らかそうな身体が愛らしい。私はいいねボタンを押し込む。
彼はおもちたんを溺愛していて、頻繁に写真をアップロードしていた。猫崎ケンスケ、という名前も、猫耳のキャラクターデザインも、おもちたんが由来らしかった。
猫崎ケンスケが配信者としてデビューしたのは一年ほど前のことだ。当時、彼があるシューターゲームの実況配信をしていたのをきっかけに、私は彼を知った。私もハマっていたタイトルだった。パンデミックで外出ができなかった当時、私はPCゲームと動画配信に熱中していた。それまで好きだった、アニメや漫画は、コロナ禍になって急に見なくなった。それらの作品の中に現れる学生生活は、自分たちのそれとは大きく違う。なんだか他人事に思えてしまったのだ。
猫崎ケンスケは高校生を名乗った。ほとんどのVTuberの場合、それは単なる設定に過ぎない。でも、ひょっとすると彼は本当に高校生かもしれないと私は感じていた。言葉づかいや物事を見る感性が、不思議に私と似ている気がした。同世代かも、と思うと親近感が湧いてきて、ちょくちょく配信を見るようになった。
「あんたたちの世代はほんとに大変よね」と母はよく言った。「俺たちの頃は、部活をやってないやつなんてほとんどいなかった」と父も言った。ネットの記事で私たちは「コロナ直撃世代」と書かれていた。ネットやスマホばかりで密な人間関係が失われ、対面でのコミュニケーション能力に難があると指摘されていた。
私たちはティーンエイジャーが経験すべきことを経験していないらしかった。私たちに体育祭は来なかった。部活動は制限された。楽しみにしていた修学旅行もなくなった。昼食を友達と一緒に食べることすら制限された。
いくら反発してみたところで、新型コロナウィルスの感染者数は変わらない。鬱屈がいくら溜まろうと、私たちに現実を変える力はなかった。
だからこそ、同世代かもしれない猫崎ケンスケを、私はなんだか応援したくなった。
しばらくすると、彼の配信にアンチが現れるようになった。コメント欄が荒らされるだけではなく、配信しているゲーム上でも嫌がらせをされるようになった。
「ゴースティングされてるでしょこれ!」
彼は声を荒らげた。ゴースティング─配信で彼のプレイを見ながら同じサーバーでプレイする嫌がらせを彼は受けていた。配信で位置がバレることは、シューターゲームでは相当な不利になってしまう。偶然とは言い難い頻度で彼は負け続け、コメント欄では『コロナ世代、すぐキレるwww』と煽られていた。そんな配信が何回か続くと、彼は疲れ果てた声で呟いた。
「正直、活動やめよっかなと思ってるんだよね」
私はいてもたってもいられなくなった。アンチに負ける彼の姿を見たくなかった。
気付けば私は最寄りのコンビニに走り込んでいた。1000円のプリペイドカードを購入し、すぐにスマホからチャージした。
《ネコケンさんのファンです。ずっとゲーム配信見てました。アンチがいるならゲーム配信はゆっくり休んでもいいと思います。でも雑談もすっごく楽しくって面白いので、雑談配信だけでもいいから活動はどうか続けてください》
生まれて初めての投げ銭だった。まどろっこしい文章だなと、ボタンを押した直後に思った。色のついたコメントを見た彼は、「えっ」と一瞬沈黙した後、大袈裟なぐらいはしゃいで喜んでくれた。当時はまだ、彼の配信の登録者数も少なく、投げ銭もほとんどなかった。
「ゴースティングでモチベ落ちてたんだけど、とっても嬉しい。俺がんばるよ」
彼は私のアカウント名を読み上げ、ありがとうと言ってくれた。胸がいっぱいになった。彼は私を必要としてくれている。私も彼の力になりたいと思っている。初めて他人と本気で通じ合えたような気がした。ディスプレイの向こう側の彼が急に愛おしく思えてきた。私たちには私たちなりのコミュニケーションがあるのだと思った。
《ありがとうございます! 私は何があっても推し続けます!》
間髪をいれず、私は再び投げ銭を打ちこんだ。今度はストレートに文字に気持ちを乗せることができた気がした。彼はまたも大袈裟に喜んでくれた。私はそれを見て、プリペイドカードのポイントが一瞬でなくなったことなどどうでもよくなった。
アイドルを推す気持ちを、私はこのとき初めて理解した。他のどんなファンよりも、強く彼を応援しようと私は誓った。
私のコメントの影響がどれだけあったのかはわからないが、彼の配信は雑談ばかりになった。何かの歯車が嚙み合ったのか、それから彼の人気は急速に高まった。たまにしか来ていなかったコメントも、みるみる流速が早くなった。
今日では、猫崎ケンスケのチャンネルの登録者数は五万を超えている。先ほどの彼のツイートにも、すごい勢いでリプライが集まっていた。私は内心で新参者のファンに優越感を感じていた。あのとき私が投げ銭をしていなかったら、猫崎ケンスケの配信は終わっていたかもしれないのだ。
「タラじゃん!」
突然の叫び声。
私の意識はツイッターから校門前に引き戻される。
顔を上げる。同じクラスの藤島だった。「まじじゃん」「やべー」と周りの男子も次々に声をあげる。藤島はいつも男子の輪の中心にいる。おそるおそる彼らの視線の先に目をやると─本当にタラが落ちていた。
スーパーで見かけるような切り身の姿ではない。まるごと一匹、その場に落ちていた。体長は60センチはあるだろうか。身体もぷっくりと肥えていて、いかにも重そうだ。箱に入っているわけでもなく、歩道のアスファルトの上に、じかに置かれていた。
圧倒的異物感。そこにあるべきでない物が、CG合成みたいに存在していた。
「魚じゃん」「ウケる」「美味しそう」「でっけー」「こいつ死んだ魚みたいな目してんな」「死んだ魚だよ」と、藤島とその仲間たちは興奮している。私も思わず、彼らの輪の外側からそっとスマホで撮影し、仲良し三人組のLINEグループに共有した。すぐに恭子から《ヤバすぎて草》と返信が来る。もう一人の真の既読はまだついていない。
誰かが意図して一時的に置いていたのだろうか? だとしたら、箱に入れず地べたに直接置いたりするだろうか。あの後売り物になるにしろ、店で捌かれるにしろ、地べたに直接食べ物を置くなんて、なんだか変だ。
かといって、誰かが気づかず落としてしまった、というのも考えにくい。あんなに大きくて重そうなタラを運んでいて、落として気づかないなんてこと、あるわけがない。
嫌がらせの筋も考えたが、すぐに頭の中で可能性を消した。それなら犬とか猫のうんちをばらまいた方が効果的だし、何より安く済む。あのサイズのタラは値段も相応にするはずで、わざわざ嫌がらせのために買うなんて考えにくい。
とすれば、誰かに何らかのメッセージを送っているのではないか。私が気づけていないだけで、タラを置くことで何かのメッセージを発していたのかもしれない。スマホを手に取り「タラ 象徴」で検索してみる。ハトが平和の象徴であり、亀が長寿の象徴であるように、タラにも何かあるのでは─と思ったが、何もヒットしなかった。
家に帰るまでの間、隠されたメッセージとは何なのか、頭をしぼって考え続けたが、納得できる結論は出なかった。
家に帰ると、親が作ってくれていた夕食を急いでかきこんだ。猫崎ケンスケの配信の時間が迫っていた。私はいつものように自室でノートを開き、メモをとる準備をした。彼について新しい情報がわかったら、ファンWikiを更新するのだ。彼のファンWikiはほとんど私が更新していた。彼の全てを知ることで、彼を応援するんだという自負があった。
彼の配信がはじまった。様式美のようなオープニングに、何人もが投げ銭をした。
《そういえばさ、今日、学校でびっくりしたことがあってさ、なんていうか、何言ってるかわからないと思うんだけど─》
次の言葉を聞いて、私は耳を疑った。
《学校の校門前にタラが落ちてたんだよ》
一瞬、自分の頭がおかしくなったのかと思った。自分が見たものと、猫崎ケンスケが言っていることの区別がつかなくなってしまったのかと不安になり、頰をぱんぱんと叩いた。じんと頰が痛む中、猫崎ケンスケはどんどん話を続ける。タラって結構でかいんだよ? 60センチぐらいの立派なやつでさ。おろしたやつじゃなくて一匹まるごと落ちてたの。ほんと意味わかんなくてさ─どうやら本当に彼はタラの話をしているらしい。彼の話は止まらない─いやもうね、存在感がぱないの。めっちゃ笑っちゃった。おもちたんがタラめっちゃ好きだから、持って帰ったら喜ぶかなって一瞬思ったりもしたけど流石にやめた。ははは。いやほんとの話だよこれ─
どう考えても、猫崎ケンスケは私が校門前で見た光景の話をしているようにしか思えなかった。
(続きは本誌でお楽しみください。)