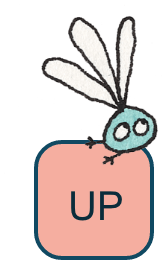一、友の隠れ家
小さい生き物たちは、喋ることがある。注意していないと聞きもらしてしまうような密やかな声で、ほんの一言だけ。
例えば草の間から飛び出したカナヘビが「夢見た」と言って岩のすき間に消えたり、甲羅を干していた亀が「足ない」と言ったり。ちなみに、その亀の足はちゃんとあった。
彼らの言葉は流れ星に似ていると思う。きらめいていて特別で、見つけたと思ったら消えているところとか。いつ流れるかもわからないのに、つい夜空を見上げて探してしまうところとか。
会話ができるわけではない。今までに一度だって彼らの言葉が私に向けられたことはないし、私の言葉に返事があったこともない。でもそれは別に悲しいことじゃない。流れ星を見つけられたらそれで十分なのであって、隕石を拾いたいとまでは思わない。そんな感じ。
カコン、と鹿威しが落ちる音が響く。澄んだ余韻が中庭全体に広がっていくのを感じた。私は椿の茂みに、半ば埋もれるように座り込んでいる。目の前の蛙を観察するためだ。冬眠から目覚めたばかりの小さな蛙。池の縁のぬれた岩にうずくまっている。少し弱々しく見えるのは、老いているからかもしれない。
辺りはもうだいぶん暗い。座敷の雪見窓からもれた灯りが、スポットライトのように蛙を照らしていた。私たちは同じように背を丸め、瞬きをし、喉を上下させた。わずかな動きに寄りそっているうちに、呼吸や鼓動まで感じとれるようになる。次第にそれが蛙のものなのか私のものなのかもわからなくなって、自分の輪郭があいまいになる。その状態になるまで深く深く集中していくのだ。
どれくらいそうしていただろう。私を集中から引き戻したのは足のしびれだった。足は腫れているみたいにしびれ、ジンジンと脈打っている。下駄の上で指を曲げたり伸ばしたりしてみた。大人用の下駄は私の足の二倍以上の大きさだ。指を動かすのには困らない。
くしゃみが出そうになって必死にこらえる。鼻をつまんでみたけれど、止まりきらなかった息がもれた。蛙は驚いたのか、むっちりとした太ももを落ち着かなげに動かした。
「帰らなきゃ」
ふいに鼓膜の片隅で、申し訳程度に声が響いた。蛙が喋ったのだ。
「どこに?」
驚かさないように、そっと声をかけてみる。返事はなくてもいいと思っているのに、話しかけるのを止められないのはどうしてだろう。
ちょぽんと軽い音を立てて、蛙は池に飛び込んでしまった。浅くて広い池だ。一度深く沈んだ蛙は、すぐに伸びやかに泳ぎ出した。シダの陰に隠れて見えなくなるまで、その後ろ姿を見送る。彼女はたぶん鯉に食べられてしまうだろう。私が生まれる前からこの家にいる巨大な鯉たち。彼らは底なしに思える食欲で、池に落ちたものを何でも飲み込んでしまうのだ。
暗い水面はぬらぬらと照る。それがただの水の流れなのか、尾ひれの揺らぎなのかもわからない。
私は足をかばってゆっくりと立ち上がり、大きく伸びをして固まった体をほぐした。部屋に戻るために振り向いて、廊下に立つ人影に気づく。
風呂上がりなのだろう。上気した足首が白っぽい浴衣のすそから見えている。眼鏡にかかる髪はまだ乾ききっていない。中庭からは五十センチほど高い位置にある廊下に立っているから、ものすごく背が高く見える。暗い天井に頭が届きそうなくらい。顔は影になって、眼鏡だけが白く反射している。
ずっと蛙を見ていたからか、妙な生き物に出会ったような気持ちになる。手を複雑に組んで、二本の足でぬっと立つお化け。
「美苑、そろそろ入りなよ」
呼びかけられて、やっと腑に落ちる。それは人間という生き物で、私の父親だ。
「何度も呼びかけたのに」
私は首を小さく振る。あれほど耳を澄ませていたのに、父の声は少しも聞こえていなかった。集中しすぎていたのは認めるけれど、父の声が小さいのもいけないと思う。
彼はけっして無口というわけではないのだけれど、会話は少ない。つまりほとんどが独り言なのだ。父は思考するときに、言葉に出さずにはいられないのだと思う。
独り言であれ会話であれ、父の声はとても小さい。学生たちから苦情はでないのだろうか。父は大学で教授をしているのだ。植物学の。
黒くつやのある廊下が足を避けてくもっている。父が足を動かすと、湯気に縁どられた足跡が残った。私はそれを茂みからじっと見つめる。逆の足跡だ。まだそこに誰かが立っているみたい。
「紫苑さんが探してたよ」
「母上が? 怒ってた?」
パッと反射的に顔を上げたけれど、父の表情はやはりよく見えなかった。ずっと中庭にいたことに対するお𠮟りの言葉だろうか。新学期の心構えをお説教されるかもしれない。
「また熱が出るといけないから、早く入浴して寝なさいだってさ。明日から四年生なんでしょ」
父が重ねて中に入るよう言うので、私は歩き出す。本当はもう少し中庭にいたかった。
「顔赤いよ。熱があるんじゃないの?」
「冷えたからだと思う。熱はないから、大丈夫」
階段代わりになっている平らな庭石を踏んで、廊下へと飛びあがった。できるだけ元気に見えるように。またくしゃみが出そうになって、なんとか止める。思ったよりも体は冷えてしまっていた。日中は暖かくゆるんできたけれど、朝晩の冷え込みはまだ鋭い。お風呂に向かおうとしたら、後ろから父に呼び止められた。
「生物を観察するのもいいけど、たまにはなんていうか、家族でゆっくり過ごす時間があってもいいんじゃないかな」
私は父を見つめて、首をかしげる。
「つまり、どういう?」
「どう……だろう。食事以外の時間も母上と過ごしてみたら? テレビを観るとか、遊ぶとか」
父は自分で言いながら頭を傾けている。私も眉をひそめた。母上はテレビを観ない。まして遊ぶとは何なのか。ボードゲームみたいなものを想像して、首を振った。母上にとってそれは時間の無駄以外のなんでもない。
「お父さん、この間も同じようなこと言ってた。どうして?」
どうしてって、と父は言いよどむ。彼は最近になって、急にこういうことを言うようになったのだ。家族で過ごすということについて。その真意はよくわからないし、上手くいっているとも言いがたい。私たちは確かに別々で過ごしていることが多くて、家族らしい家族ではないかもしれない。でも物心ついた頃から今までずっとこの調子でやってきた。私にとってはこれが普通なのに。
どうしてだろう、と父は口の中で言ったみたいだった。聞きまちがいかもしれない。何か言いたいけれどうまく言葉がでない、という様子で眉を上げている。
「いや、いいよ。早くお風呂入っておいで」
熱が出るよ、と父がまた繰り返すので、大丈夫だってばと口を尖らせた。
「最近はそんなに熱出してないよ。三年生の最後の学期なんか、ほとんど学校行けてたでしょ」
教室にはあまり入れていないけど、という言葉は飲み込む。そうだね、と父はまた困ったみたいに顎をかいた。私が学校に行ったのかそれとも休んだのかなんて、父は知らないのかもしれない。彼は私より先に家を出るから。
「友達も、がんばって作るんだよ」
おやすみと言いながら立ち去らない父。私がちゃんと風呂に入るか見ているのだろう。いくらなんでも今から中庭に戻りはしないのに。仕方なく小走りで風呂に向かった。本当にどうしたというのだろう。ぶつぶつ言い続けてはいるけど静かで、自分の考えに没頭していて、人にはあまり関わらない。それが父だったと思うのだけれど。
小学校に入学してから三年間、私が最も長く過ごした場所は保健室だった。原因は体調不良。大変ふがいないことに、私は人より体が弱いらしいのだ。特に悪いところがあるというわけではない。ただ疲れやすかったり、調子が悪くなる回数が人より多いだけ。
まず一番多いのは熱を出してしまうこと。あとは腹痛、頭痛。給食のおさまりが悪いと、午後に吐き気におそわれることもしばしば。
それでも少しずつ体は強くなっていっていると思う。春休みの間はほとんど熱も出さなかった。
「転校生?」
「いや、入学したときからいる子だよ。えっと、八口さん。保健室の子」
クラス替えをしたばかりの教室には、そわそわと落ち着かない空気が流れている。私はそんな空気にあらがうべく早々に着席し、大人しく本を読んでいた。それでもさすがに、自分の名前が呼ばれたら気になってしまうものだ。
「八口って、あのお屋敷の?」
「あれって寺じゃないんだっけ」
「じゃないよ。華道の先生の家じゃん。テレビに出てる」
お屋敷のお嬢様。教室の後ろの方にいるらしい子たちは、私が本に集中していると思っているのだろう。声を潜めようという気配もない。
お屋敷、もとい私たちの家は確かに古い日本家屋で、立派で、お屋敷としか言えない見た目をしている。山の中腹辺りに建っているからお寺っぽく見えるのもたしかだ。山も八口家のものだから、周囲に他の家もない。つまるところかなり目立っているのだ。町のみんなに認識され、こうして話題にされても仕方がないと思う。ものすごく嫌だとも思わないけれど、選べるなら普通の家がよかった。
後ろを振り向いてみる。時間割を書くための小さい黒板の前に数人の女の子たちが集まっていた。目が合ったけれど、すぐに逸らされてしまう。彼女たちはお互いの肩を押し合いながら、新しく教室に入ってきた子に駆け寄って行った。
「ほーちゃん! またおんなじクラスだね!」
はしゃぐ女の子たちの声。それと同じ声がクラスのあちらこちらで上がっている。誰とも話していないのなんて、私くらい。
私は教室の中を何となく見回す。同じクラスになったことがある子もいるはずだけれど、誰の名前もわからなかった。小さい生き物たちを観察するのはあれほど楽しいのに、人間たちには何の興味も持てない。みんな同じ顔だ。当然歳は同じだから、ほとんど大きさに違いもない。制服があるから服装も一緒。見分けるだけで一苦労だ。
頑張って友達を作るんだよ。父の言葉が脳内で再生される。指導めいたことをしない父が言ったことだから、妙に頭に残ってしまっていた。学校は勉強をするところだから、友達は無理に作らなくてもいい。勉強はしたい人がするものだから、したくないならしなくていい。今までの父だったらそんなことを言いそうなのに。
私は軽くため息を吐いた。父の言うことにも一理ある。私は保健室にいる間、連絡ノートや配布物を日直の子に持ってきてもらっていた。いつまでも日直に頼ってもいられない。休んだ日に宿題をメモしてくれたり、ノートを写させてくれたりする相手を自力で調達すべきだ。いちいち探すのは大変だから、決まった相手がいるといい。つまりそれが友達なのだ。助けあいが約束された間柄。集団生活においては、やはり友達はいた方がいい。
私の後ろの席には女の子が座っていた。そばに立っている子と話し込んでいる。まずは近場から声をかけてみようか。
女の子たちはひっきりなしに喋っている。話しかけるタイミングというのがわからなかった。回転している大縄跳びに上手く入れない感じに似ている。
「おはよう」
意を決して声を出してみたけれど、結局女の子たちの会話を中途半端に分断することになってしまった。立っている方の子はすでに迷惑そうな表情を浮かべている。
「私、八口美苑です。これからよろしくお願いします」
どちらの女の子に言うべきか決めかねたので、二人のちょうど真ん中に向かって言葉を投げかけてみる。結果として誰に言っているのかわからない、朝礼の挨拶みたいになってしまった。
女の子たちは一応ぎこちなく挨拶を返してくれた。しかしそれ以降何も言わない。どうして名乗らないのだろうか。私は名乗ったのに。
不自然な間が空いて、女の子たちは困惑半分、笑い半分でお互いに目くばせし合った。
退散した方がよさそうだ。失礼しました、と口の中で呟きながら姿勢を戻す。背後から押し殺した笑い声が聞こえている。去年も同じクラスだったのに、というささやきも。
「珍しいね、美苑がテレビ観るなんて」
居間で録画したドラマを観ていると、父が部屋に入ってくる。
「クラスで流行ってるから」
「へえ、友達ができたの?」
父の声が明るい気がする。なんとなく罪悪感を覚えながら、私は首を振った。友達どころか、まだ誰とも会話を交わしていない。この一週間休まずに教室に行けたのは快挙だが、それだけで友達ができるというわけでもないらしい。
「ごめん、友達はできてない。話題になってるドラマを観たら、いいかなと思って」
教室にいる間、みんなが話題にしていることをそれとなく調べていたのだ。意味が分からないことがほとんどだったが、このドラマをみんなが観ているということは間違いない。
「なるほど。話題作りか」
父は納得したように頷きながらも、眉間にしわを寄せている。
画面の中では、不良と言われる学生たちが隣の学校の不良たちと喧嘩をしていた。ドラマの中の学校は落書きだらけで、机が積み上げてあって、学びの場とはとても思えない。本当にこんな学校があるのだろうか。
「勉強したくないならしないでいいけど、学校を荒らすのは違うよね」
理解に苦しむ、と父はますます表情をくもらせる。私はそうだね、とあいまいに返した。私だってこのドラマの内容が好きで観ているわけではないのだ。どういう立場で返事をしたらいいのかわからない。
「悪影響があるんじゃないか、とか思う?」
「美苑がどうってわけじゃないけど、このドラマを面白いと思っている小学生たちがどこをカッコイイと思ってて、どう真似しようとするかは気がかりかなあ。でも友達を作るっていうことは影響したりされたり、そういうことも含むから」
父は途中から力尽きたみたいに声を小さくしてしまったので、何を言っているのか聞き取ることができなくなってしまった。よくあることだ。
「悪影響もあるかもだけど、影響を受けること自体は悪いことじゃないね。友達を作ろうと努力しているのはすごくいいと思う」
父はなんとか盛り返して聞き取れる声で言うと、ソファーに腰かけた。テレビを観続けるつもりらしい。
「目が悪くなるから、もうちょっと下がって観なさいよ」
私はテレビから三十センチくらいの床に座っていた。二十四インチの小さいテレビ。この家で唯一のテレビだ。ほとんど誰も観ないので滅多に使われていない。
私が音量を上げようとすると、父がリモコンを操作して字幕を表示させてくれた。知らない機能だった。テレビの下の方に文字が表示される。「うりゃあ」とか「ぐっ」とか。丁寧に文字におこされているのを見ると、喧嘩がより奇妙に感じられてしまう。
私と父は並んで、ドラマを最後まで観た。第五話の放送を録画したので、今までの話は推測するしかない。私は登場人物の顔と名前を覚えることに集中していた。しかしなかなか難しい。やはり顔を見わけられないのだ。服装に個性があるので、全身が映っていると判別しやすいのだけれど。
「影響された?」
アイドルが歌うエンディングを観ながら、父が尋ねてくる。私は首を振った。
「なにも」
少なくとも真似したいと思った場面はなかった。ストーリーもほとんど頭に入っていない。
「アトリエ行くの?」
父はソファーの横に茶色い革の鞄を置いていた。それはシルエットが楕円に見えるほど膨らんでいる。ノートパソコン、カメラ、筆記用具、電卓。あとよくわからない電子機器とか研究の資料がたくさん入っているのだ。
「一緒に行く?」
行く! と叫んで立ち上がる。しいっと父が指を立てた。
慌てて口を押さえる。鬼、と父が指を角みたいにコメカミに当てる。そのまま皮膚を引っ張って目を吊り上げた。怒ったときの母上の顔真似らしい。ちょっと笑ってしまったけれど、母上の顔を思い浮かべるとすぐに凍り付く。
私のイメージの中の母上は、いつも冷たい刃みたいな顔をしている。研ぎ澄まされていて冷たく、触れてはいけない感じ。母上が笑っているところなんて、生まれてから一度も見たことがない。
彼女はいつも厳格で、自他ともに厳しい。私にとってはルールそのものみたいな人だ。言うことなすことすべて正しくて、太刀打ちしようがない。たぶん母上は世間一般でいうお母さんとは少し違う。例えばそう、私は彼女に甘えたことなんてないし、甘えたいとも思わない。そういうものとはかけ離れているのだ。
母上は今、ふすまと廊下を隔てた一つ向こうの座敷で教室を開いている。彼女は活け花の先生なのだ。よくは分からないけれど、偉い先生らしい。テレビに出たり新聞に載ったりすることも珍しくない。
母上が稽古をしている間は、家の中がシンとしずまりかえっている。切られる直前の花か、手厳しい指導に怯える生徒さんたちか。とにかく何者かの緊張感が漂って、空気が張り詰めているのだ。その感じがあると、ああ土曜日の朝なのだなと実感する。
私と父は足音を忍ばせて、お屋敷の外に出る。アトリエは山を十五度くらい回り込んだところにある。車だと五分くらい。エンジンの音を響かせるわけにはいかないからゆっくり歩いていくけれど、それでも十五分ほどで着く。
アトリエは父が結婚して少ししてから建てたものらしい。論文を書くために。小さい建物だけれどキッチンやお風呂まであるから、泊まることだってできる。とはいえ父がそこに泊まったことは、私が知る限りでは一度もない。
「外で遊んでるね」
声をかけたけれど、すでに研究のことで頭がいっぱいらしい父からは返事がなかった。なにか小さく喋りながらアトリエに入っていく。私のことはもう見えてもいなさそうだ。いつものことだから気にしない。というより、その感じが心地よかった。友達がどうとか母上がどうとか、干渉してくる父とはどう接していいかわからないから。
私は花畑に潜り込む。花に用があるわけではない。その向こうの、山際の茂みに行きたいのだ。
(続きは本誌でお楽しみください。)