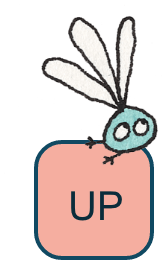第一章
七代目立川談志。
世間のイメージは毒舌家、古い経歴を知る人からするとタレント議員の走り。沖縄開発庁の政務次官にまでなったが、わずか三六日で辞任した。原因は二日酔いで記者会見に臨み、記者から「酒と公務とどちらが大事なんだ!」と問われ、「酒に決まっているじゃねぇか!」とタンカを切ったから。
そんな破天荒な落語家だが、若い頃から古典落語に関しては天才だと評価され、近年は談志こそが落語中興の祖だと言う人もいる。いや、ただの異端児だと談志を毛嫌いする向きもある。談志の濃いファンは、談志信者と呼ばれている。
とにかく好き嫌いの分かれる落語家であることは間違いない。
若い頃に出版した『現代落語論』は、多くの落語家や落語ファンのバイブルとなっている。著書のなかで「落語が『能』と同じ道をたどりそうなのは、たしかである」と危惧し、「伝統を現代に」をスローガンに落語と闘い続けたのも事実である。
さらに、「落語は人間の業の肯定」だと謳った。人間は弱いもの、ダメなものだ。それを認めてやるのが落語だと。
たとえば、忠臣蔵で主君のために切腹覚悟で仇討ちを遂げた四十七士は業の克服であり、それは芝居や映画の描くこと。一方、落語は、いくら主君のためとはいえ、仇討ちなんてとんでもないと逃げてしまった大勢の家来の側を描く。つまり「業の肯定」なんだと結論づけた。
談志は一九八三年、長年在籍していた落語協会から離脱して、落語立川流を創設。初代家元におさまった。
引き金になったのが、真打ち試験問題。当時、落語協会の会長であったのちの人間国宝、五代目柳家小さんとは相思相愛、親子のような師弟関係だと言われていた。だが、のちほど詳述するこの一件により、談志は、師匠小さんから破門される。
落語立川流をつくったはいいが、三六五日、一年中興行を行なっている東京の寄席─新宿末廣亭、上野の鈴本演芸場、浅草演芸ホール、池袋演芸場には、談志をはじめ、その弟子たちは全員出演することができなくなった。当時、寄席は落語家にとって命であり、修業の場としても必要な空間とされていた。しかし談志は、「寄席がなくても落語家は育つ」という意志のもと、売れっ子の弟子を育て上げた。
談志の功績のひとつに『笑点』がある。寄席芸としてファンに親しまれていた大喜利をテレビショウに仕立て上げたのだ。『笑点』はその後、五十年以上にわたってお茶の間の支持を受け、いまなお親しまれている。
談志は晩年、落語はイリュージョンだと謳い、なんだかわからない夢のような、しかしそれは芸術の本質でもあると言うようになった。同時に、落語とは「ひとことで言うなれば、江戸の風が吹くもの」とも主張し、とりわけ後者は多くの落語ファンの支持を得た。
談志を絵画で喩えるならば、若い頃は写実主義。やがて、己のフィルターを通して語る印象派に変わり、晩年はキュビスムへ。抽象画の世界に入り込んだが、末期は喉のガンによりきちんと話すのが難しくなり、まるで一筆描きのごとき落語をやるようになった。
そして二〇一一年一一月二一日、七五歳の人生に幕を下ろした。
常人ではなかった。その芸、言動、行動のどれをとっても天才としか言いようがない。
かつて私は、立川談志という落語家が大嫌いだった。
落語家のくせに議員になったり、テレビに出てくれば生意気なことばかり言って、こんな落語家がまともな落語をやるはずがないと思っていた。
子どもの頃から好きだったのは、いわゆる「名人」と呼ばれていた本寸法の落語家だ。
中学生の頃、NHKで放映された懐かしの名人芸での三代目三遊亭金馬の『藪入り』に衝撃を受けた。
「おじいさんなのに面白い!」
ちょうど同じ時間帯に『8時だョ!全員集合』が放映されていて、私としてはカトちゃんを見たかったのだが、父親が薦めるので、しかたなく見たのだった。
「カトちゃんより面白い!」
衝撃である。おじいさんなのに面白い。ましてや、当時の子どもには神のような存在であったカトちゃんよりも面白いとは。
あくる日、学校に行くと友だちに吹聴して回った。
「ドリフターズより面白い人がいるんだよ。金馬! すごいんだよ」
以来、落語に興味を持つようになった。
父親の書斎に落語全集のレコードがあり、そのなかに金馬の『藪入り』もあった。ソラで言えるほど聴きまくった。金馬のほかにお気に入りは、十代目金原亭馬生。水墨画のようなシブい落語をやる名人だった。
高校生になると、落語を聴きに寄席やホール落語に足を運ぶようになった。
大学一年の夏、私の運命を変える出来事が起こる。
東横名人会という歴史あるホール落語の会があった。たまたま購入したチケットは最前列のド真ん中。落語家たちの息遣いが伝わってくる席だった。
お目当ての馬生の出番。いつもならば前座が出てきて、高座にある座布団をひっくり返し、落語家の名前の記されためくりを返す。出囃子に乗って落語家がひょこひょこ現れると、座布団に座り、深くお辞儀をする。
しかし、このときは違った。
出囃子はたしかに流れたのだが、幕が閉まってしまった。
しばらくして、ふたたび幕が上がった。すでに馬生が高座に座っていた。
のちにわかったのだが、馬生は病気のため、高座まで歩くことができなかった。なので、いったん幕を下ろし、弟子たちが馬生を担いで高座に座らせたのだという。
このとき馬生は、食道ガンに侵されていた。
声が出ない。『船徳』という夏の定番の落語をやったが、台詞が聞きとれない。当然、笑いもまったく起きない。それどころか、客の多くは寝ていた。
馬生は、噺を中断させてしまった。痰が喉に絡んだようだ。ちり紙を懐から取り出し、口をぬぐうと、「高座でこんな失礼なマネをしたのは、初めてでございます」と客に詫びて、噺を再開させた。
おそらく馬生の落語家人生で最低の落語だった。だが、私は涙が止まらなかった。芸人としての気迫がヒシヒシと伝わってきた。「坊や、落語を頼むよ」と私に対して、馬生が言っている気がしてならなかった。
帰り道、私は決心した。
「この人の弟子になろう!」
当時の私は、映画監督になるという夢を追って、日本大学の芸術学部に入学していた。
でも、落語家になろうと思った。
その十日後、テレビでニュース速報が流れた。
「落語家の金原亭馬生さん、亡くなる」
……え?
全身が震えた。
馬生が亡くなってしまった。
私の父は、息子が馬生のファンということを知ってはいたが、まさか弟子入りまで考えていたとは夢にも思わず、「ああ、死んじゃったのか。残念だなあ」と言った。その軽さに、腹が立った。
金原亭馬生、享年五四歳。
そんなに若かったのか。
私はてっきり、もっとおじいさんかと思っていた。
落語とはおじいさんが演ずるもの。おじいさん以外の落語家は、落語家にあらず。そう信じていた。おじいさんが面白いという衝撃。そんなおじいさんのファンになっている自分が面白いとも思っていた。
弟子になりたかったことを、どうしてもこの最高にカッコよかったおじいさんに伝えたい。私は馬生の葬式に行くことにした。いや、むしろ弟子入りに行くような気持ちだった。
亡くなった人に弟子入りする─。
志は崇高だが、喪服すら持っていなかった。
「ねえ、お母さん、うちに喪服ある?」
「お父さんのは冬用しかないよ」
「冬用だと暑いなあ」
「夏用ならば、リサイタルで使う燕尾服ならあるわ」
父はクラシックのギタリストだ。スーツはいっさい着ない。リサイタルのときは燕尾服を着ていた。子どもの頃からその姿が嫌いだった。嫌いというか怖かった。まるでバルタン星人のようなのだ。
「燕尾服なんか着て、葬式にはいけないよ」
「お葬式? 誰の?」
「いや、本当の葬式じゃない。大学の授業で使うんだよ」
授業で喪服を使うって、どんな授業なんだ。ただ、私は演劇学科だったので、衣裳だと思えば、なんら不思議なことはない。
「高校のときの制服のズボンに白シャツで黒ネクタイをすれば、それらしく見えるよ」と、母がアドバイスしてくれた。
冬用の喪服。燕尾服。制服。
三択である。
当然ながら、私は制服を選択した。
ここで問題が起きた。制服のズボンのチャックが壊れていたのだ。
「これなんとかならないかな?」
「じゃ、縫いつけてあげようか」
縫いつけられたら、たまらない。どうやってオシッコをすればいいのか。
しかたなく私は、ズボンの前が開いたままで出かけた。電車ではカバンで前を押さえてごまかした。
日暮里にある馬生の自宅。葬儀の受付まできて、はたと気がついた。
香典を持っていない。
財布には数千円しか入っていない。香典袋もないし、いくらなんでも香典を数千円で済ませるわけにもいかない。ましてや、剝き出しで。
私は電信柱の陰に隠れ、同じような境遇の人はいないかしらと見ていたが、そんなやついるわけがない。
そのうち受付の人が私の存在に気がつき、声をかけてきた。
「なにか御用ですか?」
「すみません、ご祝儀を忘れてしまって」
「ご祝儀って?」
「あの、弟子になりたいんです」
「弟子に? 師匠は亡くなったんですよ!」
「わかっています。気持ちを伝えたくて。……あの、お線香だけでもあげたくて」
「困ります」
「いや、そこをなんとか─」
押し問答をしていると、馬生一門の番頭格、古今亭志ん駒師匠が現れた。この方はヨイショの達人という異名を持つ。
「なにをモメてるんだい?」
「あ、志ん駒師匠、こちらの方が弟子になりたかったから、お線香あげさせてほしいと。香典もなにも持ってきていないんですよ」
すると志ん駒師匠、ニコッと笑みを浮かべた。
「兄ちゃん、師匠のファンなのかい? 若いのにいい了見だね。香典なんかいらねぇよ。さあ、こっちにいらっしゃい。本当にいい了見だなあ!」
いくら私をヨイショしても、それこそ祝儀を持ち合わせていない。
「さあ、ここに並びな。師匠は喜ぶよ。おまえさんみたいな若い子がファンだなんてね」
「……はい」
「弟子になりたかった思いの丈を、きちんと伝えるんだよ」
「ありがとうございます」
一般の参列者は庭からのお焼香。祭壇の脇には実弟の古今亭志ん朝師匠、馬生師匠の娘さんで女優の池波志乃さん、ご亭主の中尾彬さんらが鎮座していた。
私の番が回ってきた。
「荷物、お預かりしましょうか」
係の人が声をかけてきた。
「いや、けっこうです」
なにしろズボンのチャックを隠すためのカバンだ。しかし、カバンで前を押さえたまま、拝むのは難しい。両手で拝めばカバンは落ちてしまう。かといって片手だけで拝むわけにはいかない。
思案に暮れていると、馬生師匠の遺影が目に飛び込んできた。かわいらしい笑顔の写真であった。
自然と身体から力が抜け落ちた。カバンを下に落として、手を合わせた。
「師匠! 弟子になりたかった。師匠! 弟子にしてください」
そう言うと涙が止まらなくなった。
遺族は驚いた。見ず知らずの若者が、弟子にしてくれと号泣している。
しかもズボンのチャックが開ききっている。そのことに気づいた誰かが、耐えきれずに笑い出した。つられて皆、肩を震わせはじめた。私はあわててカバンを拾い上げると、前を隠した。
正式な弟子入りではない。
でも、これが私にとって落語家人生スタートの日だ。
初日に笑いがとれたのだから、幸先はよかったのかもしれない。
葬儀場をあとにした私は、こんな日だから落語を聴きたいと思った。
足は池袋演芸場へと向かった。「主任 立川談志」と書かれた看板が目に留まった。
私は談志が嫌いだった。よりによって談志とは。
木戸銭を払い、こぎたない雑居ビルのような階段を上る。
普段はガラガラの客席だが、談志のトリということもあり満杯の客席。おそらく弟子であろう、中途半端に面白い顔をした落語家が高座に登場した。口を曲げたり、やたら手を動かすところばかりが談志にそっくりで、案の定、面白くもなんともなかった。
数人の芸人の高座のあと、談志が出てきた。
不機嫌そうな感じで高座に座り、お辞儀をした。客は大盛り上がり。すると、談志はおもむろに馬生の思い出を語りはじめた。
「ネタ数は誰よりも多かった師匠だったなあ。でも、十八番がねぇんだよな。ただ、いまの落語界においていちばん話の通じる人だったよ。きちんと論理で話すことができる、落語家にしては稀有な存在だった。もったいねえなあ」
べつにギャグを言うわけでもなく、淡々と思い出を語る。盛り上がっていた客のテンションが次第に下がっていくのがわかった。そんなことはおかまいなく、談志は馬生の話を続けた。
やがてシビれをきらした客が、談志をやじった。
「落語をやれ!」
客席に緊張が走る。談志は客とよくケンカをする、という話がのべつあったから。
やじられた談志は、しばらく無言でいた。そして、悲しそうな顔で言った。
「ごめんな。落語をやる気分じゃないんだ。金なら返すよ」
私の身体に、電流が走った。
商売人としては失格だ。どんなときでも金銭に見合う芸を披露しなくてはダメだ。でも、芸術家としては素晴らしい。馬生が亡くなって、そんな悲しい気分で落語をやれば客には迷惑だし、落語そのものにも失礼だ。
その言葉にシビれたのもたしかだが、それ以上に、凜としたその佇まいに惹かれた。
なんてカッコいいんだろう!
一瞬、談志と目が合った。
「おい、おまえ。落語家になりてぇんだったら、オレの弟子になれよ」
談志が高座からそう言っているように聞こえた。
「この人の弟子になろう」
その晩、けっきょく談志は落語をやらなかった。
追い出しの太鼓が鳴り、談志が丁寧にお辞儀をする。ちょっと顔を上げると、満面に笑みを浮かべた。その笑顔は悲しみに溢れていた。
帰りの電車、私の脳裏で、馬生師匠の遺影の笑顔と談志の笑顔とが重なり合い、ひとつになった。
(続きは本誌でお楽しみください。)