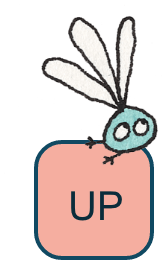#1 Closer 僕らはあの頃と変わらない
「ねぇねぇ、どうして指輪って特別なんだろうね」
「特別?」
「うん。ネックレスとかピアスとかブレスレットとか、アクセサリーって色々あるけど、指輪って特別な感じがするでしょ? どうしてなんだろう」
「そりゃあ、結婚式で使うからじゃないかな」
「そういうことじゃなくて。もっとロマンチックなことを言ってほしいの」
「ロマンチック? なにそれ。嫌だよ、恥ずかしいから」
「えー、いいじゃん! ちょっとでいいから言ってみてよ!」
「無理」
「お願い! ね!」
「そうだなぁ……」
「うんうん」
「指輪って、心とつながるものなんだ」
「心と?」
「古代ギリシャだと、心は心臓にあるって思われていたんだって。その心臓と左の薬指は一本の血管でつながっていて、そこに『永遠』を誓った指輪をつけると─」
「相手の心と永遠につながれる!」
「まぁ、そういうことかな」
「へぇ~、ロマンチック! やるやるぅ~! そっかぁ、指輪にはそういう意味があったんだね。じゃあ征ちゃんがくれたこの指輪があれば、わたしたちの心は─……」
ずっと一緒なんだね。
恋をした。今までの片想いが全部ニセモノだって感じるくらいの圧倒的な恋だと思った。
昨日よりも太陽がうんと綺麗で、春の匂いがくすぐったい。風の歌は優しくて、胸の奥で果実のような甘さが広がって心が痛いよ。手のひらがあなたに触れたいって叫んでる。
五感で、心で、全身で、わたしはあなたに恋をした。
世界の色が全部塗り変わっちゃうくらいの、正真正銘、本物の恋を……。
安藤花耶はそんなことを思いながら一人で勝手に盛り上がっていた。
彼女がその『圧倒的な恋』と出逢ったのは入学式のあとのことだ。式を終えて一年A組の教室に入ると、黒板に貼り出されていた席順表に従って座席に腰を下ろした。男女混合の名前の順らしい。『安藤』という比較的ア行でも後ろの方になることの多い彼女は、一列目の一番後ろの席になった。
ラッキー! 一番後ろだ! 授業中でもスマホいじれるじゃん!
そんなことを思いながら、椅子の後ろ脚に体重をかけて扉の向こうに目をやった。一階に位置する教室。廊下を挟んで並ぶ窓では桜の花が満開だ。その姿がこの上なく美しい。
花耶はロッキングチェアのように椅子をゆらゆら揺らしながら、ちょっとだけ緊張していた。
同じ中学校の友達とは別のクラスになってしまった。心機一転、友達作りを頑張らないと……。
そんなことを思っていると、一陣の風が扉の横の廊下を吹き抜けた。春風に誘われて、桜の花びらがひとひら、窓から迷い込んできて宙を舞う。その軌道をなんの気なしに目で追いかけていると、桜に続いて一人の男の子が花耶の横を通り過ぎていった。うんと背の高い男の子だ。
花耶はバランスを崩してひっくり返ってしまった。けたたましい音が教室内に響き渡る。クラスメイトたちが一斉にこちらを見た。なんという高校デビューだろうか。恥ずかしさを唇の端に浮かべて「あはは、ごめんなさい」と苦笑いで立ち上がり、椅子を引き起こして、目立たぬように腰を下ろそうとした。そのとき、前の扉が開いて、さっきの男子が入ってきた。
教室で唯一立っていた花耶は、彼と目が合う。
その瞬間、時間が止まった。壁の時計の秒針が、クラスメイトたちが、宙を舞う桜が、ピタリと一時停止した。そんな気がした。ほんの数秒の視線の会話が、何秒間、何分間、何時間、何年間、何光年にも思えた。心臓まで止まってしまったみたいだ。息すらできない。なにも考えられない。そんなふうに花耶のすべては、いともあっさり、奪われた。
背が高くて、肌が白くて、整いすぎているほど綺麗な顔立ちをした男の子。少し寂しげな漆黒の瞳に思わず吸い込まれそうになる。文字通り、彼に釘付けになってしまった。
再び世界が動き出したのは、二人の間をチャイムの音が駆け抜けたときだった。
彼は黒板で自分の席を確認すると、隣の列の一番前に座った。大きな背中だ。長い黒髪が春の風に揺れている。花耶の心もゆらゆら揺れていた。
席順表をチラッと見た。そこに記された圧倒的に素敵な彼の名前を知りたかった。
「市村征一君……」
口の中で呟くと、それは特別な呪文のように思えた。神秘的で美しい恋の魔法だ。
こうして花耶の恋ははじまった。
永遠のように遠く果てしない未来へと向かって。
忘れじの 行く末までは かたければ
今日を限りの 命ともがな
これは、花耶のお気に入りの一首だ。平安時代の和歌で、『新古今和歌集』に収録されており、『百人一首』にも載っている。詠み人は儀同三司母という人だ。
花耶は文学少女じゃない。小説なんてほとんど読んだことがないし、知っている文豪は太宰府治くらいなものだ。本より動画が好きで、年がら年中YouTubeを見たり、TikTokの動画を指で弾いている。成績は中の下。それでも和歌は好きだった。特にこの歌の意味に心を打たれたのだ。
「いつまでも愛は変わらないよ」というあなたの誓いが、遠い未来まで変わらないなんて分からないから、その言葉を聞いた幸せな今日の間に、命が尽きてしまえばいいのに。
この刹那感がたまらない。うんうんと激しく同意したくなる。遠い未来のことなんて分からない。永遠の愛とか、消えない想いも、来世も、別に信じてない。そんな不確かなものよりも、それよりも今、この瞬間に「好き」って言葉がほしいんだ。花耶は常々そう思っていた。
そんな打ち上げ花火のような思考のせいか、彼女は幼い頃から恋多き乙女だった。小学生の頃からクラス替えがあるたびに片想いをしていたような気がする。初恋の相手はダンスが得意な中島君。次は算数が得意な大磯君。サッカークラブの吉田君、加藤君、杉山君……などなど、中学を卒業するまでの間に十人くらいに想いを寄せた。だけど、どれも実らなかった。告白する勇気がなかった。バレンタインチョコを渡したこともなければ、誕生日プレゼントも渡せずじまい。だからいつも背中を見ていた。大好きな人の背中を。遠くから見つめるだけで十分だった。
「この人がわたしの『運命の人』でありますように!」と心の中で祈りながら、いつも、いつでも、見つめ続けた。他人が見たら本格派のストーカーだと思うほど、意中の彼を目で追いかけていた。
しかし運命は残酷だ。大好きな背中の隣には、いつも別の背中があった。
恋にもなれない片想い─それが花耶の恋だった。
そんな報われぬ日々の中で、彼女は次第に思うようになっていった。
わたしには『運命の人』はいないのかなぁ……と。
失恋の胸の痛みで眠れぬ夜、花耶は悲しげに左の薬指を見た。そこから伸びているであろう赤い糸の行く先は、この世界の誰ともつながっていないのかもしれない。そう思うと切ない。悲しい。寂しくてたまらない。孤独でどうにかなってしまいそうだ。
どうしてわたしの恋はいつも上手くいかないの? 別に多くは求めてないのに。永遠の愛なんていらないのに。たった一言、「好きだよ」って言葉がほしいだけなのに。
花耶はいつも、いつでも、恋に恋い焦がれていた。運命の人と出逢えるように願いながら。
そして、ついに出逢った。それが市村征一だった。
市村君は、わたしの『運命の人』に違いない……。花耶は強く強く思った。
「それさぁ、前の人のときもおんなじこと思ってなかった?」
そう指摘してきたのは、中学時代からの友達の上原叶恵だ。
耳に小ぶりのターコイズのピアスをつけた明るい髪色の女の子。なかなかの優等生だ。花耶よりもずっと勉強ができるのだが、第一志望の高校に落ちたことで、一緒の学校に通うことができたのだった。
校舎の中庭のベンチに座って購買部で買ってきた菓子パンを齧りながら、叶恵は冷ややかな視線をこちらへ向けてくる。長い睫毛に彩られた目を細めている表情がなんとも憎たらしい。花耶はちょっとムッとして「そんなことないってば!」と言い返した。
しかし、待てよ、とすぐに思った。言われてみればそうかもしれない。前に好きになった小林君も「運命の人だ!」って一人で勝手に盛り上がっていた気がするぞ。結局、彼には恋人がいた。女子バレー部の超美人の恋人が。並んで歩く姿を見て「はいはい、あなたも面食いなのね」と冷めてしまった。そんな苦い記憶がよぎったが、花耶はぶんぶんと頭を振った。
「今回は違うよ! 全然違うから! なんていうか、輝きが違ったの!」
「輝き?」
「そう! 輝き! 市村君を見た瞬間、世界がぱーっと輝いた気がしたの! 今までとは全然違ったんだから! もうね、教室中がキラッキラに輝いたんだってば!」
「あんたさぁ、それ人には言わない方がいいよ。恥ずかしすぎて黒歴史になるから」
「うるさいなぁ」と花耶は焼きそばパンを口に突っ込んだ。
「それに、あれだけ背が高くて格好良いなら彼女くらいいるんじゃないの?」
「いないよ、絶対」
「なんで断言?」
「だって毎日彼のことを見てるけど、女子と親しげに話してるところなんて見たことないもん。高校入学と同時に横浜から引っ越してきたから、同中の友達もいないし、親しいクラスメイトもまだいないの。もう五月なのに。きっとわたしと一緒で人見知りなんだよ。部活もしてないし、アルバイトもしてないし、学校が終わったらいつもまっすぐ帰ってるみたいだし。家はJR横須賀駅のすぐ近くね。ほら、あの大きなマンション。オーシャンビューの」
「花耶さぁ、それぜぇぇったい人に言っちゃダメよ? ストーカーだって思われるから」
「ストーカー? どうして?」
「……ううん、なんでもない」と、叶恵はなぜだか苦笑いしていた。
「じゃあさ」と叶恵が肩を叩いてきた。「彼が『運命の人』って言うなら、動き出してみたら?」
「動き出す?」
「勇気を出して話しかけてごらんよ」
焼きそばパンを喉に詰まらせてしまった。パックのコーヒー牛乳で大慌てで胃に流し込むと、花耶はゲホゲホと何度か咳き込み「それはそうなんだけどさ」と弱々しく新品のローファーを見た。
「彼ってさ、なんていうか、『話しかけるなオーラ』がすごいんだよね。影があるっていうか、暗いっていうか、クールっていうかさ。まぁ、そこが格好良くもあるんだけどさ」
「高校からこっちに来たってことは、中学時代になにかあったかもしれないね」
「なにかって?」
「イジメられてたとか」
「えー! あんなに格好良いのに!? 背だって百八十センチ以上あるんだよ!?」
「容姿背丈は関係ないでしょ」
「それはそうだけど」
「まぁ、とにかく話しかけてごらんって。動き出さなきゃ、赤い糸も腐って切れちゃうよ?」
「叶恵ってさらっとひどいこと言うよね。分かってるよ、そんなこと。あーあ、ただでさえ好きな人に話しかけられない性格なのに、その上、彼の負のオーラがすごすぎて近づけないよ」
「弱音弱音。せいぜい頑張りな。今までと同じように話しかけられずに終わらないようにね。じゃあ、そろそろ行くね。次の授業、移動教室だから」
叶恵が手を振りながら去ってゆくと、花耶はブレザーの右ポケットからスマートフォンとワイヤレスイヤホンを出した。入学祝いにお父さんが買ってくれた念願のアイテムだ。
イヤホンを耳に突っ込んで音楽アプリの再生ボタンを押すと、リズミカルな音楽が耳を喜ばせてくれる。叶恵に教えてもらった洋楽のダンス・ポップ・デュオ。その代表曲だ。
少し散歩してから教室に戻ろうかな。ゴミ箱にパンの空き袋と牛乳パックを捨てて歩き出した。
入学して一ヶ月、はっきり言って、友達作りには苦戦している。だから今日も中学時代からの友達である叶恵にお昼を付き合ってもらった。教室で一人で食べる勇気はない。ひとりぼっちの陰キャだって思われるのは絶対に嫌だ。花耶は引っ込み思案な性格だから、いつもクラスに馴染むのには時間がかかった。だから春は一年で一番嫌いな季節だ─桜は好きだけど─。特に中間試験が迫ってくる五月のこの時期は憂鬱ゲージが満タンになる。教室にいると肩身が狭いし、家に帰るとお母さんに「勉強は?」と迫られる。どこにいても居心地が悪い。ため息ばかりが漏れてしまう。
ため息って春の季語に認定されるべきだよね……。
天を仰いでいつものように嘆息をこぼした。その途端、ちぎれ雲が東の空へと流れていった気がした。春風の成分って半分くらいはわたしみたいな不器用な子のため息なのかもしれないな……と、そんな馬鹿げたことを思いながら、花耶はまた彼のことを考えた。
市村君もおんなじ気持ちだったりするのかな。もし彼もわたしと同じ憂鬱を感じているのなら、それだけで救われる気がするんだけどな。なんてね。そんなことを叶恵に言ったら「それ、人に言うのは絶対やめなよ」って馬鹿にされるに決まってるよな。
苦笑いで黒いローファーを一歩前に出す─と、心が大きく胸を叩いて足が止まった。
校庭の隅っこにある体育館。その扉の前に征一がいる。彼は制服のズボンに手を突っ込んだまま、ぼんやりと体育館の中を覗いている。館内では男子生徒がバスケットボールに興じているようだ。その様子を眺める彼の瞳は、いつも以上に憂いの色を帯びていた。
どうしてそんなに悲しそうな顔するの? 花耶は征一を見守った。
彼は苦笑いで頭を振った。「バカバカしい」と言いたげな、そんな痛々しい笑みだ。こちらへ向かってやってくる。花耶はたじろいだ。このまま逃げようか。でも、胸の奥で叶恵の声がした。
─動き出さなきゃ、赤い糸も腐って切れちゃうよ?
左の薬指を見た。そこにあるはずの目には見えない赤い糸の行く先が、彼の薬指とつながっていることを強く強く、強く願った。
この恋は今までのとは違う。彼はわたしの運命の人だ。だから動き出そう。よし……!
花耶はイヤホンを外してポケットに突っ込んだ。そして、
でも待って! なんて話しかければいいの!? 「市村君! 元気!?」とか? いや、わたしってそんな元気潑剌キャラじゃない。じゃあ「市村君! なにしてたの!?」とか? うん、自然な感じだ! いやいや、でも待って! どうして急にそんなこと訊くわけ? 馴れ馴れしいって! だったら「ちゃんとご飯食べた?」とか? いやいやいやいや、親じゃないんだから!
そんなことを考えていると、彼が無言で横を通り過ぎていった。
靴音がどんどん遠ざかってゆく。
どうしよう! 行っちゃうよ! 早くしないと! ええい! こうなりゃ出たとこ勝負だ!
「い、市村君!」
後先考えずに叫んで振り返ると、彼もこちらへ踵を返した。
入学式のあとの教室以来、久しぶりに彼と目が合った。
体育館から聞こえるボールのドリブルの音が胸に大きく響く。
花耶は恐る恐る、震える声で、言葉を放った。
「どうしてですか……?」
「え?」
「どうしてあなたは─」
恋のため息のようなそよ風が新緑の葉を揺らした。
その風の中、彼に伝えた。
「どうしてあなたは、いつもそんなに暗いんですか?」
(続きは本誌でお楽しみください。)