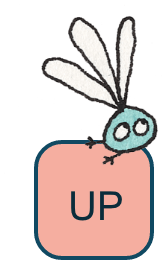【競売人(オークショニア)の権限】
一、競売は、競売人の裁量の下に行われるものとする。
(株式会社麻生オークション「オークション規約」)
◆ ◆ ◆
東京・京橋、〈麻生オークション〉本社。
午後一時二十七分。
椎名英司は廊下に佇み、スマホ画面の新聞記事をじっと見つめていた。
読む、までもない。その短い記事を探し出し、少々迷った後で結局保存してしまって以来、既に何度となく読み返しているのだ。句読点の位置までもう覚えてしまっている。
『七日午前二時ごろ、中野区の路上で、男性会社員が運転する乗用車が、路上にいた七十~八十代の男性をひいた。男性は全身の複数個所を骨折し、搬送先で死亡が確認された。中野署によると、死亡した男性は「路上寝」をしていたとみられ、署では詳しい事故原因を調べている。』
「出番だぞ、シーナ」営業部長の三谷が、横を通りつつ声をかけてくる。
「あっ、はい」
急いで後を追いながら、椎名は廊下のガラス窓をちらっと見やった。そこに映る自分の身だしなみを、もう一度確かめる。会社のプロトコルで、オークションの本番会場ではスタッフ全員が黒スーツを着用、その中で唯一オークショニアだけが蝶タイを着けることとなっている。
入社してもうじき十ヶ月。オークショニアをやらせてもらうのはこれが初めてではないのだが、今まで二回ほど任されたことがあったのは、いわば予想落札価格のつかない、〈成り行き〉と呼ばれるお手軽な出品作品の時間帯ばかりだった。むろん、それはそれで楽しかった。壇上に立ってはいても、客との距離が不思議と近く感じられる。その空気感が椎名は好きなのである。
だが、今日の午後の部はそれとはわけが違う─
無頼の天才陶芸家と謳われた故・岬冬堂の名品コレクション、その貴重な四十二点を扱う、会社としても重要な位置付けの競りなのだ。
三谷と共にスタッフ・オンリーの階段を駆け下り、照明も眩い受付ロビーへと出た。客やスタッフの行きかう、その一隅では、社長の麻生薔子が常連客とにこやかに談笑している。この〈麻生オークション〉の名物社長である薔子は、御年六十二歳。「美しい女であること」から生涯引退するつもりはなく、今でも人目を惹く華やかな容貌と美脚の主だ。今日のお衣装は他のスタッフと同じく黒のシンプルなスーツ。お気に入りのドルチェ&ガッバーナ。
足早な三谷に続き、競りの会場となるホールに入る。途端に視界に飛び込む、人の群れ。
(……多いな)
並べられた二百脚の椅子は、既にほとんど客で埋まっていた。競りの開始前から熱気が生まれている。午前中の部では七割ほどの入りだったのだが、やはり注目度が違うのだ。事前の入札の多さからもそれは予測出来ていたにせよ、椎名はさすがに少し動悸を覚えた。独特な無言の迫力を醸しているのは、客席よりもむしろ、後方の壁際に立っている老獪な面構えの男たちである。客たちの中に埋もれるより、競りの全体を見渡せる位置を選ぶベテランの業者は少なくない。
「あれっ、今日は椎名くんがオークショニアなの?」何度か営業で訪れたことのあるギャラリーの店主が、椎名の蝶タイに気付いて声をかけてくれた。「すごいね、冬堂の競りを任されたのかい。頑張ってね」
「はい、ありがとうございます。よろしくお願いします」
オークショニアが姿を現したことで、場内のざわめきがほとんど静まった。ロビーで話し込んでいた客たちもホール内へと移動してくる。
(大丈夫だ、ちゃんとやれる。あれだけ準備もしたんだ……)
三谷が先を譲り、椎名は満座の視線を浴びながら、なるべく胸を張って会場正面の壇の方へと歩いて行った。手にはびっしりと書き込みをしたオークション・カタログを持って。カタログは今回の全ロットの写真とデータが記載されたブックで、客たちがいま手にしているものと同じである。ただその各ページは、椎名がつい五分前まで追記し続けていた、オークショニアにとって必要な情報で余白が埋め尽くされている。作品のリザーブ価格─つまり「これ以下では、出品者が落札を認めていない」という金額。事前の入札の最高額と主だった入札者の名。電話で競りに参加する客たちの名。そして作品そのものに関わる補足のデータ等々。
「オークショニアは、言ってみりゃオーケストラの指揮者みたいなもんだ」椎名は以前、三谷に言われたことがある。「つまりカタログは、指揮者にとってのスコア、つまり楽譜と同じなんだ。指揮台に上がる前に、隅々までよく読み込んどけよ」
これからの約一時間強、三谷がすぐ斜め後ろに付いてくれるとはいえ、椎名は基本的にはあくまで一人で、そうしたカタログ・データを含めた無数の情報を脳内で瞬時に組み立てながら、次々に上がるであろう番号札の群れを捌いていかなければならないのだ。
会場の右側の壁際には、電話での参加を仲介する担当者たちの並ぶブース席がある。直接来場せずにビッドしたいという顧客のためのサービスだ。海外など遠隔地からの参加、あるいは顔を見られずに競り落としたいという匿名性を希望する客は、創業時から一定割合いるのである。
その電話用ブース前を過ぎた時、椎名の唯一の同期である筧と目が合った。
(がんばれ)筧が微かに頷いてよこした。
(おう、おまえもな)椎名も目顔で返した。
筧が本心としては自分がオークショニアに指名されたかったであろうことは、椎名にも想像がついている。むしろ「シーナ、おまえ、やれ」と三谷に言われた時には本気で驚いたくらいだ。筧は真面目な努力家で、その態度が初対面の客にも良い印象を与えるのか、新人としては営業成績も悪くない。色白の小顔に丸眼鏡がよく似合い、蝶タイを着けて壇上に立つ中背の姿には、いかにもお行儀のよさそうな雰囲気が漂う。もちろん大学で美術史もきちんと学んできている。一方の椎名はといえば、大学では一応「アート同好会」という、ネーミングもやや緩めのサークルに籍をおいてはいたものの、講義以外の時間はもっぱら生活費補塡のバイトに明け暮れていた。高校でも、部活は三年間バスケ。社内で当てにされることがあるとすれば作品運びなどの肉体労働の場面ばかりで、客の前ではいまだに有名作家の年代を間違えたりして、三谷に怒られているような有様なのである。
(なのに、どうして、俺……?)
オークショニアは、競売場における花形スターだ。
狭義には競売の進行役のことを指す。そしてさらに言えば、優れたオークショニアと呼ばれるためには、おそらく一般に想像される以上の資質が要求される。単に目の前で起きている競りの交通整理をすればいいというポジションではないのだ。作品や作家に関する十分な知識と適切な理解。微かな動きや表情を見逃さない眼。どんな瞬間にも場を仕切り通す冷静さはもちろんのこと、大勢の客に聞き取りやすい声、心地よいリズム、それでいて飽きさせないテンポ、絶妙なタイミング、そしてほどよいユーモアなど、卓越したコミュニケーション・スキルをも必要とする立場なのである。
その腕前が競りの結果にまで影響しかねないのだと椎名が最初に気付いたのは、ある出品客から「これは、三谷さん担当の競りに入れてね」とわざわざ指定された時だった。その後になって、海外のオークション・ハウスでは優秀なオークショニアの存在は扱う美術品と同じくらい重要とみなされ、メイン・オークショニアは管轄オフィスのトップが務めるというハウスも少なくないのだということを知った。
「筧、おまえは英語がうまいから、アメリカのショーンさんの電話ビッドを頼む」
三谷に続けて言われて、筧は「えっ? あ、はい」と慌てて応えていた。ショーン・マクビーは過去に何度か高額落札をしてくれた、米国東海岸の裕福なコレクターで、会社にとっては重要な顧客と言えるのだ。
「でも、あの、僕なんかに出来るでしょうか」
「他の英語出来る奴はみんな、別のクライアント対応で塞がりそうなんだ。おまえなら大丈夫だよ。頼んだぞ」
「オークショニアは、僕なんかでいいんでしょうか……」励まされる筧が少々羨ましくなり、椎名もなるべく同じ一年生らしく言ってみたのだが、「うるさい。俺がやれと言ったら、うだうだ言わずにちゃんとやるんだ」とカタログの角で小突かれただけだった。パワハラだ。
(だから……、なぜ、俺なんだ?)
椎名が正面の壇に上がり、演壇につく。三谷がそれに続き、椎名の斜め後ろに立った。競りの記録係は演壇の両サイドのブースに一人ずつ着席しているのだが、オークショニアと同じ視線の高さから競りの進行を追い、視認しつつ記録していくのが、今回の三谷の役目となる。三谷の身長は一七〇センチ台後半で、椎名とほぼ同じだ。
椎名は胸元にピンマイクを付けた。演壇上の小さなモニターの時刻を見る。
午後一時三十分。
「お時間となりました」
深呼吸を一つしてから、椎名は満場の客に向かって声を発した。
「ただいまより、陶芸家・岬冬堂先生の作品コレクション、計四十二点のオークションを開始いたします」
会場の前方に設置されている大型モニターに、モノクロの写真が映し出された。彫りの深い、眼に尋常ならざる覇気を宿した初老の男のポートレイト。
「皆様すでにご承知のとおり、岬冬堂先生は昨年八月、不幸にも交通事故に遭われ、お亡くなりになりました。七十四年のご生涯でした。〈孤高の無頼派〉と呼ばれ、全国各地を放浪される中で、数々の素晴らしい作品を生み出され、発表して来られました。伝統的な陶芸世界とエッジなフロンティアとの間に大胆な補助線を引く、刺激的で雄渾なその作品群は、日本国内のみならず海外からも注目を集め、アートのオリンピックとも称されるヴェネツィア・ビエンナーレを始めとして、複数の国際美術展において名誉ある評価を獲得されております」
画像が、冬堂が生前獲得した様々なタイトルのリストに切り替わる。
「今回のオークションは、冬堂先生の創作活動を長年にわたり支援してこられた方々の特別なご厚意により、当社において企画、本日実現の運びとなりました。出品者様、また関係の皆様に、この場をお借りしまして心より御礼を申し上げます。競りの開始の前に、岬冬堂先生のご冥福をお祈りし、一分間の黙禱を行わせていただきます。─黙禱」
会場の全員が目を閉じ、しばしの沈黙が辺りを満たした。
「ありがとうございました。それでは、競りに入らせていただきます」
モニターの表示が、一個の小ぶりな花入の画像へと切り替わった。今回は出品作がすべて壊れものである陶芸品なので、移動による不慮の事故を防ぐため、競りの際に実物の提示はされない。続いて画面の端に、日本円、米ドル、ユーロ、中国元、韓国ウォンでの金額表示欄が現れた。
「ロット・ナンバー一番、自然釉花入─」
作品名とその特徴を告げながら、椎名は満席の客たちの顔をぐるりと見回した。これまでオークショニアを経験した時とは、客層が明らかに違う。
(……進行が、多少ぎこちないとしても)
腹の底で、ぐっと気合を入れる。
(このお客さんたち全員に、「今日はいい競りだった」と思ってもらうんだ)
(続きは本誌でお楽しみください。)